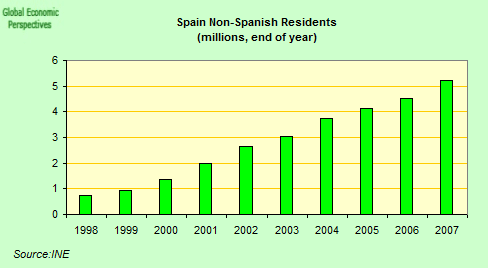このところあるプロジェクトで、現在失職していて求職活動中だが、まだ職に就くことができないでいる人々に、現代の「仕事の世界」に関わる話をしている。参加者の年代は、20代から60代にわたり毎回100人を越える。これまでの社会経験もそれぞれ異なる人たちなので、話のトピックスの選び方がきわめて難しい。雰囲気も毎回異なる。そのため、一般論から初めて、聞き手の反応を待って、次に進むという形にしている。一方通行ではなく、相互に時代の動きを打診し合うような試みだ。
最近のひとつの話題は、失業している場合には「どんな仕事でもないよりは(言い換えると、失業よりは)よいか」というテーマだ。ここで「どんな仕事でも」というのは、暗に短期で賃金の安い仕事を意味している。これは一般論としても、かなり答えるのが難しい。さまざまな条件が関わるからだ。
ある調査では、失業者はたとえ一時的な仕事でも、失業しているよりは仕事に就いた方がよいという答を出している。その仕事が低賃金で質の悪い仕事であるとしても、努力して次のより条件の良い仕事へ移行する架け橋の意味を持たせられるという。確かに、履歴書などに空白の期間があると、応募の時にそれを指摘されて不利になるという見方もある。雇用保険給付などの財政負担も軽減するから、失業から脱却するという意味では、好ましいといえるかもしれない。
他方、これとは異なった考えもある。失業状態から脱却しようと、先のことを考えることなく、目の前に提示された短期の低賃金の仕事に移ると、それが足かせになって、その後の労働条件を制約してしまうという。前に安い賃金の仕事に就いていたのだから、高望みなどしない方がいいという話にもなってしまう。
デトロイトで、失業して社会保障給付などで生活している人々を労働市場へ引き戻そうと、”Work First” というプログラムが実施されたことがある。それによると、失業状態から一時的な仕事に就いた人々は、その後、就業前の2年間と比較して年収レベルで1000ドル近い低下になったという。他方、がんばって目の前の短期の仕事を選ばず、長期のフルタイムの仕事に就いた人は、仕事の安定性が寄与して、年収レベルで2000ドル上昇したという。
一時的な(有期の)仕事に就くと、失業期間は短くてすむかもしれないが、雇用が継続することで生まれるポジティブな効果が現れる前に再び失業状態に陥り、仕事探し、精神的にも落ち込みかねない過程に入ってしまう。他方、長期のフルタイムなどの安定した仕事に就くためには、良い仕事が提示されるまでの待ち時間に加えて、新たなスキルの蓄積なども必要であり、再就職できるまでのストレスも大きい。
求職者の考えもそれぞれの人が置かれた状況で、かなりの振幅で浮動する。景気の上昇期には、転職することが賃金水準の上昇につながるとの考えが有力だった。しかし、今のように不況が長引くと、求職者の考えもひとつの会社にできるだけ長く勤めたい、勤められるような仕事に就きたいという考えに傾いてくる。「上昇志向」よりは「安定志向」ともいうべき考え方だ。過去20年くらいの新卒者などの就職に関する動向調査などをみると、驚くほど振幅がある。
こうした志向の現れ方には、かなりの個人差もある。その人が置かれている条件で相当異なってくる。いずれか一方が正解という二者択一の道ではない。職業ガイダンスは、応募者が置かれているマクロ・ミクロの状況をしっかりと見極め、適切な方向付けをしなければならない。「仕事の世界」についての深い理解と洞察が求められる。安易な「キャリア教育」と称するプログラムを義務教育段階や高校、大学に導入しても、それが望ましい効果を発揮するか、保証はできない。実際、かなり疑問がある。そして今、「仕事の世界」には地殻の大変動のような変化の兆しが感じられる。ブログではとても扱えない問題だ。しばらく耳を澄まし、その鼓動を探りたい。