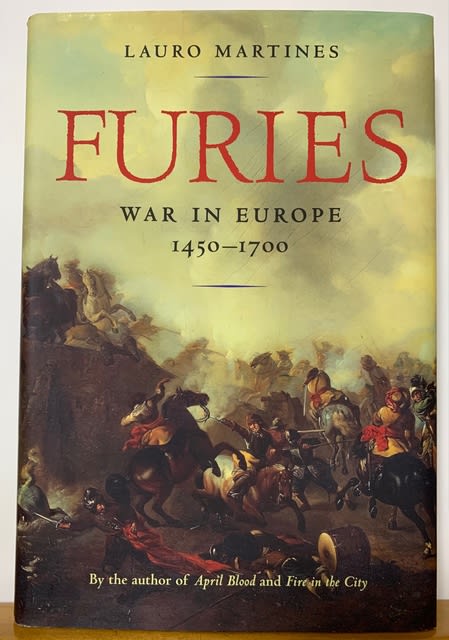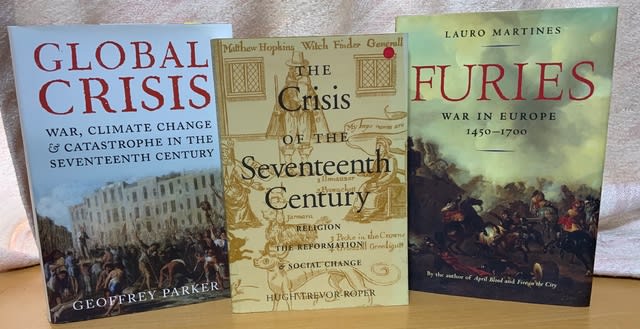レンブラント・ファン・レイン(1606-1669)
《フローラ》
1654年頃 油彩/カンヴァス 100×91.8cm
メトロポリタン美術館
父コリス・P・ハンティントンの思い出として、アーチャー・M・ハンティントンの寄贈
1926 / 26.101.10
1926 / 26.101.10
コロナ禍、ウクライナへのソ連侵攻など、騒然とした世界だが、絵画や音楽は荒んだ世の中にしばし癒しの風を吹き込んでくれる。前回に引き続き、現在開催中の「メトロポリタン美術館展」からブログ筆者の心に残る別の一点を選んでみた。これだけは記しておきたいと思う逸品でもある。今回の日本での展示は同美術館が所蔵する作品で「西洋絵画の500年」を表現するというテーマである。展示には多くの傑作、名画が含まれているが、ひとりの画家の企画展とは異なり、いかなる大家であっても、複数の作品を展示することは回避されている。それにしてもひとつの美術館の所蔵品だけでこの大テーマを語ることができるのは驚異的だ。出展されているのは同館所蔵の西洋絵画2500点余から選ばれた 65点であり、内46点は本邦初公開とされている。
今回取り上げるのは、17世紀オランダの巨匠レンブラントが描いた《フローラ》である。ブログ筆者のお気に入りの一点でもあり、本ブログでも以前に記したこともある。広く肖像画の範疇に入る作品だが、大変美しく優雅な印象を与える。日本には1976年にも来ている作品である。
筆者がこの作品に接したのは、はるか昔1965年のことであった。それ以降、今日まで何度も見る機会があったが、見るたびに新しい発見があった。もしレンブラントの作品で《フローラ》という画題をつけるとすれば、この作品が最もふさわしいのではないかと思うほどになった。
この作品に惹かれるようになったひとつのきっかけは、同じレンブラントの名作《ホメロスの胸像を見つめるアリストテレス》に接してからであった。
春、花、豊穣を司る古代ローマの女神フローラは、ルネサンス期に多くのイタリアの画家が描いており、レンブラントのこの作品も16世紀ヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノ・ヴェチェッリオの画風、とりわけ《フローラ》(フィレンツェ、ウフィツィ美術館所蔵)の影響を受けているとされる。この作品( 制作年 1515–20 頃)は現在はウフィツィ 美術館が所蔵するが、1641年までしばらくアムステルダムにあった。レンブラントがこの作品を見たかどうかは定かでないが、影響を受けていることは、対比してみるとほとんど明らかだ。
今回取り上げるのは、17世紀オランダの巨匠レンブラントが描いた《フローラ》である。ブログ筆者のお気に入りの一点でもあり、本ブログでも以前に記したこともある。広く肖像画の範疇に入る作品だが、大変美しく優雅な印象を与える。日本には1976年にも来ている作品である。
筆者がこの作品に接したのは、はるか昔1965年のことであった。それ以降、今日まで何度も見る機会があったが、見るたびに新しい発見があった。もしレンブラントの作品で《フローラ》という画題をつけるとすれば、この作品が最もふさわしいのではないかと思うほどになった。
この作品に惹かれるようになったひとつのきっかけは、同じレンブラントの名作《ホメロスの胸像を見つめるアリストテレス》に接してからであった。
春、花、豊穣を司る古代ローマの女神フローラは、ルネサンス期に多くのイタリアの画家が描いており、レンブラントのこの作品も16世紀ヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノ・ヴェチェッリオの画風、とりわけ《フローラ》(フィレンツェ、ウフィツィ美術館所蔵)の影響を受けているとされる。この作品( 制作年 1515–20 頃)は現在はウフィツィ 美術館が所蔵するが、1641年までしばらくアムステルダムにあった。レンブラントがこの作品を見たかどうかは定かでないが、影響を受けていることは、対比してみるとほとんど明らかだ。

ティツィアーノ・ヴェチェリオ
《フローラ》Flora ca.1515-1520年
油彩、カンヴァス 79.7 X63.5cm
ウフィツィ美術館、フィレンツェ
《フローラ》Flora ca.1515-1520年
油彩、カンヴァス 79.7 X63.5cm
ウフィツィ美術館、フィレンツェ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
N.B.
レンブラントには、最愛の妻サスキアあるいはサスキア亡き後、内縁のヘンドリッキェ・ストッフェルをモデルにしてフローラを描いたとされる作品が複数点ある。と言っても、画家が画題として明記したわけではない。画家自身あるいは後世のコレクター、画商、美術史家などが、推定した結果である。
フローラのイメージと重なる作品としては、次のようなものがある:
1633年 《レンブラントと婚約して3日後のサスキア・アイゼンビュルフ》
ベルリン 国立絵画館版画素描室
1634年、《新妻サスキアを描いた作品》(エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク)
1635年《フローラ(サスキア・アイゼンビュルフ )》 (ナショナル ギャラリー、ロンドン)
1654-55年頃《フローラ(に扮したヘンドリッキェ・ストッフェルス)》(メトロポリタン美術館、ニューヨーク)
以上の他にも、サスキアをモデルとしたと推定される作品は多い。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
N.B.
レンブラントには、最愛の妻サスキアあるいはサスキア亡き後、内縁のヘンドリッキェ・ストッフェルをモデルにしてフローラを描いたとされる作品が複数点ある。と言っても、画家が画題として明記したわけではない。画家自身あるいは後世のコレクター、画商、美術史家などが、推定した結果である。
フローラのイメージと重なる作品としては、次のようなものがある:
1633年 《レンブラントと婚約して3日後のサスキア・アイゼンビュルフ》
ベルリン 国立絵画館版画素描室
1634年、《新妻サスキアを描いた作品》(エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク)
1635年《フローラ(サスキア・アイゼンビュルフ )》 (ナショナル ギャラリー、ロンドン)
1654-55年頃《フローラ(に扮したヘンドリッキェ・ストッフェルス)》(メトロポリタン美術館、ニューヨーク)
以上の他にも、サスキアをモデルとしたと推定される作品は多い。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
《アリストテレス》と《フローラ》

在りし日のハンティントン邸の書斎
2 East Fifty-seventh Street, New York
1919-25年頃
Source: Esmee Quodbach
1919-25年頃
Source: Esmee Quodbach
ブログ筆者がレンブラント《フローラ》(メトロポリタン美術館)に魅せられたのは、オランダ美術のアメリカにおける受容の過程を探索していた過程であった。この作品はメトロポリタン美術館の所蔵になるまでは、アメリカの富豪ハンティントン家の邸宅に飾られていた。その様子を示す古い写真が残っている(上掲写真)。興味深いのはこれもレンブラントの名作《ホメロスの胸像に手を伸ばすアリストテレス》と並べて掲げられていた。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
N.B.
ハンティントン家書斎に掲げられていた4点の作品(右から)
1)サー・ジョシュア・レイノルズ《レディ スミスと子供たち》はコリス ハンティントンが1895年に購入、1925年にメトロポリタン美術館に”1900年遺贈”の一部として贈られた。
1)サー・ジョシュア・レイノルズ《レディ スミスと子供たち》はコリス ハンティントンが1895年に購入、1925年にメトロポリタン美術館に”1900年遺贈”の一部として贈られた。

2)レンブラントの《ヘンドリック・ストフェルズ》、

3)《ホーマーの胸像とアリストテレス》

4)《フローラ》(アルソップのスペンサー伯爵の所有であったが1919年にハンティントン夫人が取得)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
レンブラントの作品《ホメロスの胸像に手を伸ばすアリストテレス》では、アリストテレスは、右手を伸ばし、ギリシャ叙事詩の創始者であるホメロスの胸像に触れて、ホメロスの精神的遺産について黙考している。ホメロスは知性と倫理の力の模範とされてきた。しかしアリストテレスの顔色を見ると血色が悪く疲れた表情に、深い悲しみがたたえられている。深く考える人間に固有の精神状態であるとみられ、「憂鬱」メランコリアには特別の意義が認めてきた。ルネサンス期の哲学者たちは「憂鬱質」を黒胆汁の過剰によって生じるものとしてきた。17世紀の著述家、哲学者、芸術家などがこの状態に傾斜し、憂鬱が流行していたといわれる。アルブレヒト・デューラーの《メランコリア》を思い出す人もいるかもしれない。
ホメロスの首にかけられたアレクサンドロス大王から下賜された肖像画がついた金のメダルは世俗世界を体現するものと考えられてきた。ホメロスはアレクサンドロス大王の家庭教師であった。ホメロスの精神的価値と世俗価値との間の緊張関係は17世紀においても、考えられるべき真摯な道徳問題だった。
ホメロスの首にかけられたアレクサンドロス大王から下賜された肖像画がついた金のメダルは世俗世界を体現するものと考えられてきた。ホメロスはアレクサンドロス大王の家庭教師であった。ホメロスの精神的価値と世俗価値との間の緊張関係は17世紀においても、考えられるべき真摯な道徳問題だった。
この作品におけるアリストテレスは、離れてみると堂々とした哲学者の姿に見えるが、画面に近づくとその姿は絵具の色彩の中に埋没してしまう。これは「粗い仕上げ」として知られる技法の極致の発露である。この様式を最初に試みたのはイタリアの画家ティツィアーノであるといわれ、レンブラントはこの技法を様々な作品で試みている。
レンブラントの《フローラ》は、横向きであり、ティツィアーノの《フローラ》の正面とは異なっているが、官能的に肌を露出することもなく、左手に手繰り寄せたエプロンから右手で取り出した花を差し出している。そして白い生地の衣装はティツィアーノのフローラのように、袖口がゆったりとしている。この衣服の描写には、レンブラントがティツィアーノの作品を十分に意識して取り入れていることが見てとれる。細部は「粗い仕上げ」だが、全体としてみると、大変美しく春、花の女神としての雰囲気が画面から伝わってくる。ティツィアーノよりシンプルに描かれているが、《ホメロスの胸像に手を伸ばすアリストテレス》に勝るとも劣らない作品に仕上がっている。
モデルはレンブラントの最愛の妻サスキアあるいは内縁のヘンドリッキェともいわれてきたが、そのどちらでもないように思われる。画家は理想としての春と花の女神フローラのイメージに在りし日のサスキアを重ねて、現代風に描いたのではないか。今回の展示では見逃せない指折りの作品と思われる。

Esmee Quodbach, The Age of Rembrandt: Dutch Paintings in the Metropolitan Museum of Art (cover)
The Mwtropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Heaven and London, 2007