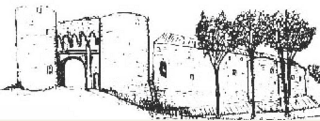『山の郵便配達』が語る仕事の世界
われわれが失ったもの
IT革命の時代、筆をとって手紙を書くことが目に見えて少なくなった。自筆の手紙には、単に文章にとどまらず、書く人のさまざまな思いがこめられていて捨てがたい。しかし、Eメールの利便性には逆らえないものがある。葉書や便せんに向かい筆をとるまでに立ちはだかる、見えない壁を、Eメールはかなりの程度取り払ってくれた。今や「メール語」ともいうべき独特の表現やルールが行き交うまでになった。しかし、この変化の過程で、私たちは明らかになにかを失ってしまった。
数年前、一部の人々の間で大変注目を集めた中国映画『山の郵便配達』(監督:霍建起)は、それがなにであるかを知らせてくれる。全編、清爽感に満ち溢れた佳編である。舞台は1980年代初頭、中国湖南省の山岳地帯である。そこで長年郵便配達を勤めてきた初老の男( 滕汝駿)が、健康上の理由で仕事を息子に譲ることになり、引継のために一緒に2泊3日の旅に出る。突き放していえば、ただそれだけの話で、波瀾万丈の場面があるわけではない。しかし、そこにはこの仕事一筋に勤めてきた男と一人息子のこれまでの人生が凝縮されている。そして、脇役であるが、人間以上の活躍を見せる「次男坊」と名づけられた犬(警察犬だそうだが、映画の舞台には過ぎた名犬)と主人公の男の妻、そして旅の途上に出会う数々の印象深い人々がこの感動深い映画を彩っている。
人生の奥深さ
映画からは、見方によって実にさまざまなことを汲み取ることができる。現代社会で失われた親子の対話の重み、人生における仕事の意味や仕事の尊さ、地味だがかけがえのない仕事をしてくれてきた主人公への人々の信頼、青春の輝き、人生の充足感と寂寞感などが、情 趣豊かな画面から感じ取れる。
重い郵便物が入った背嚢を担ぎ、一日40キロ近い山道を歩き、点在する山村の家々に手紙や伝言を届け、時には一人暮しの失明した老婆の相談相手などを勤めながらの旅である。山道といっても、大変けわしく、主人公はこれまでに崖から転落し、村人に救われたり、凍るような冷たい川を渡って、足を痛めたりしている。彼が引退を決めたのは、この冷たい川を渡るということで足を痛めたことが原因のようだ。
長年にわたり、主人公の男は一人黙々とこのつらい仕事を誠実に果たしてきた。男は自分の仕事が持つ意味と責任を十分に理解し、多くの日々を妻や息子と離れて、山中の一人旅に過ごすという人生を送ってきた。この寡黙で責任感の強い男が、自分の人生のほとんどすべてであった郵便配達の仕事を一人息子に引き継ぐ旅は、最初はぎくしゃくしたものであった。息子は父に対する強がりもあってか、道案内はいらない、一人で行くから大丈夫だという。しかし、父とともに旅の労苦を共にしてきた道案内役の犬「次男坊」が、当日朝になる と息子についていかないのだ。結局、行く予定のなかった父が「次男坊」を引き連れ、息子と旅を共にすることで、この映画は始まる。
仕事の尊さ
一人で心細い旅をしなければと不安顔であった息子も、父と次男坊が同行してくれることになり、にわかに明るくなる。しかし、はじめは父と息子の間にあまり会話はない。しかし、狭い急峻な山道で、出会った村人とうまくすれ違うことのできない息子に父は、そういう ときは山側に寄るのだというルールを教える。郵便物を粗雑に扱うことのないように、厳しく対応する父親、村人の父に対する絶大な信頼感、時折はさまれるこれまでお互いに知らなかった出来事についての回想などを通して、父と息子の間には次第に会話が生まれる。一見平凡な仕事をしていたかに見えた父親の計り知れない労苦、妻や息子への愛情を息子は感じ取る。そして、父親も出かける時ははたして仕事がつとまるだろうかと思った息子が、旅の終わりには立派に成長していることを知り、安堵と幸せな思いにふける。
峻険な山岳地帯にもバス道路が開かれつつあり、重い背嚢を背負っての郵便配達という仕事がいずれは消えてゆく仕事であることを暗示している。しかし、男は自分が果たしてきたこのつらい仕事に大きな誇りを感じ、誰も引き受けない仕事を息子がひき継いでくれること に喜びを感じている。父親が健康を損なうことになった冷たい川を渡るとき、息子が父を背負い、川を渡る。その時、息子からはじめて「父さん」という言葉が発せられ、当惑とともに喜ぶ父親の表情がなんともいえない。
原作にはないが、映画では登場し、いつも村の出入り口の橋で夫の帰りを待つ母親役のベテラン女優(趙秀麗)も役柄をしっかりとこなしている。この美しく賢い母親と「次男坊」と呼ばれるシェパードが、目立ちすぎるくらいの立派な脇役なのだ。中国の奥深い山岳地帯にも入り込んでくる近代化と称する変化は、いつまでこうした人間味あふれた世界をとどめることができるのだろうか。映画は、失われて行く牧歌的ともいえる時代の「労働のかたち」を見事に映し出して終わる。(2001年6月8日記)
旧ホームページから転載(一部加筆)