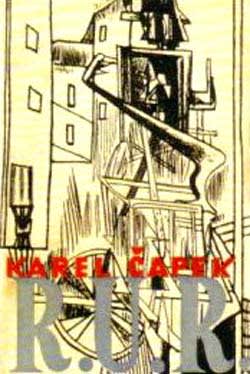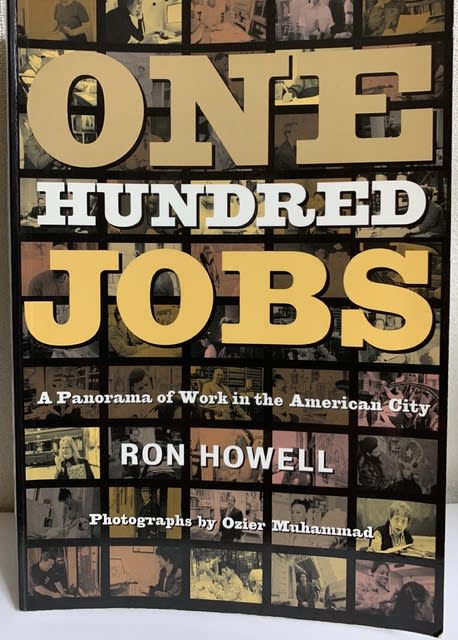
Newsboy, St.Louis, Missouri, 1910
(Source:R.Freedman) 拡大は画面クリック
一枚の写真や絵画が時にさまざまなことを思い出させる。「断捨離の時代」の流れに身を任せたわけでもないのだが、なお捨てがたく残っていた書籍資料の整理をしていると、ある写真に目が止まった。ブログにも何度か記したことのあるアメリカの写真家ルイス・ハインの写真を題材とした児童労働についての小冊*である。その中の一枚が上掲の写真である。これまで折に触れ何回か見てきた写真集なのだが、あまり気にとめることのなかった光景であった。ルイス・ハインが残した写真はあまりにも多いので、その映像群の中に埋没していた。写真家が被写体として焦点を当てたのは、20世紀初め、ペーパーボーイ paperboy(or newsboy) と呼ばれた新聞の売り子である(数は少ないが、ぺーパーガール papergirl もいた: 最下段写真)。
ペーパーボーイの原風景
新聞の各家庭への配達が一般化している日本では、人々が町中で新聞を買うのはスポーツ紙などが中心で、それも駅などの売店である。最近では、紙の新聞ではなく、ディジタル版を読む人も増えているようだ。かつて滞在したアメリカやヨーロッパの国々などでも、ほとんどの家庭は新聞は購読していないか、必要な時だけ買い物の途上でスーパー・マーケットや雑貨ストアなどで買っている人が多かった。家庭への配送は新聞代金に配送料が加算された。
新聞産業が盛期にあった頃は、アメリカやイギリスでも、 paperboy(papergirl)が自転車、時にはモーターサイクルで、各家に新聞を配送していた。しかし、新聞産業が急速に衰退するとともに、こうした配達方式は急速に衰えた。この写真は、その配達システムが未だ普及していなかったころ、いわばpaperboyの初期の姿をとどめた貴重な画像といえる。
ペーパーボーイの職場
20世紀前半の頃、アメリカでは新聞はしばしば街頭などで、paperboyから出勤途上などに買い求めることが多かった。新聞を売るのは主として幼い子供たちで、小脇にその日売れるくらいの数の新聞を抱え込み、通りがかりの客に売っていた。1日に売れる紙数は知れたものだったが、子供たちは親方から買った新聞を売って、わずかな金を得ていた。貧しい家計の足しにもなっていた。いつも同じ所に立って、新聞を売っていると、なじみの客も出来て、時にはわずかな釣り銭などをチップにくれることもあった。
大体、6,7歳から仕事を始め、真夜中に近く、新聞が印刷される時間に印刷工場へ行き、自分で売れると思う部数の金を支払い、小さな腕に抱え込んで、駅や街頭へ走って行った。彼(女)らが立って新聞を売る場所は、年齢や力関係で決まっていた。仲間の間で縄張りがあり、しばしば喧嘩騒ぎが起きた。日給とか週給など、決まった支払いなどなく、売れなかった分は少年の損失になった。売れ残った新聞を身体の下に敷いて、階段で眠り込んでいる少年の写真も残っている。彼らは、孤児か、きわめて貧しい家庭の子供たちであり、ホームレス状態も珍しくなかった。ニューヨーク市の場合は、Children's Aid Society と呼ばれる慈善団体が雨露をしのぎ、貧しいながらも食事を安価で提供する場所を運営しており、そうしたところに寝泊まりする子供もいた。
ペーパーボーイと小さな貴婦人
さて、この上掲の写真、改めて気がついたのは、写真家が画面の左側に含めた若い少女の姿である。明らかに豊かな家の少女であることがわかる。大人たちは今日はニュースがないと思うのか、ペーパーボーイを無視して、通り過ぎてゆく。新聞が売れず、うらめしそうな顔をしているペーパーボーイの存在など目に入らないようだ。他方 、少女は少年と年齢的にはほぼ同世代だろうか。雨模様の日なのだろう。きちんとレインコートを着て、傘を小脇に抱え、髪が乱れないように美しい帽子まで被って、小さなレディ(貴婦人)が颯爽と通り過ぎてゆく。
ここで注目したいのは、今日世界的に注目を集めている児童の貧困、そして彼らの間に存在する貧富の格差が、すでにこの時代にさまざまな形で露呈していることだ。ルイス・ハインは繊維工場や炭坑、農場で働く子供たちの姿ばかりでなく、「ストリート・キッズ」 Street kids と呼ばれた都市で働く子供たちの画像も多数残している。彼らは新聞売り、靴磨き、荷物運び、薪、石炭、氷などの搬送など、「苦汗労働」 sweatshops といわれた、ありとあらゆる厳しい仕事の分野で働き、日々を過ごしていた。これらの子供たちの中には、花、靴紐、リボン、キャンディなどを売ったりして、家計の足しにしていた者もいた。今でも、開発途上国でしばしば見かける光景でもある。
今も昔も
最近日本では高齢者の貧富の格差がしばしば議論に上がっている。他方、子供の間にも貧富の格差があり、明らかに拡大していることが判明している。「貧困」の定義はいくつかある。国民の平均的な所得の半分を「貧困ライン」と呼ぶが、その基準に満たない所得の低い世帯の子供たちが、2012年の統計でみると、6人にひとりは該当し貧困状態にあるといわれている。貧困をもたらす背景はさまざまだが、とりわけ深刻なのは、母子家庭など「ひとり親世帯」の子供で、貧困率は54.6%、実に2人に1人を超えている。子どもの貧困は、次の世代を生きる人たちのありかたに深くかかわっている。高齢者の貧困より見えにくい子どもの貧困は、この国の来るべき姿、社会のありさまを定める。アジアの周辺諸国などからみると、うらやましい国に見える面もあるが、貧困は絶えることなく深く日本の社会に根をおろしているのだ。
現代の人は見たことがない、あるいは見ても見過ごしてしまうような一枚の写真だが、国の違いを超えて100年前の世界と今をしっかりとつないでいる。
「断捨離」の仕事はまったく進まない。
papergirls
Reference
Russell Freedman, KIDS AT WORK: LEWIS HINE AND THE CRUSADE AGAINST CHILD LABOR, New York: Clarion Books 1994
ルイス・ハインの残した写真はきわめて多いので、それらを編集した出版物もかなりの数にのぼる。日本では労働や仕事の世界を記録に残した写真は少ない。写真家を志すみなさんの中で、後世のために、歴史を変えた一枚の写真」を試みる方はおられないだろうか。
★ 「児童労働」とは、法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害します。
ILOが定める就業最低年齢の国際基準については、ILO第138号条約。
出所:ILO駐日事務所HP
ある辞典編纂のお手伝いをしている過程で、気がついたことがあった。変化が激しいご時世、使われる言葉にも盛衰があり、辞典に採用すべき用語の取捨選択がひとつの仕事となる。採択候補の用語の中に、「サラリーマン」があった。いつの頃からか、見聞きすることが少なくなったと思ってはいた。とはいっても、まだ死語になったとはいえまい。しかし、なんとなく過去の響きがある。もともと「サラリードマン」salaried man が日本語化したものであり、俸給生活者、給料生活者、月給取りという意味である。そういえば、「ホワイトカラー」、「ブルーカラー」も色褪せた感じがする。
折りしも、新年の英誌The Economistが、「さようなら、サラリーマン」 'Sayonara, salaryman' *という短い記事を掲載していた。雑誌記事だけにそれなりの誇張はあるが、日本社会の問題を鋭く突いている。読みながら、改めて考えさせられてしまった。そこで、少しばかり思い浮かぶことをメモしてみた。
サラリーマンは、戦後日本の発展を支えてきた主柱の一本だった。敗戦の灰燼の中からたくましく立ち上がった日本経済の担い手になってきた。
「サラリーマン」という言葉には、長らく誇らしげな響きがあった。彼ら一人一人が会社を背負っているように見えた。その組織のメンバーとなることは、それ自体が将来の成功を約することであり、堅実な中産階級の一員である証だった。
彼らはキャリアよりも会社を選んできた。坂の上に光が見えていた時代、会社の成長は、彼ら自身の社会的上昇とも重なっていた。しかし、そうしたイメージは1990年代、バブルの崩壊とともに急速に後退した。
日本のサラリーマンは、しばらく世界もうらやむ存在であった。彼らはひとたび職を得た会社に強い忠誠心を抱いていた。特に問題がないかぎり定年にいたるまで献身的に勤続することを当然と考えていた。しばしば家庭を犠牲にしてまで長時間働き、会社に貢献してきた。家族もそれを当然のこととしてきた。日本の労働者はどうしてそれほどまでに働くのか。なにが彼らをそうさせているのか。日本経済が世界をリードしていた1990年代初めまで、彼らと企業との関係には、多大な関心が寄せられた。西欧の人々が思い浮かべるパターナリズムの一言で片付けられないものが、明らかにそこにあった。
強い共同体意識が組織を長らく支えていた。しかし、1990年代バブル崩壊後の長い経済停滞は、企業の風土を大きく変えてしまった。厳しい競争原理の風が組織に吹き込まれ、サラリーマン社会の牧歌的イメージは急速に荒涼たるものへと変化してゆく。パートタイム労働者、派遣労働者、契約社員など、さまざまな非正規雇用と呼ばれる雇用形態が市場に溢れ、「格差社会」の議論がメディアを賑わすようになった。企業社会の荒廃のすさまじさと労働条件の劣化。そこに起こった激しい変化の諸相は、労働者ばかりか使用者の想像をも上回るものであった。
The Economist誌は、日本は変化しているが、その速度は大変遅いとしている。最近の政治の膠着、混迷の状況を見ていると、確かにこんなことをしていたら日本はどうなるのだろうかという思いも強い。他方で、現実は政治の遅滞を置き去りにして、急速に変化もしている。
同誌が風刺を込めて記しているように、長時間労働、実質賃金の停滞など、劣化が著しい仕事と生活の関係に対しての処方箋として、「ワーク・ライフ・バランス」という外国の概念が使われている。「外国に学ぶものはなくなった」という傲慢な言葉が聞こえたのも、そう古いことではない。同誌は、一人の若いサラリーマンの言葉を借りて、「(過去はともあれ)この組織は機能しなくなった。それはあまりにも長く続き過ぎたのだ。システムは錆びてしまった」と結んでいる。
現実はともかく、「サラリーマン」を廃語にするのは忍びない。過ぎし日の記憶を留めるためにも、用語としては残すことになった。
* 'Sayonara, salaryman' The Economist January 5th 2008.
トヨタのロボット(ヒュマノロイド)
ロボットは人間を超えるか
高いロボットの出生率
最近の国際ロボット協会と国連の統計によると、世界で「働いている」ロボットの数は急速に増加しつつあるようだ。多目的型の産業用ロボットの販売(価額)は、昨年世界全体で17%伸びた。そのうち日本は稼動台数で35万台以上を占めている。世界最大のロボット王国だ。生産性を考えると、100万人を超える数のロボット労働者が働いているともいえる。ドイツなどいくつかのヨーロッパ諸国でもロボットは増え始めた。ロボットの出生率(?)はきわめて高いのだ。
人間の嫌がる仕事をするロボット
なぜロボットは増えているのか。この背景にはいくつかのことが考えられる。ロボットが多数働いている国は、日本、ドイツ、アメリカなど先進国が多い。イタリア、韓国、台湾、フランスなどがこれに続く。これらの国では、とりわけ製造業での人件費が高く、人手不足が進行している。ロボットはその不足を埋めているのだ。
この点については、いずれの国でも失業者が多いではないかという疑問があるかもしれない。確かに若者、中高年者などの失業者は多い。しかし、彼らは仕事の空きがあっても、必ずしも仕事に就くというわけではない。自分のやりたい仕事がなければ、働かない。
1980年代後半に、日本のマスコミが使い、その後世界に知られるようになった「3K労働」という領域がある。若者が就労しないので、使用者は不況下にもかかわらず人集めに苦労する。外国人労働者など不安定な供給源に頼ることにもなる。しかし、安定した操業のためには、安定した労働力の供給が望ましい。
人間のできないことをするロボット
このような状況では、ロボットはきわめて頼りがいのある働き手である。ロボットは「誕生」すると、その日から直ちに働くことができる。教育や訓練の期間も必要ない。不満もいわず、ストライキをすることもない。工場の照明が消えていても、黙々として働く。 もちろん、今日の段階では、ロボットが活躍する領域には一定の限度がある。
ロボット労働者は、今のところ臨機応変な対応が常に要求されるような仕事は苦手だが、仕事の内容が定型化できるような職場は人間以上に得意である。自動車工場の溶接、塗装など、労働条件がきびしい職場は、最初にロボットが導入された職域である。
ロボットの生産はしばしばロボットが担っている。ロボットがロボットを作っているのだ。人間の労働者がほとんど見えない工場で、ロボットが黙々と?動いているのは、その意味を考えると衝撃的である。
こうして誕生したロボットの生産性は高い。人間の労働者の何倍もの仕事をしてくれる。先進国では人間の労働者の賃金は高い。人口も多い開発途上国の賃金と比較すると、他のコストが同じならば、太刀打ちできない。しかし、トータルな生産性を考えると、ロボットが活躍する余地は大きい。中国、ヴェトナムなど賃金コストの低い海外への仕事の移転が懸念される産業でも、再び生産の場が日本へ戻ってくる可能性も高い。 日本の出生率の反転上昇がほとんど見込めない以上、ロボットに期待する部分は大きい。
ロボットに税金をかける日?
対人サービスなど、複雑な対応が要求されるサービス業では、ロボットの「職域」はおのずと限度がある。しかし、これからのサイボーグ技術の発展を考えると、数十年後には人間とほとんど変わらないロボットが生まれる可能性はきわめて高い。もしかすると、アンドロイド(人造人間)として、日本のように働き手が少なくなる一方の人間労働者に代わって、ロボットが課税対象になる時が来るかもしれない**。
台湾で開催された国際会議で、「新しい仕事の世界の次元」Emerging Dimensions of a New World of Workというテーマで、こうした内容を一部に含めた話をした。時間が短いこともあってか、聞いている人たちは半信半疑、冗談を聞かされているのではないかと思ったようだ。遠い未来の話と思ったのかもしれない。
しかし、たまたま目にしたNHKスペシャル番組「立花隆:サイボーグ技術が人類を変える」*を通して、技術の最前線は私の想像以上に進んでいるのを知って衝撃を受けた。ジストニア(身体が意思とは関係なく動いてしまう病気)、パーキンソン病などが、脳コンピューター技術で日常生活に支障ないまでに改善されるのだ。人工内耳の発達で、難聴の子供がヴァイオリンを弾けるまでになる光景が示される。その光景は感動的ですらある。
ロボットが人間を支配する時
そればかりか、脳コンピューター・インターフェイスの発達は、脳を操作することまで可能になっている。遺伝子操作とともに、人類が科学技術をコントロールする力を失うと恐ろしい事態も生まれかねない側面もある。この分野の先端にいる科学者の話では、数年後にはこれらの技術は実用化段階に入るとしている。遺伝子工学も科学技術の進歩の名の下に、次第に規制が緩められている。科学技術の社会的コントロールは可能なのだろうか。TVを見ながら、あまり長生きをしない方が良さそうな気がしてきた。
Reference
*NHKスペシャル番組「立花隆:サイボーグ技術が人類を変える」 2005年11月5日
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/shiryou/soukyoku/2005/10/005.pdf
**「ロボットから税金を取る日は来るか」
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/eb3831765220f8a5d38b7aff405cb0a0
秋学期開始も近くなると、キャンパスへ学生が戻り、大学は活気を帯びてくる。今、アメリカの主要大学ではそれに合わせて、優秀な学生を採用しようとするリクルーターが多数訪れているらしい。大学生の就職市場も好転の兆しがあるようだ。 優秀な学生といっても、いろいろな見方があるが、企業側は成績に限ると上位10%くらいを対象にしているようだ。株主主権のアメリカ企業といっても、つまるところ企業は、それを構成する人材の質に大きく規定されている。やはり「企業は人」なのだ。
定着したインターンシップと採用内定
優秀な大卒人材を求める動きはこのところ活発になっていて、去年くらいまでは内定を3つくらいもらった学生ならば、今年は5つくらいに増えているらしい。そのために、夏に優れた学生にインターンシップを経験してもらい、本採用につなげたいという企業が多い。インターンシップはしばらく前までは、夏場など季節的調整のためのお手伝いと見られてきた。しかし、今ではフルタイム雇用の候補として採用する場合が多くなっているという。
たとえば、2000人近くになるGEの大卒採用者の60%は、インターン経験者とのことである。こうして多数のインターン経験者は、卒業年の夏には採用内定の通知を手にして、キャンパスへ戻ってくるらしい。
好感度の高い企業とは
企業は学生に好感度の高いという企業というイメージを植え込むのに力を入れている。そのため、1年中アメリカのキャンパスを訪ねては、学生や教員にコンタクトする専属のスタッフを置いている企業もある。たとえば、GEは戦略的にしぼりこんだ38大学に採用エネルギーを注いでいる。学生側としても、さまざまな形で能力を試されるので売り手市場というわけではない。
上位にランクされた企業は、それなりに努力をしていることが感じられる。PricewaterhouseCoopers (PWC) は会計事務所だが、200大学に対象を設定している。そして、企業の上級管理者層にあたるパートナーに採用の責任感を持たせ、年間200時間くらいは「キャンパスで同社とのつながりを持たせるよう」指示している。こうした努力は効果があるようだ。
Universum という大学ブランド・コンサルタントの企業は約3万人のアメリカ人学生に、彼らが入社したいという会社名を挙げさせた。2005年の調査では、PWCは第2位(04年は4位)、第一位はなんとBMWであった。かつてはMicrosoftが「君臨」していた座をドイツ企業が獲得したのだ。その人気は製品が「クール」だということにあるらしい。日本でもかなり変化してきたが、外資系企業という受け取り方は、ほとんどないようだ。
それにしても、しばらく前までは金融・投資関係の企業が上位に多数顔を出していたが、大分様子が変わってきた。
時流に乗っている企業
日本でも同じだが、学生は就職先の選択において企業の製品やサービスの社会的な認知度、内容などに大きな影響を受けるらしい。典型例は昨年41位だったApple Computer が今年は13位に急浮上している。その背景に世界的なiPod人気があることはいうまでもない。
とりわけ、アメリカらしいと思うのは、最近のTVや映画でFBI(Federal Bureau of Investigation)の活躍ぶりが人気を博し、138位から10位に急上昇したことである。CIAも同様である。アメリカの学生も、時の動きに大分左右されて就職先を選ぶようだ。
これも面白いと思われる現象は、EnronやArthur Andersenの社会的失墜も会計士分野には悪影響を及ぼしているわけではないという。会計士という仕事は、単に「数を数えている」だけの仕事ではなく、経営全般に采配が振るえるのだという印象が浸透して着実に応募者が増えているという。確かに、アメリカの4つの大会計事務所はすべて、今年の人気就職先に入っている。
重要となるウエッブ上のイメージづくり
また、最近の大学生は、就職先の選定に際してウエッブ上の企業イメージにも大分影響を受けているようだ。PWC, Microsoft, Ernst & Young などの各社は、この点の評価で金・銀・銅という評価を得た。企業としては、ウエッブ上の好イメージづくりに一段と力をいれざるをえない。
しかし、伝統的に個人的な対面、インタビューを重視して、そのために上級の経営者をキャンパスに出向かせ、学生に会い、スピーチをすることの方が良質な学生を獲得できるという企業も多い。GEの役員などは頻繁にキャンパスを訪問しているという。人材重視といわれてきた日本企業だが、役員が絶えず大学を訪問して、優秀な人材確保に努めている企業はどこだろうか。
2005 年の人気企業
(アメリカの大学生が理想の働き先と考える企業、事務所)
( ) 内は2004年
BMW 1 (2)
PricewaterhouseCoopers 2 (4)
Ernst & Young 3 (6)
Boeing 4 (7)
Johnshon & Johnson 5 (17)
Deloitte 6 (8)
Coca-Cola 7 (5)
Microdoft 8 (1)
CIA 9 (14)
FBI 10 (138)
Merill Lynch 11 (12)
IBM 12 (11)
Apple Computer 13 (41)
KPMG 14 (16)
J.P. Morgan Chase 15 (18)
Source: Universum Communication
Reference “Undergraduate recruitment” The Economist August 20th 2005
ケータイ文化が得たもの・失ったもの
急な仕事で北海道まで出かける。機内誌「翼の王国」(8月号)の頁を繰ると、どこかで見たような写真が掲載されていた。「中国電影旅行」Traveling China with 10 Movies と題して、10の中国映画作品ゆかりの地を尋ねるという構成である。その最初が「山の郵便配達を捜して」というテーマであの懐かしい映画の故郷へ行くという話である。このサイトでも2月21日「働くことの重み」で話題にしている。原題「那山、那人、那狗」(「あの山、あの人、あの犬」の意、1999年、監督は霍建起 フォ・ジェンチィ)。
郵便配達の仕事を描いているが、日本の郵政改革とは、まったく次元を異にした話である。日本の郵政改革は国民不在のままに、与野党の泥仕合の様相を呈して、今回の結末となった。いったい誰が責任を負うのか。腹立たしいかぎりである。
それに反して、この映画はストーリーこそ単純だが、仕事の尊さ、厳しさを教える感動的な映画であった。環境が違うということを別にしても、日本ではもう制作できないような精神性の高い作品である。
さて、雑誌の特集では、取材班は撮影のロケ現場を求めて、中国の奥地へと向かう。この映画のロケ地は湖南省綏寧であった。北京から桂林へ飛び、そこから車で綏寧まで入ったとのこと。苗(ミャオ)族が住む地域であるらしい。映画でも説明はなかったが、少数民族の村々であることは伝わってきた。そこには、今でも郵政代行所という小さな郵便局があり、1969年から36年勤続する于合松(ユィホォソン)という映画の俳優とは違うが、それを思わせるような54歳の郵便配達人が今でも村々をまわっていた。毎日30キロは山中を歩いているそうである。 映画では、主人公の父親と息子、そして犬が大活躍だったが、この地域では犬が大切にされてきたらしい。主人そしてその仕事の責任の重さを十分知って、縦横に働く犬の忠誠さが目に浮かぶ。
ケータイの時代の到来は、通信の世界を大きく変えてしまった。利便性は改善されたかもしれないが、失ったものも計り知れない。人間の心の深層にまで影響している。電車に乗ったとたんに反射的にケータイを取り出し、画面に見入る大人・子供。ケータイをなくしたと全財産を失ったようにパニック状態になる人。これはもう病気であるとしか思えない。ちなみに私は、ケータイは持ってはいるが、使用するのは月に数回。画面はモノクロのままである。まわりをみても、誰も使っていない旧型モデルである。それで不便を感じたことはほとんどない。
カレル・チャペック、「RUR」への連想
奇妙な言葉の氾濫
少子・高齢化の予想を上回る速度での進行、「2007年問題」といわれるまでになった「団塊の世代」の大量退職、そしてついにやってきた「大学全入時代」。さらに、「フリーター」、「ニート」と他の国ではほとんど使われない言葉を多数の人が口にする日本はかなり奇妙な国である。
「フリーター」はメードイン・ジャパン
ある辞書の執筆にかかわった時に知ったのだが、実際、「フリーター」は日本製?なのだ。語源はどうやら、「フリー」と「アルバイター」を接合させたものらしい。これでは英語freeとドイツ語Arbeiterの接着である。「アルバイト」は、昨今では「バイト」である。ドイツ人もびっくりでしょう。他方、いまや知らないと常識を疑われそうな?「ニート」NEET(Not in Education, Employment or Training)の語源はイギリスといわれているが、しばらく暮らしたイギリスではほとんど聞いたことがなかった。イギリス人でも知っている人は少ないが、日本ではティーンエイジャーがニートで困っているという話を聞かされると、強いヘアローションと細かい櫛で髪をきちんと(ニート neat, 発音も異なる)固めている若者を思い浮かべるというから、かなりの落差がある*。
こうした状況で、日本から例のごとく視察団がやってきて、イギリスは「ニート」の先進国?だそうだがと聞かれれば、大変面食らうだろう(ちなみに、日本は視察団の大変好きな国である。「ニート」問題でも多数イギリスへ出かけたらしい。)
深刻なのは労働力不足
ところで、人口激減時代に入った日本では、最近は公表される失業率もやや低下し、これでフリーターやニートも救われると報じているメディアもあるが、とても手放しで喜ぶ気にはなれない。現実に起きていることは、これまで経験したことのない深刻な労働力不足の先駆けである。とりわけ、土木建設や介護に携わる労働者が不足するだけである。失業者が多くの職種について、大幅に減少するわけではない。多くの若者がフリーターや失業状態でありながら、その裏側では日本人が誰も働こうとしない職場が確実に増えて定着してしまった。そこでは多数の外国人が働いている。
すでに10年ほど前のことになるが、まだ不況から脱却していなかった頃、静岡県の浜松市で、フィールド調査をしていた時、ある小企業の経営者が嘆いていたことを思い出す。「日本人の若者は半日もいませんよ。それに比べて・・・」と彼が手で示した先には中東系と思われる若者が3人ほど、真剣な顔つきで、油まみれで小さな機械を動かしていた。バブルで見せかけの豊かさを経験してしまった日本人には、もう見られなくなってしまった顔であった。
先が見えない日本
なぜ、こんなことになってしまったのか。思い当たる点は多々ある。しかし、過ぎ去ってしまったことを嘆いてもしかたがない。日本はこれからどうやって労働力不足に対応していくのか。このごろの政府は、目先の問題に追われてか、日本の将来についての構想はほとんど示さなくなった。少子高齢化対策は、根本的なヴィジョンに欠け、部品の寄せ集めのような印象である。これで、出生率が目立って回復し、子供が増えるとはとても思えない(実際、その後10年近く経過しても、出生数は激減一方である。
移民かロボットか
労働力不足に対応する道のひとつとして国際的な場で提示されてきた政策のひとつに移民受け入れがある。国連人口部が提案した先進国の人口減を開発途上国からの移民で補充する案は、ほとんどまともに議論されることなく忘れ去られている。これは人口減少の数の点だけをみた提案ではあったが、それを契機に質を含めて、日本のあり方をもっと議論すべきであった。
外国人の受け入れを増やして共存の道を模索することは、最近のテロ事件などをみても、かなりけわしい道のりとなる。10年近くも住んでいて隣人と思っていた人たちが、事件を起こしたとなると、どの国も開放政策には二の足を踏む。しかも、実効ある選択肢は限られている。国民的議論が必要である。
RURの時代?
もうひとつの道は、ロボットに手助けをお願いすることである。世界ではおよそ80万台の産業用ロボット(アミューズメント・ロボットなどは除く、2003年末)*2 が稼働している。その内、実に34万8千台は日本で動いている。ドイツの11万3千台、アメリカの11万2千台をはるかにしのいでいる。しかも、1台で何人分もの仕事をこなしている。
日本は世界でも突出した「ロボット王国」である。ロボットにはニートもフリーターもいない。文句もいわずに昼夜を問わず働いている。いずれ「国勢調査」の人口にロボット人口?を数える時代が来るかもしれないと思うのは、炎天下でのあながち妄想ではない。「ロボット」という言葉を初めて使ったチェッコの国民的劇作家カレル・チャペックは、その名作「RUR」(ロッサム・万能ロボット製造会社、1920年)の中で登場人物に次のように云わせていた。
バスマン ははは、こいつはいいや! ロボットはなんのために作るのか、だってさ!
ファブリー 労働のために、ですよ、グローリーさん。一人のロボットは二人半前の働きをします。人間の労働者ってのはね。グローリーさん、恐ろしく不完全なしろものでした。早晩その地位から追われるべき運命にあったんですよ。
バスマン そのうえ費用ばかりかかってね。
ファブリー 能率的じゃなかったんです。人間の労働者はもう近代産業の要求には応じきれません。しかるに自然のほうでは近代的労働と歩調を合わせる考えなどすこしもありませんからね。たとえば、技術的見地からすれば子供時代なんてものはまったく愚の骨頂でね、えらい時間の浪費でしかありません。そしてまた――
カレル・チャペック「RUR」『海外SF傑作選 華麗なる幻想』所収(深町真理子訳)、講談社文庫
Reference
* Neet generation Education Guardian.co.uk
*2 International Federation of Robotics (IFR)
★ 2014年現在、「フリーター」も「ニート」もほとんど使われなくなった。もしかすると、意味も忘れられているかもしれない。
このサイトの始まりを語る一枚の画像*が、アメリカの繊維工場で働く少女をとらえた一瞬であるのと関連して、このクレスピ・ダッダもイタリア北部の木綿紡績の工場を中心とした企業町 (company town)である。1970年代中頃に、ミラノへの旅の途上で訪れたことがあった。実は、友人のイタリア人に「クレスピ・ダッダ」ヘ行きたいと話すと、そんなところへなぜ行くのか、なにがあるのかと逆に質問されて当惑した記憶が残っている。
労働者の村」の実現
18世紀後半、イギリスから始まった産業革命は、世界各地へ波及し、資本家と労働者の激しい対立を生み出した。「持てる者」と「持たざる者」の格差は拡大し、深刻な社会・経済問題を生んでいた。とりわけ、労働者階級の状態は貧窮の方向へ進むばかりであった。そうした状況を深く憂慮し、自分の事業の範囲だけでも労資の対立のない平和な工業の町を創れないかと思った企業家がいた。クリストフォロ・クレスピというイタリアの豊かな資産家であった。一時は聖職を志したともいわれるが、クレスピは、1875年、ミラノに近いアッダ川に沿った土地に理想的な紡績工業の町を建設することを構想した。
当時の一般の繊維工業は、過酷な労働条件で知られていた。時代の先端を行く技術を使い、清潔な職場環境で、労働者の生活環境を充実したものにすれば、企業の生産性も高まり、良質な製品が作り出せると考えたのである。そして、工場の近代化、安全衛生の改善に努めるだけでなく、住宅、教会、学校、病院など、労働者の人間的な生活にふさわしい理想郷ともいえる都市を創り上げた。そこでは、工業化に伴って世界的に激増した労働争議も50年間にわたって発生しなかった。
古き良き時代のカンパニー・タウン
ミラノからイタリア人の友人に案内されて訪れたこのカンパニー・タウンは、すでにクレスピ家から人手にわたり、一部の設備を使って細々と生産を続けていたが、時代の荒波から取り残されたような静謐な、そしてどこかわびしげな町であった。しかし、壮大な水力発電設備、整然とした並木の残る町並みなど、あの時代に良くこれまでのことを実現したという印象が残っている。事業の最盛期であった20世紀初期には、おそらく労働者が生き生きとして働き、生活を楽しんだ理想郷であったのだろう。いわゆるアパートメントではない一戸建ての家々が立ち並び、それぞれに草花で飾られていた。会社から離れた後も、この地に住んでいる人々の思い出話は、かつての良き時代への追憶で溢れていた。そこには、資本家と労働者の間に一種の友愛と尊敬の念が生きていた。
消えてしまったユートピア
しかし、資本主義社会のユートピアともいえるクレスピ・ダッダも、世界大恐慌の大波に巻き込まれてしまう。企業が生き残るには労働者の解雇しか手段がなかったが、同社は従業員を解雇せずに操業を続け、ついに倒産してしまった。その後、創業者の手を離れ、経営が続けられたが、繊維工場としての命脈は尽きた。ヨーロッパ、アメリカ、そして日本でも「開明的」な産業資本家たちが、時には「ユートピア」実現の理想に燃えて生き生きと活動した時代があった。
私が訪れたこうした企業町の中には、アメリカの繊維工業の中心であったニューイングランドのローウエル、ドイツ、ザールブリュッケン近傍の陶磁器の町メトラッハなど、今でも強く印象に残るものが多い。メトラッハでは、独特の可愛いデザインで知られる陶磁器やタイル・メーカーのVilleroy and Boch社 (1748 年設立)が今日でも経営を続けており、工場で働く人々のために保育園まであった。日独の大家の先生方とご一緒する機会があり、Villeroy and Boch社が所有する素晴らしい迎賓館で過ごした思い出も懐かしい([ラ・トゥールを追いかけて~2~])。
これらのカンパニー・タウンを、たまたまその時代の開明的企業家のパターナリスティック(家父長主義的)な政策によるものにすぎないと片づけることは容易である。しかし、グローバル化が進み、環境破壊が世界的な課題となっている中で、労働条件そして労使関係も厳しさを増している状況で、人間らしい働き方、生活の環境、労使のあり方として、いかなる方向が選択されるべきか。これらの実験的な試みに学ぶところは少なくない。
クレスピ・ダッダの町並みは、資本主義の牧歌的時代の面影を色濃く残し、創業者たちの意図した経営者と労働者の一体感を継承してきた。 1995年、Unesco世界遺産の審査委員会は、19世紀および20世紀にわたり、人間らしさを維持していたこの夢の「労働者の村」 (Workers' Village)をそのリストに加えた。
画像:現存する繊維工場の一部(窓はクレスピ家の紋章)
Courtesy of villaggiocrespi
* 2005年2月12日「窓外の世界:少女はなにを見ていたのか」(仕事の情景)
クレスピ・ダッダについて、さらに詳細を知りたい方は、次のHPを訪れてください。
http://www.villaggiocrespi.it/xUK_A1_HOME.htm
このところ、インドネシア・スマトラ沖の大地震、津波の後には北九州の地震と、災害が続発している。「災害は忘れた頃にやってくる」とは、寺田寅彦の有名な言葉だが、この頃は忘れないうちにやってくるようだ。
寺田寅彦は、「津波と人間」という随筆で、次のような興味深い言葉も残している。 「しかし困ったことには「自然」は過去の習慣に忠実である。地震や津浪は新思想の流行などには委細かまわず、頑固に、保守的に執念深くやって来るのである。紀元前二十世紀にあったことが紀元二十世紀にも全く同じように行われるのである。科学の方則とは畢竟「自然の記憶の覚え書き」である。自然ほど伝統に忠実なものはないのである。それだからこそ、二十世紀の文明という空虚な名をたのんで、安政の昔の経験を馬鹿にした東京は大正十二年の地震で焼払われたのである。」(昭和八年五月『鉄塔』)
残念なことにわれわれ人間は災害から逃れることはできないようだ。どこかで必ずやってくる。あの地下鉄サリン事件の時も、私はひとつ前の地下鉄に乗っていて危うく運を逃れた。もっとも、これは天災ではなく、人災であったが。
たまたまTVを見ていると、カンボジアの首都のホテル街で火災が起き、20名を超える人々が犠牲になったと報じていた。ホテルの火災は意外に多い。20年ほど前、私もたまたま滞在したロンドンのストランド・ホテルで夜間に火災に遭遇し、煙の立ちこめる廊下を何も持たずに文字通り這うようにして、逃げ出た経験がある。一寸先も見えなくなるという状況を実体験した。幸い、この時は犠牲者が出なかったが、このホテルと契約している近くのサヴォイ・ホテルが避難場所になり、思いがけないことでロンドン最高級ホテルの一時的な客となった。ストランド・ホテルの方は何の変哲もない普通のホテルだが、この騒ぎのしばらく前に中曽根康弘元首相が議員時代に宿泊したということを後で知った。
歴史に残る悲劇
ホテルや工場の火災の記事を読むと、しばしば思い出すのが1911年3月25日にニューヨークのトライアングル・シャツ会社(Triangle Shirtwaist Company)で発生した悲劇的な火災事件である。現代アメリカ史には必ず登場する著名な事件である。 悲劇の発端の火災は、ビルの最上階にあるトライアングル社の終業時間近くに起きた。火の手は瞬く間に広がり、500人の従業員のうち146人が焼死するという悲惨な事故となった。煙に巻かれ、苦しさのあまりビルの9階から飛び降りた人もいた。
この事件については、かつてGHQ 時代に日本での教育向けに作成されたアメリカ労働運動の記録フィルムを見ていた時、その中でこの火災事件が大きく紹介されていたことも記憶に残っている。
現代に残る苦汗労働
2001年はこの火災が発生して90年目に当たるために、ニューヨーク市では、3月27日に追悼行事が行われ、そのひとつとして「トライアングル火災事件の今日;苦汗労働とグローバル経済」と題したフォーラムも開催された。
この悲劇が今もなお多くのアメリカ人の心に刻み込まれているのは、この火災をめぐってさまざまな出来事が展開したことによる。トライアングル社は当時のニューヨーク市イーストサイドでの典型的な苦汗労働工場 (sweatshop)であった。苦汗労働というのは、低賃金 できわめて長時間、不衛生な環境の中で労働者を働かせることである。非人間的な労働条件の下での過酷な労働といってもよい。この工場では、ビルの持ち主がビルの各階を個人に賃貸しをして、雇い主はそれぞれお針子と呼ばれる女子労働者をきわめて低い賃金で、シャ ツやブラウスの縫製のためほとんど拘束状態で働かせていた。劣悪な状況で管理もないに等しく、この事件が起きても、いったい何人がビルの中で働いていたか見当がつかなかったといわれる。
苦汗労働は今日でも消滅せず、世界中に見いだされる。アメリカ労働省の最近の調査でも、ニューヨーク市の衣服縫製工場の63%は、連邦最低賃金を下回る賃金しか支払っていず、労働時間も過長で違反していた。グローバル化の進展は、労賃の低さだけで生き残ろうとするこうした苦汗工場を開発途上国ばかりでなく、先進国にも存在させている。 火災発生以前の1909年には、劣悪な労働条件に耐えかねた若い女子労働者たちの職場放棄などが起き、女性労働組合連盟 (The Women's Trade Union League) などが、争議を支援するなどの前触れが起きていた。なにかがなされねばならないと良識ある人々が感じ始めて いた矢先の悲劇であった。
この火災で犠牲になったのは、ほとんどが当時アメリカに移民してきたばかりの若いイタリア人、ヨーロッパ系ユダヤ人労働者であった。犠牲者はほとんど女性であり、中には11歳の少女まで含まれていた。貧困のどん底生活を送り、想像を絶する環境の下で働いていた 。火災発生時、避難階段への道はほとんど閉ざされており、逃げる労働者の重みで階段自体が折れてしまった。消防車のはしごも短く届かなかった。
しかし、事件の責任追及は不十分に終わった。火災発生後8ヵ月して陪審員は工場の所有者を無罪放免した。陪審員団のしたことは火災発生時に外部に通ずるドアに鍵がかけられていたか否かを確認しただけだった。生存者は異口同音に外部のはしごに通じる唯一のドアは開くことができなかったと証言した。しかし、被告弁護士の巧みな弁舌によって、証言は陪審員を動かすにいたらなかった。「正義はどこにあるのだ」という非難が高まった。
工場安全衛生法の成立に
事件の悲惨な内容が次第に判明するにつれて、国際婦人服労働組合(International Ladies' Garment Workers' Union: ILGWU) を初めとして、市民たちの救援活動や労働条件改善要求の運動が盛り上がった。そして、この事件の責任を追及する社会的運動へと広がった。 ニューヨーク州知事は、工場査察委員会を設置し、5年間にわたる公聴会その他を経た後、アメリカ労働立法史上、きわめて重要な工場安全衛生法の制定が行われた。
後にニューディール政策を実行したフランクリン・ D. ルーズヴェルト大統領の下で、労働長官を務めたフランセス・パーキンス女史は、現場を視察し、その後の人生で労働者の地位改善の主唱者となることを決意したといわれる。そして、ニューヨーク市安全委員会事務局長の立場で工場査察を支援した。 この悲惨な事件は、上記の労働立法への道を開いたばかりでなく、過酷な労働条件で働く労働者への関心の喚起、そして救済のための立法への契機となったものとして、絶えず思い起こされ、多くのアメリカ市民の心に今に残るものである。後に労働長官となったパーキ ンス女史は、ニューディールはトライアングル事件の日から始まったと述べている(関連記事:本ブログ「芸術と政治の戦い:「クレイドル・ウィル・ロック」」)。
事件発生後、90年の年に当たる2001年3月、コーネル大学キール労使関係アーカイブセンター (Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives, Cornell University/ILR) は、この歴史的な事件に関わる詳細を記録・再現する素晴らしいHP(注)を開設した。
このHPには当時を知る関係者の記録がオーディオ・ヴィジュアルな手段を駆使して蓄積されており、きわめて印象的なHPとなっている。この分野に関心を持つ学生が資料を発掘し、研究に利用する場合の注意など、細かな配慮もされている。日本人は過去の出来事を大変忘れやすい民族ではないかと私は思っているが、災害についても確実に後世の人に伝える努力が必要であろう。
注:トライアングル・ファイア事件を記録するHP http://www .ilr.cornell.edu/trianglefire/
画像:トライアングル事件を記憶するため国際婦人衣服労働組合が Ernest Feeney に依頼、制作した壁画「縫製産業の歴史」 (1938), Courtesy of New Deal Network
写真の拡大はクリックしてください
ひとりの少女が窓の外をじっと眺めている。背景はどうも工場の一隅のようだ。しかし、何の機械だろうか。実は、ここに紹介する写真は20世紀の初めにアメリカの労働現場、「仕事の世界」を数多く撮影したルイス・ハイン Lewis Hineが、1909年にアメリカのノース・カロライナ州の工場(Rhodes Mfg. Co.)で働く少女を撮影したものである。
「外の世界を見る一瞬」(A Moment Glimpse of Outer World)と題するこの小さな写真は、アメリカ繊維産業の調査をしている中で見つけたものだが、それこそ一瞬にして私を惹きつけてしまった。被写体となった少女は当時11歳で、それまで1年間、工場で働いていた。少女が立っている場所は、明らかに綿紡績工場の中である。背後にある機械から、彼女が当時の繊維工場で「女子の職場」とされていたスピナー (spinner)と呼ばれた仕事についていたことが分かる。
働く多数の子供たち
綿紡績工場では多数の子供たちが長時間の労働に従事していた。大体,週6日、1日11-12時間、立ちっぱなしの過酷な労働であった。作業環境は大変悪く、綿くずが換気の悪い工場内に飛び散り、充満していた。温度と湿度を高く保つほど、糸が切れにくいため、工場の窓は通常閉め切られていた。その中で彼女たちは機械の横の通路を行き来し、回転する糸巻き機の糸が切れていないかを注意し、切れている場合にはできるだけ早く糸の先を見つけ出し、つながなければならなかった。
劣悪な労働条件
稼働率を維持するために、繊維工場の機械は連続運転されていた。作業の間は、機械から離れることができません。製品の品質は、彼女たちの若い眼と細い指に大きく依存していた。背後にはいつも管理者の目があった。湿気が多く、蒸し暑い、騒音に満ちた劣悪な労働条件の下で、子供たちが工場災害や病気になる頻度は大変高かった。綿紡績工場で働く子供たちが、生きて12歳を迎える数は、ふつうの子供の半分以下であったといわれている。
子供たちの親の賃金も大変低く、それだけではとても生活できないために、親と一緒に工場に出ていた。時々査察にやってくる工場監督官に見つかると、「たまたま今日は、親につれられて来ていただけです」などと答えて、見過ごしてもらっていた。
少女の視線の先
この写真の少女は、文字通り機械に追い回されるような時間の中で、ほんの一瞬と思われるが、窓外に視線を向けている。多分、機械が故障するかして、思いがけない静止の時間が生まれたのだろう。ルイス・ハインの写真を含めて、当時の工場の状況を記録した写真は、過酷な労働を反映して、被写体の労働者の表情にも暗い陰が落ちているものが多いのだが、この写真は例外といえる。質素だが、こざっぱりとした作業衣を身につけ、聡明さを感じさせるしっかりとしたまなざしで窓の外のなにかを見つめている。いったい彼女の眼に映った光景はなんだったのだろうか。
こうした少女たちが工場生活を送った時代のすぐ後、世界は激変した。大恐慌を間に挟む二度の世界大戦を経て、今日の時代につながっている。彼女が見ていたものは、なんであったのだろうか。想像はとめどなく広がって行く。
Photo:
Courtesy of National Archives Photo NWDNS, 102-LH-249. Rhodes Mfg. Co. Spinner, A moment’s glimpse of the outer world, N.C., November 11, 1908.