音の風景・『艪が咽ぶ』
「矢切の渡し」  細川たかし歌
細川たかし歌
作詞・石本美由紀
作曲・船村 徹 (総出演)
矢切の渡しは、昭和51年”ちあきなおみ”「酒場川」のB面として発表され、昭和58年
”細川たかし”によって新たに吹き込まれ大ヒットした。
親の心をそむき、柴又から対岸の松戸へ駆け落ちする男女のストーリがしっかり歌われている。
作曲を手掛けた船村徹は、NHKでのドキメンタリー番組「新日本紀行」で
取り上げられたことをきっかけにこの歌を発案したそうです。
この歌には消えつつあった、江戸川の男女の逃避行が重ね合わされている。
歌詞に「揺れながら 艪が咽ぶ 矢切の渡し/息殺して 身を寄せながら 明日へ漕ぎ出す
別れです」という歌詞が有ります。
「咽ぶ」という言葉の意味として「涙で息が詰まるほど泣く」この『艪が咽ぶ』と
言う語彙に筆者はピンと心を打たれた!!
▲ 艪が咽ぶ 矢切の渡し 春探し (縄)
男女の駆け落ちを思いながらも、吾(筆者)は江戸川河川敷の岸辺を
青空の下、春を探しながら彷徨っていた。
江戸川の川面が光り、岸を離れた渡し舟の艪のきしむ音が
微かに風に乗って聞こえて来た。

矢切の渡し表示板
矢切の渡しは、江戸時代の初期に、柴又と対岸の松戸の間を運航していた。
武州金町松戸関所の文書に残されている。
伊藤佐千夫が明治39年発表した小説「野菊の墓」ワンシーンに登場したことで
広く知られるようになった。
運航は杉浦家によって担われ、現在は2代目杉浦幸雄氏が行っています。
明治時代は日用品購入や社寺への参拝、野菜の運搬などで近所の人々の
足として使われていた。
おじいさんの頃は夜中の1時頃、千住の野菜市場に野菜を背負って行く
お百姓さんで一杯だったと言う。
当時は民家が川畔にあり、お酒も飲ましてくれたと言う。
尾崎士郎「人生劇場・青春篇」の舞台となった料亭「川甚」も在って、
川面に灯影が揺れていたと・・・・・。
その「川甚」も、此のコロナ禍で店を閉めてしまい寂しい限りです。


「矢切の渡し」歌碑

渡し江戸川の半ば

岸の柳と待つ人達

艪漕ぎの船頭さんと船外機
渡し舟は川中にくると、エンジンを動かし船外機により松戸川の対岸に着く。
現在都内で稼働している渡し船は、矢切の渡し舟の身になってしまい、
貴重な渡舟場として稼働しています。
「矢切の渡し」が一世を風靡してから時が流れましたが、『艪が咽ぶ』音がそうした
江戸川を織りなすシーンを彩ってきたのであ
「東京人。朝日ジャーナル、可豆思賀を参照しました。
画像は蔵出し画像としました」
コメント欄はOPENです。























 細川たかし歌
細川たかし歌





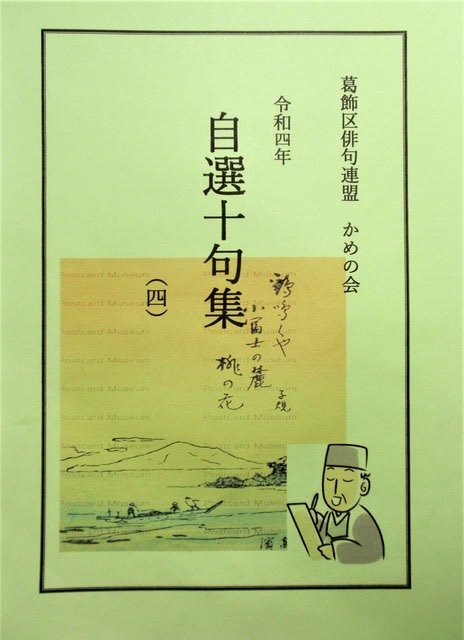

























 .
.










