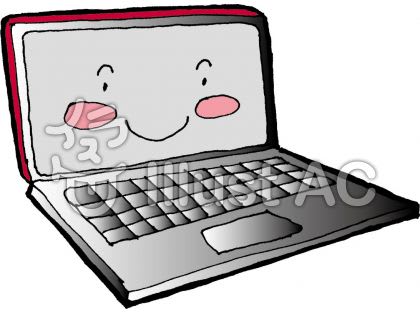多くの水路が至る所に・・・・。
見沼代用水とは
江戸時代の初期、利根川と荒川は、
越谷付近で合流し、いつも氾濫を繰り返し住民悩みの種でした。
当時としては大工事、
氾濫をなくすために両川を引き離し、その後を大水田地帯にした土木工事です。
埼玉県東部から南部の水田地帯を流れる関東平野最大の農業用水。
幹線水路延長84キロメートル、灌漑(かんがい)面積1万7000ヘクタール。
江戸中期、井沢弥惣兵衛(やそべえ)によって掘削された。
名称は、新田開発のために干拓された見沼溜井(ためい)に代わる用水の意である

↑
芝川沼地の広大な面積を取り囲む、周囲6,5kmの散策路でした。
この沼地を改良とする人々のドラマがありました。
東浦和駅から時計と反対廻りにウォークしました。

↑
入り口の標識表示
埼玉浦和・見沼通船堀を歩く クリック下さい。
クリック下さい。
DB掲載方式が額縁式➡貼り付け式に変わりました。
このウォークについて、他に2件を編集中です。