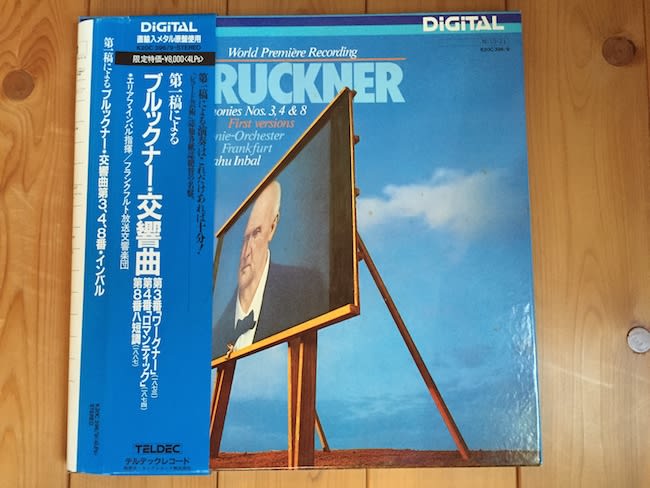イスラム国に囚われた後藤さん、
最悪の結果を迎えたようで残念でたまりません
ただ、何を言っても無駄な様に思える彼の国との交渉も
もう少しやりかたはあったのではと思わざるをえない
もっともヨルダンにお任せするしか手は無いので
仕方なかったとも言えるけれど
この手の交渉でいつも思うことは、北朝鮮の場合もそうだけれど
こちらの打つ手や彼の国の行動の解釈は
全て報道で明らかにされている
「イスラム国はこう考えている、、、」などと
これは、イスラム国にとって相手が自分たちをどう考えているかを
よく知る手がかりになる
一方我々はイスラム国(北朝鮮)の事は全然知らない
情報の不均衡極まりだ
だからこそ、秘密保護法みたいなものがつくられて
秘密にすべき問題は秘密裏に
ということになるのだろうが
どうもそうとはならず情報は垂れ流し
ところで、秘密保護法は何を秘密と考えるのだろう
拡大解釈で手におえないようなことにならなければいいのだが
今朝の安部首相のインタビューで気になったのは
{許すことはできません」ではなくて
「許しません」と言ったこと
後者のほうが感情がこもって、前者の他人ごとのような言葉よりも
感情に訴えるかもしれないが
心配なのはより危険な方向に彼は舵を取らないかということ
安部首相は有志連合ではなく、人道支援的な金銭の提供といったが
実はトーンとしては外務省の希望もあったかもしれないが
有志連合の一員的な存在に勘違いしてもらえれば
と思ったのではないか
イスラム国が有志連合云々言ってきたから
人道的な見地からのとニュアンスを変えたが
本当は皆にどう思われていたかったかが怪しい
あちらの国の人皆に正確に物事を理解してもらえる
のは難しい
ただでさえ人は早とちり、錯覚、思い込みをしやすい
だから正しい言葉遣いをして、正しいことをいっても
それがその通りに通じているかは別問題
本当はそこのところの正しい冷静な分析が必要
安倍さんのイスラエル国旗の前での人道支援的な
資金の補助の発表は確かに好ましくないというか
錯覚を起こしかねない
それにしても、今回の結果が引き金になって
安倍さんの暴走にブレーキがかからなくなってしまいそうな
不安を感じるのは考え過ぎか、、、