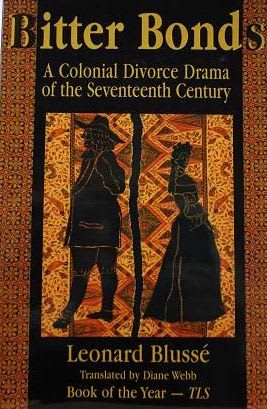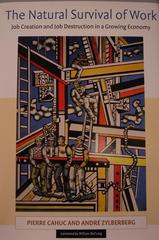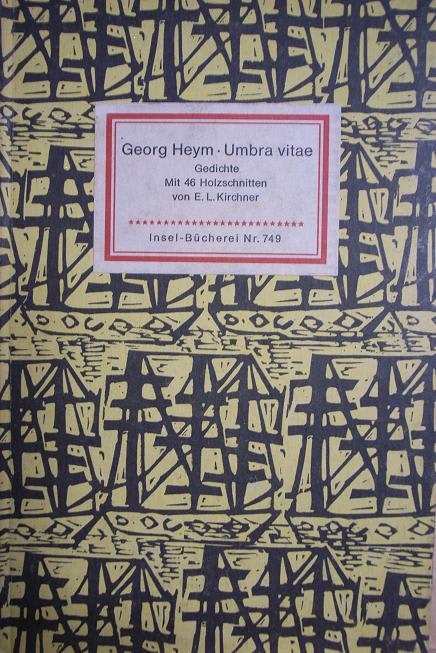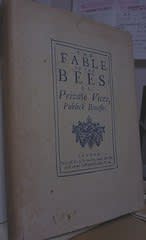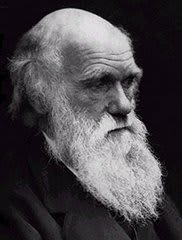不合理で、煩わしいことも多い世の中を過ごしてくると、いつの間にか身についてしまった心の凝りのようなものを、解きほぐしたいような気になる。そうした折にしばし手にしてきた一冊がある。オスカー・ワイルド『幸福な王子』*という小編だ。最初に出会ったのは10代半ばだったが、その文体に魅せられて何度も読み、かなり覚えてしまったほどだった。実はこうした肩こり解消?トランキライザーのような役割をしてくれるものは、他にもいくつかあるのだが、今日はこれにしよう。
最初手にしたのは、英語と日本語の対訳版だった。出版事情も今のように良くなかったこともあって、紙質も装丁も貧しく、ページが散逸してしまった。ふとしたことで最近新版*が刊行されたことを知って、早速手に入れた。Penguin Books のPuffin Classicsというシリーズに入っている。この短編、ともすれば子供向けの童話として考えられ、実際児童書のコーナーに置かれていることも多い。ちなみにある大書店でオスカー・ワイルドのコーナーを見たが、『ドリアン・グレイの肖像』『ウインダミア夫人の扇』『獄中記』など他の作品はかなり揃っていたが、「王子さま」はみつからなかった。
実は『幸福な王子』(および他の関連童話作品)は、大人が読むべき作品と思っている。オスカー・ワイルドは18世紀後半のヨーロッパで時代を代表するセレブリティであり、毀誉褒貶ただならぬ文人だった。生前は悪名の方が高かったかもしれない。しかし、ワイルドが書いたこの小品は、どれをとっても見事なきらめきと深みを持っている。この短編集には『幸福な王子』を含めて9編が収められているが、いずれも珠玉のような作品だ。そこには、愛、裏切り、利己心、純粋さ、犠牲、悪、美しさ、どう猛、残忍、真理、などこの世を組み立てる道具立てはすべて揃っている。ひとつひとつの話の底になにがあるかを考えながら読むのは楽しい。ごひいきの作品『幸福な王子』にも多くのことが含まれている。久しぶりに読み直す。少し最初の部分をご紹介しよう(管理人仮訳)。
幸福な王子
市を見下ろす丘に建つ高い円柱に、幸福な王子の像が立っていた。王子は全身を純金の箔で覆われ、両目には明るいサファイアがはめ込まれていた。身につけた刀の柄には大きな赤いルビーが輝いていた。
王子は誰からも賞賛されていた。「王子さまは風見鶏のように美しい」。美術眼があるとみられたい市会議員のひとりが言った。「あまり役に立たないけれども」と、彼は付け加えた。人が彼は実務的でないと思うのを恐れていた。実際、彼は役に立たなかったのだが。
「どうしておまえは王子さまのようになれないの」と、お月さまが欲しいようと泣く小さな子供に、しっかりした母親は諭し、「王子さまはなにかを欲しがって泣いたりしないのよ」と言った。
「世の中に本当に幸せなひとがいるとは素晴らしい」とすっかり絶望した男は、見事な像を眺めながらつぶやいた。
「王子さまは天使のようだね」。深紅の上着に清潔な白い上っ張りをつけ、寺院から出てきた慈善孤児院の子供たちは口々に言った。
(中略)
そしてある朝、市長と助役はくだんの丘の下を歩いていた。円柱の下を通った時、王子の像を見上げた。そして「おやまあ、なんと王子さまはみすぼらしくみえるのだろう」と市長は言った。「たしかにみすぼらしい!」といつも市長に同調する助役も声を上げ、王子の像を見に丘を登っていった。
「ルビーは刀の柄から無くなっているし、王子さまの目もとれてしまっている。それにもう黄金の王子ではないぞ」と市長は言った。「これでは乞食と変わらない!」
「乞食と変わりません!」助役も唱和した。
「足もとには死んだ鳥が落ちている」、市長は続けて「ここで鳥は死んではいけないと布告を出さないといけないな。」そして、市の書記はその言葉を書きとめた。
そして彼らは幸福な王子の像を円柱から下ろした。「王子はもう美しくないから、役に立たない」と大学の美術の教授は言った。
彼らは王子の像を炉で溶かした。そして、溶かした金属でなにを作るかを決めるため議会を開いた。「別の銅像を作らねば」と市長は言い「それは当然私の像だ」と続けた。
「いや私のだ!」と議員たちは口々に言いつのった。後で議会室をのぞいたら彼らはまだ言い争っていた。
(話はもう少し続くのだが、読者のお楽しみに)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
この話、人間の心を持っていた銅像の王子と一羽のつばめの物語なのだが、読むたびに印象が少しずつ異なってくる不思議な作品である。子供の時に最初に読んだ時は、ストーリーの美しさには魅せられたが、作品が持つ深い意味、とりわけ細部の含意にほとんど気づかなかった。王子の眼下に広がる心貧しく、荒んだ光景、王子に殉じた一羽のつばめの過ごした時・・・・・・。王子とつばめの幸せとは。考えてみると、オスカー・ワイルドは、多数の鋭い金言を残していることでも知られる文人だった。いくつか思い浮かぶ。
仕事とは、ほかになすべきことのない人の逃げ場である。
[削除 2010/04/11: 修正2010/04/15]
人間は不可能なことを信じることができるが、ありそうももないことを決して信じることはできない。
経験とは誰もが自分がおかした失敗につける名前だ。
*
Oscar Wild. The Happy Prince and Other Stories. London: Puffin Edition, 2009. 原作は1888年。(邦文は仮訳)