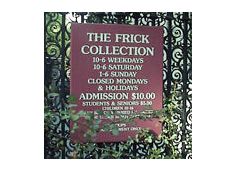Book Cover Photo: Mrs. Frances Perkins
Kirstin Downey. The Woman Behind the New Deal: The Life of Frances Perkins, FDR’s Secretary of Labour and His Moral Conscience. Non A. Talese; 458pp. 2009.
今回のグローバル大不況と比較されることが多い1930年代の世界恐慌前後の時代には、かねてから大きな関心を抱いてきた。学生の頃、たまたま周囲に大恐慌を経験した人々がいて回想談を聞いたことが、興味を呼び起こすきっかけになったのかもしれない。しかし、そうした人々も次々と世を去り、今日メディアなどで大恐慌に言及する人々も、文献記録、伝聞などでしか、当時の状況を語るにすぎなくなってきた。他方、最近1930-40年代について、新たな資料による見直しも進んで、かなり興味深い新事実も明らかにされている。
忘れられていた人
今夏、一冊の本を手にした。1930年代、アメリカで大不況に対応を迫られた大統領フランクリン・デラノア・ローズヴェルト(略称FDR)の政権下で、女性初の労働長官 Secretary of Labor として働いたフランセス・パーキンス女史Frances Perkins (born Fannie Coralie Perkins, April 10, 1880 – May 14, 1965) の人物伝であるパーキンス自らの手になる回顧録パーキンスからみたFDRについては、このブログでも記したことがある。
新著は自叙伝ではなく、パーキンス女史に近かった人々の証言や記録などからクローズアップされた歴史的人物伝といったほうがよいだろう。著者カースチン・ダウニーは女性のフリーライターであり、2008年のジョージア工科大学銃乱射事件の報道でピュリツアー賞を共同受賞している。本書はこれまで埋もれていた資料やインタビューなどを積極的に行い、十分知られることがなかったパーキンス像を見せている。新たな資料発見があり、同時代史としても興味深い点が多い。アメリカ人でFDRの時代を知る人は、大体彼女ののことも知っていたが、日本ではFDRはともかく、パーキンスのことを知る人は、研究者を含め厚生労働の分野でもきわめて少ない。
今日のグローバル不況の下でも、各国政府にとって最大の課題は雇用そして社会保障問題である。景気は底を打ったという一部の観測にもかかわらず、主要国での失業率は上昇を続けており、改善の兆しはまだ見えない。他方、比較の対象になる1930年代大恐慌当時、いかなる背景の下に、どんな政策が実行されたかという点については、必ずしも正確に知られていない。FDRの時代に、いかなる歴史的文脈の中から個々の政策が構想され、実現したかを知ることは、現代的視点からもきわめて重要なことだ。 本書はパーキンスという一人の女性の人物伝としては決定版とはいえないが、当時のアメリカ政界や女史の周囲にいた人々、社会環境がつぶさにうかがわれて大変興味深い。
ニューディールを支えて
1930年代の大恐慌時、震源地となったアメリカでは雇用、労働にかかわる諸制度は、ほとんど未整備といった状況だった。資本主義最大の危機といわれた不況の拡大に伴い、失業、労災などの労働問題は最重要な社会経済問題として急速に浮上した。しかし、その問題に対処した人物は、当時はまったく重きを置かれなかった。パーキンス女史はまさにその人であり、閣僚の順位では自ら認めていた通り最下位だった。
アメリカ史上最初の女性の閣僚として、パーキンスは公共事業 Public Works Association (後にFederal Works Agency)による雇用創出、全国産業復興法(NIRA)、失業保険、社会保障(公的年金)などの導入に努めた。さらに、労働法の大幅な改革、最低賃金制の導入、週40時間立法、児童労働の禁止などを実施した。FDRの政権はニューディールの時代として知られるが、組織勢力としては弱い立場にあった労働組合について、団体交渉権、組合組織化の権利の拡充も行われた。FDRの政権は12年間続いたが、彼女はほぼ一貫して労働長官として、大統領を助けて働いた。今日、ワシントンD.C.の労働省の建物の入り口には Frances Perkins Department of Labor と記されている。
リベラリストの働き
パーキンスの名前を知ったのは、アメリカで学び始めた頃に、トライアングル・ファイア事件に関する文献を読んでいる時に出会ったのが最初だったと思うが、ほぼ同時にファカルティの何人かから、ニューディール時代の体験談を数多く聞いた。ニューディール政策の実施のためには、実に多数の人たちが働いた。その中心として指導的立場にあった人の多くは、アメリカ社会でもかなり鮮明にリベラルな立場をとっていた。戦後、占領下の日本で、労働政策その他の立案過程に関与した人たちの中に、ニューディーラーが多かったことはよく知られている。
パーキンスは名門女子大マウント・ホリヨークを卒業後、婦人参政権が獲得される前から、ニューヨークで社会改革家として活動していた。彼女に決定的な転機をもたらしたのは、1911年ニューヨークのグリニッチヴィレッジで発生したトライアングル・シャツ工場の悲惨な火災事件だった。146人の若い移民の女子労働者などが火炎と煙に巻き込まれ命を落とした。この時、パーキンスは現場の近くの友人の家にいた。そして劣悪な労働条件で働かされていた多くの女子労働者が逃げ場を失い、12階建てのビルの上から飛び下りる惨劇を目のあたりにした。
若い社会活動家としてニューヨーク市で働いていたパーキンスは、こうした悲惨な事件を繰り返してはならないと心に誓い、当時の民主党と保守党に働きかけた。当時の民主党は政治的に大変腐敗していたことで知られていたが、パーキンスは臆せず、活動した。彼女がFDRに見出されたのは、FDRがニューヨーク州知事の時だった。
最下位の閣僚
FDRが大統領に当選後、労働長官として登用され、FDRの任期のほぼすべて12年間(1933―1945)にわたり同ポストを務めた。ちなみに、FDRの任期を通して閣僚を務めたのは、彼女と内務長官ハロルド・アィクス Harold Ickesの二人だけである。
今日と違って、女性差別が厳しかった時代で、彼女はさまざまな脅しや嫌がらせを受けた。パーキンスはしばしば嘲笑の的となったファニーFannie という名前をフランセスFrances に改名までした。30歳代には、男たちの母親のような野暮ったい格好をしているなら、男の政治家も競争相手とはみなさないだろうと考え、流行遅れの衣装を身につけることまでしたようだ。閣僚に任命された後も、男の政治家の妻たちとなるべく同じ席につくように心がけた。FDRの妻エレノアの発案で、閣僚の妻たちの昼食会が定期的に開催されていた。パーキンスは積極的に参加し、側面から自分の考えの浸透を図った。こうした努力にもかかわらずパーキンスに対する差別はひどく、とりわけ労働組合の指導者たちが問題だった。彼らは女性が労働政策を立案、実施するという考え自体をひどく嫌悪していた。
当時のパーキンス女史の活動範囲は大変広く、現在のボーダー・パトロール(国境警備)もその指揮下だった。劣悪な労働条件にあった炭鉱や戦時下の防衛産業なども精力的に視察していた。
他方、彼女の家庭生活も複雑で問題山積だった。夫のポール・ウイルソンは鬱病状態が長く、その人生のほとんどを経費がかかるサナトリウムで過ごした。彼女はその費用を負担していた。一人娘のスザンナは結婚に失敗した後、同様に鬱状態になり、母親の支援が必要だった。パーキンスにとって、晩年までスザンナのことは大きな心ががりのことだった。もっとも二人の関係はその後、パーキンスの晩年には次第に疎遠となっていった。
パーキンスは、こうして女性が主たる家庭の稼ぎ手ではない時代に、自らその役割を負っていた。経済的な不安が常に彼女を駆り立てていたようだ。1945年労働長官退任後も、1965年に死ぬまで働いていたのはそのためだったのではないかと思われる。
不思議な縁
長官を退任した後、コーネル大学の講師として教壇に立ち、さらに男子だけのフラタニティ・ハウス Telluride House に住み込んだ。そこにいた学生の中には、保守的なインテリ、アラン・ブルームAllan Bloomやジョージ・ブッシュ政権の防衛次官補を勤め、その後世界銀行総裁となったパウロ・ウオルフォヴィッツPaulo Wolfowitz もいた。
本書を読んでいて驚いたのは、パーキンス女史に教職の道を開いたのは、たまたま私の指導教授のひとりだったMN. だったことだ。これらの関係者は、今はすべて故人となったが、MN教授(2004年没)夫妻(モーリスとヒンダ)は、パーキンス女史のニューディーラーとしての経験に感銘し、若い世代にその経験を伝えるために教職の道を提案したのだった。パーキンスは喜んでその申し出を受けた。
180cmを越える長身で髪の毛がなく、眼光鋭いMN教授はきわめて厳格な指導で知られ、文献の選択、論文の構成から句読点まで細部にわたり徹底して鍛えられた。自分でも meticulous (過度なくらい細心)と思うと冗談をいうくらい、専門領域の議論には厳しかった。英語が母国語でない私などは大分泣かされたが、得難い経験だった。容貌魁偉といってもよい一見人をたじろがせるようなこの人が、実はきわめて穏和で気配りに満ちた人であることを感じたのはまもなくのことだった。
私的な面では大変親切で、どこで見ていたのか、苦労している留学生などに細かな心配りも怠らず、しばしば自宅に招いてくれた。その後もキャンパスを訪れると、親切に配慮をしてくれ、空港まで送迎してくれたりもした。後年、自分も同じ立場になったら、その何分の一かでも努力しなければと思った。
当時は大学にもIBMの大型コンピューターしかなく、調査や計測データはすべてパンチカードで入力、PCもなく電動タイプライターが使われ始めた頃だった。MNはアメリカの労働史、国際比較に関する膨大な文献ファイルを作成するとともに、几帳面に日記を残しており、それが今回パーキンス女史の晩年の教職時代を伝える重要な資料になっていた。また、女史が亡くなった時、大学私室に残された多くの書簡などの資料が処分されることを密かに救い、議会図書館に委託し、MN教授が生存中(2004年死去)は公開しないようにしてあった。
思い起こすと、さまざまな折に大恐慌時代のエピソードを聞いていた。パーキンスを大学へ招いた本人であることは本人の口からは一言も話されなかったが、同僚は皆知っていたのだろう。ファカルティの多くは心情的にもニュー・ディーラーだったから。ファカルティ・ラウンジには、晩年の女史の肖像画が掲げられていた。女史は教室でもしばしば正装、帽子を被って教壇に立っていたようだ。
ジョン・F・ケネディが民主党大統領に立候補した当時、妻であったジャクリーンが、支持者の女性たちを集めて、パーキンス女史をゲスト・スピーカーとして招いた1960年当時の写真などを見ると、よき時代のアメリカの断片が思い浮かぶ。FDRの妻エレノアとも親しかったようだ。
話には聞いた大恐慌下の出来事を、当時よりも今の方がはるかに切迫感をもって考えられるのは不思議なことだ。歴史を真に理解するには、ワインのようにある熟成の期間が必要なのかとも感じる。現代史の面白さは、思いがけないことで急速に深まることもある。世界がますます小さくなる今日、相手の国のこともより深く知る必要がある。細部に入り込むことで格段に理解も増す。FDRそしてパーキンスとその時代については、興味深いことが多々あるが、もはやブログの域を超えてしまった。