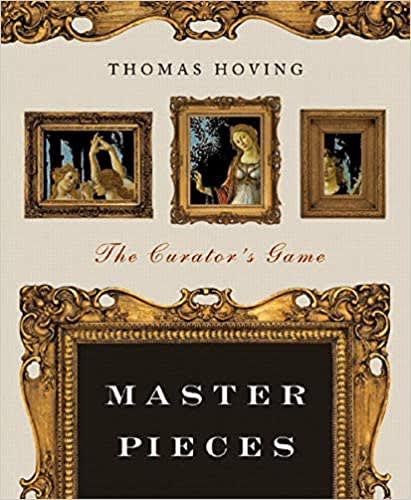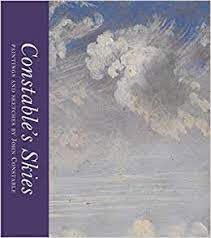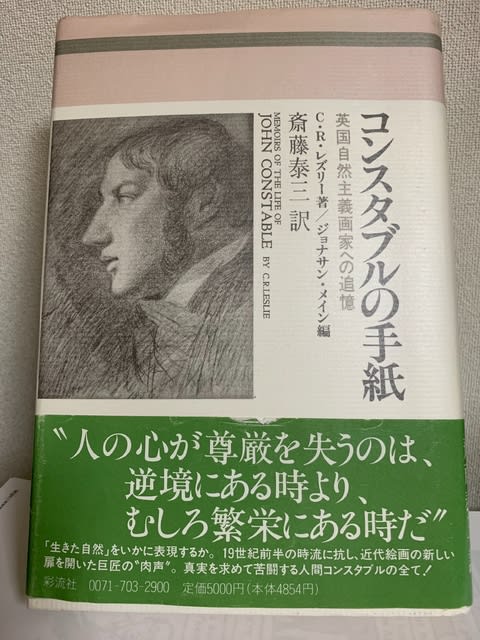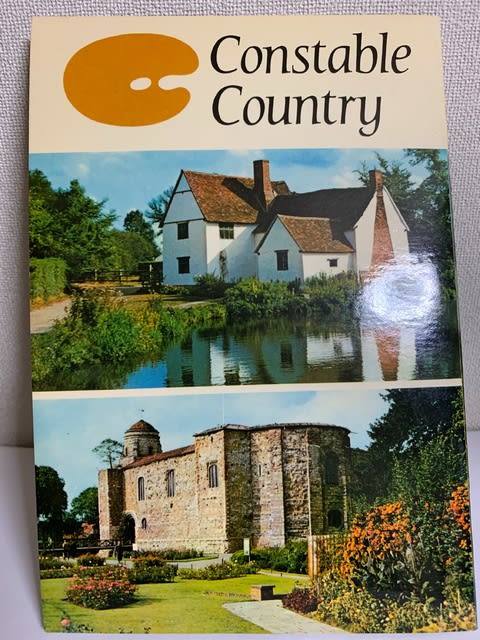ペーテル・パウル・ルーベンス《聖家族と聖フランチェスコ、聖アンナ、幼い洗礼者聖ヨハネ》1630年代初頭/中頃、油彩・カンヴァス、176.5x209.6cm, メトロポリタン美術館、ニューヨーク 出展番号18
現在『メトロポリタン美術館展』に展示されているルーベンス(オランダ語:リュベンス)の作品である。制作年代は1630年代初期から40年代中頃と推定されているこの作品は、聖家族、聖アンナが幼い洗礼者聖ヨハネを伴う聖母子、そして聖フランチェスコの幻視など、いくつかの伝統的主題をひとつの画面に描いているため、物語性は排除されている。しかし、画面からは穏やかな印象が伝わってくる。ルーベンスは、制作後も継ぎ足しや加筆をかなり行ったようだ。ルーベンスの作品の中では、決して中心的な位置を占めるものではないが、好感が持てる作品である。
メトロポリタン美術館 The METは、かつては足繁く通った時もあったが、この作品に出会った記憶はなかった。そういえば、1200点を越えるとも言われるルーベンスの作品だが、METが所蔵する作品は少ないようだ。ニューヨークとオランダとのつながりから見ても不思議な感じがする。日本の国立西洋美術館でも10点余を所蔵しているはずなのだが。
対比モデルとして:ラ・トゥールとルーベンス
ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593-1652)の探索を行う過程で、陰に陽にブログ筆者の脳裏に去来していたのは、ぺーテル・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens: 1577-1640)であった。
現在『メトロポリタン美術館展』に展示されているルーベンス(オランダ語:リュベンス)の作品である。制作年代は1630年代初期から40年代中頃と推定されているこの作品は、聖家族、聖アンナが幼い洗礼者聖ヨハネを伴う聖母子、そして聖フランチェスコの幻視など、いくつかの伝統的主題をひとつの画面に描いているため、物語性は排除されている。しかし、画面からは穏やかな印象が伝わってくる。ルーベンスは、制作後も継ぎ足しや加筆をかなり行ったようだ。ルーベンスの作品の中では、決して中心的な位置を占めるものではないが、好感が持てる作品である。
メトロポリタン美術館 The METは、かつては足繁く通った時もあったが、この作品に出会った記憶はなかった。そういえば、1200点を越えるとも言われるルーベンスの作品だが、METが所蔵する作品は少ないようだ。ニューヨークとオランダとのつながりから見ても不思議な感じがする。日本の国立西洋美術館でも10点余を所蔵しているはずなのだが。
対比モデルとして:ラ・トゥールとルーベンス
ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593-1652)の探索を行う過程で、陰に陽にブログ筆者の脳裏に去来していたのは、ぺーテル・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens: 1577-1640)であった。
ほぼ同時代の画家でありながら、画家としての出自、私的生活、制作活動などあらゆる点で、ロレーヌの画家ラ・トゥールとは、両極に近い対照を見せている。ルーベンスの作品数の多さからみても、ほぼ同時代人のラ・トゥールはこの画家の作品にはかなり馴染みがあるはずだった。しかし、その影響は余り感じられない。両者の作品制作に当たっての思想は極めて異なっている。
たまたま、ブログ筆者の友人が若い頃に住んでいた家がルーベンスの生地であったジーゲンであったことが、ルーベンスに関心を持つようになった端緒のひとつであった。自宅に泊めてもらい、ドイツ人の家庭の有り様も体験した。1960年代のことである。
ルーベンスの画家としての生涯、画風は簡単には尽くせないが、バロック期のフランドルの偉大な画家であり、外交官でもあった。作品のジャンルは、歴史画、神話画、祭壇画、肖像画、風景画など、極めて多岐にわたった。現存する作品から判断する限り、宗教画、世俗画など限られたジャンルの作品しか残っていないラ・トゥールとは対極に位置するかのようだ。さらには、ラ・トゥールが果たし得なかった版画、出版の分野にまで広範に手をのばしている。17世紀ヨーロッパ、バロック時代に屹立する有名画家のひとりである。「バロックの天才」と言っても過言ではない。他方、ほぼ同時代人のラ・トゥールは、しばしばバロックの流れに安易に位置付けられるが、その作風は明らかにゴシックの流れにあったと考えられる。
恵まれた画業生活
洗礼記録以外、誕生から画家としての修業過程もほとんど不明なままのラ・トゥールと比較すると、ルーベンスはアントウエルペンでの人文主義教育、聖ルカ・ギルドへの入会を始めとして、充実した画業修業を過した。1598年に修業を終え、21歳で親方画家として芸術家ギルドの一員の資格を認められている。画業習得の過程すら全く不明なラ・トゥールと違って、ルーベンスはあらゆる点で恵まれた環境にあった。ルーベンスの生涯についての記録は、この時代の画家としては例外とも言えるほど豊富に存在し、今日まで継承されている。
たまたま、ブログ筆者の友人が若い頃に住んでいた家がルーベンスの生地であったジーゲンであったことが、ルーベンスに関心を持つようになった端緒のひとつであった。自宅に泊めてもらい、ドイツ人の家庭の有り様も体験した。1960年代のことである。
ルーベンスの画家としての生涯、画風は簡単には尽くせないが、バロック期のフランドルの偉大な画家であり、外交官でもあった。作品のジャンルは、歴史画、神話画、祭壇画、肖像画、風景画など、極めて多岐にわたった。現存する作品から判断する限り、宗教画、世俗画など限られたジャンルの作品しか残っていないラ・トゥールとは対極に位置するかのようだ。さらには、ラ・トゥールが果たし得なかった版画、出版の分野にまで広範に手をのばしている。17世紀ヨーロッパ、バロック時代に屹立する有名画家のひとりである。「バロックの天才」と言っても過言ではない。他方、ほぼ同時代人のラ・トゥールは、しばしばバロックの流れに安易に位置付けられるが、その作風は明らかにゴシックの流れにあったと考えられる。
恵まれた画業生活
洗礼記録以外、誕生から画家としての修業過程もほとんど不明なままのラ・トゥールと比較すると、ルーベンスはアントウエルペンでの人文主義教育、聖ルカ・ギルドへの入会を始めとして、充実した画業修業を過した。1598年に修業を終え、21歳で親方画家として芸術家ギルドの一員の資格を認められている。画業習得の過程すら全く不明なラ・トゥールと違って、ルーベンスはあらゆる点で恵まれた環境にあった。ルーベンスの生涯についての記録は、この時代の画家としては例外とも言えるほど豊富に存在し、今日まで継承されている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
N.B.
N.B.
 。
。《スペイン戦争, The Spanish Fury》ダニエル・ファン・ハイル(Daniel van Heil, 1604-62)
アントウエルペン(アントワープ)の市街が戦火に包まれる光景は、現下のロシアによるウクライナ侵攻の有り様と図らずも重なって見える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
N.B.
80年戦争(Tachtigjarige Oorlog)は、 1568年から 1648年にかけて( 1609年から 1621年までの12年間の休戦を挟む) ネーデルラント諸州が スペインに対して起こした反乱である。これをきっかけに後の オランダが誕生したため、オランダ独立戦争と呼ばれることもある 。この反乱の結果として、 ネーデルラント17州 の北部7州は ネーデルラント連邦共和国として独立することになった。北部7州は、1581年にスペイン国王 フェリペ2世の統治権を否認し、 1648年の ヴェストファーレン条約によって独立を承認された。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
アントウエルペンへの侵攻と占拠は80年戦争の間に起こり、その後この都市の衰退をもたらしたとされる。しかし、ルーベンスが過した当時、アントウエルペンは、戦火の中にあったが、16世紀末から17世紀初めにかけては、ヨーロッパでも有数の芸術的環境を維持していた。
イタリアへの旅と滞在(1600年ー1608年)
ルーベンスは、当時のヨーロッパの若い芸術家たちの憧れの地であったイタリアへの旅をヴェネツィアに始まるきわめて恵まれた形で行った。金銭的には手持ち資金も少なく豊かではなかったが、多くの著名人への紹介状を手に旅を続けることができた。後には憧れのローマも訪れ、イタリア・ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどの作品から多大な影響を受けた。カラヴァッジョの作品にも接している。後に、カラヴァッジョの作品購入の手助けなども行っている。ティツィアーノのから受けた影響も大きい。この時期には、マントヴァ公の金銭的援助も受けることができた。ルーベンスに求められた役割は、公の家族、親戚などの宮廷の美女たちを描くことにあった。画家が得た報酬は故郷に残った母親に送られていた。
ルーベンスの夥しい数の作品を見て気づいたことは、肖像画のジャンルにおける卓越した能力であった。作品の数も多い。多数の著名人の肖像を描くことを通して、天賦の才能は格段に磨き上げられたことだろう。そして、経済的にも豊かになった。
ラ・トゥールの場合を見ると、人物を描くという能力はルーベンスを凌ぐものさえ感じられる。しかし、この画家には肖像画の作品が残っていない。戦火や悪疫が襲うロレーヌの地では、顧客の数も少なかったことは想像に難くない。ラ・トゥールの力量からすれば、肖像画の依頼は多数あったかもしれないのだが、滅失、逸失などで今に残る作品がないのかもしれない。環境の違いが画家の生活を大きく左右するものであったことがよく分かる。
さらにルーベンスはマントヴァ公からスペイン王フェリペ3世(1578-1621)への特使としてスペイン王を訪れ、外交官としてのスタートを果たしてもいる。フェリペ2世の収集したラファエロとティツィアーノの膨大な作品にも接していた。1604年にはイタリアへ戻り、各地を転々としながら制作活動を続けることができた。ルーベンスは念願叶ってローマに滞在したが、当時の人口は11万人くらいで、ヴェネツィアよりも少なかった。しかし、画家にとってはギリシャ、ローマの膨大な遺産を学ぶと共に、当時活躍していた同時代の芸術家たちの活動を学ぶには宝庫のような場所であった。ローマが持っていた吸引力の大きさには改めて驚かされる。
続く