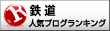長年つき合って、今や男女の間柄から、兄妹のような関係にまでなってしまった彼が、突然、食道ガン。余命は半年と宣告を受け、それから二人三脚のガンとの闘い。
1年半後の死を迎えまで、少しの後日談を含めての、壮絶な、それでいて何だか不思議なまで、飛んでいる小説。
作者が実にユニークな人生観、哲学観、生活感覚の持ち主のせいか(読者にそう思わせているだけなの話なのだが)現代的で、実は日本の伝統的な私小説の体裁をとっている。「行かず後家」になってしまった、と自嘲気味というか、居直っている語り口が見事。
この方、両親の面倒を(父親の介護も彼の死後、ほぼ同時に始まっている)見、大学での授業などをこなしながら、さらに自分の「鬱」病の薬を飲みのみ、ガンのために東奔西走する心理。
蟹(ガン)の会話の中では、その最愛の人の命を奪った悲しみ、苦しみ、恨み辛みを精一杯表現している(蟹=ガンは、ある意味、通俗的な置き換えだが)のも、経験を乗り越えた(つつある)、彼女の置かれた現状を巧みに読者に印象づけている。
読者には、様々な受け止め方があるだろう(その文体に、読者からの好き嫌いが激しくなってしまう、作家の一人か)。
1年半後の死を迎えまで、少しの後日談を含めての、壮絶な、それでいて何だか不思議なまで、飛んでいる小説。
作者が実にユニークな人生観、哲学観、生活感覚の持ち主のせいか(読者にそう思わせているだけなの話なのだが)現代的で、実は日本の伝統的な私小説の体裁をとっている。「行かず後家」になってしまった、と自嘲気味というか、居直っている語り口が見事。
この方、両親の面倒を(父親の介護も彼の死後、ほぼ同時に始まっている)見、大学での授業などをこなしながら、さらに自分の「鬱」病の薬を飲みのみ、ガンのために東奔西走する心理。
蟹(ガン)の会話の中では、その最愛の人の命を奪った悲しみ、苦しみ、恨み辛みを精一杯表現している(蟹=ガンは、ある意味、通俗的な置き換えだが)のも、経験を乗り越えた(つつある)、彼女の置かれた現状を巧みに読者に印象づけている。
読者には、様々な受け止め方があるだろう(その文体に、読者からの好き嫌いが激しくなってしまう、作家の一人か)。