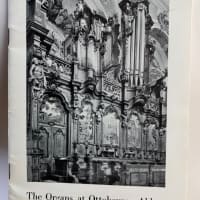Frank Brangwyn. Youthful Ambition. 1917, Lithograph on paper 45.5x35.5cn, Groeningemuseum, Bruge
若者が大志(大きな志)を抱くことは当然だし、望ましいことでもある。大きな志はそれを実現しようとする意欲の充実や努力にもつながる。若い時から「小成」(少しの成功)に安んじることはない。大志を抱けるのは若い人の特権だ。歳を重ねるごとに、現実との軋轢を重ねて、かつての大志も「小志」になってしまうことは世の常のことだ。
一人の若者が雨に濡れる岸壁に立って、海上はるか沖を見つめている。その視線の先におぼろげに見えるのは、巨大な軍艦だ。その後方にも別の船影が見える。これはなにを主題としたものか。しばらく考えた後、画家が『若者の功名心』 Youthful ambitions と画題を付していることに気づく。きわめてあっさりと描かれたリトグラフだ。制作年次は1911年。次第に画家が考えた主題の輪郭が浮かび上がってきた。
遠くの沖合に霞む軍艦を眺める少年の姿からは、戦争に大きな期待を抱き、自分もそこで壮大なことを成し遂げたいというような強い野心のごとき思いは感じられない。細身の華奢な身体で、ポケットに手を入れ、自分になにができるだろうかという、ややはかなげな不安と期待のようなものが伝わってくる。
画家の名はフランク・ブラングィン Sir Frank Brangwyn(1867-1956)というベルギー、ブルージュ生まれのイギリス人である。20世紀前半、油彩画家、版画家、製図家、陶芸家、デザイナーなど、造形美術の広範な分野で活動した。生前はヨーロッパ、そして世界レヴェルでも大変よく知られた芸術家であった。しかし、画家の没後、その名は急速に忘れ去られていった。名前や作品の一部は知っていたが、特別展カタログを読んで、画家への理解はかなり広がった。
日本との関連もことのほか深い画家であった。上野の国立西洋美術館開館50周年記念事業として『フランク・ブラングィン特別展』が開催された背景の詳細を知った。国立西洋美術館の基礎となった「松方コレクション」の充実に大きな貢献をした人物なのだ。ブラングィンは、松方の依頼を受けて広範な協力をした。造船業経営者の松方幸次郎との深い交友が「松方コレクション」、そして国立西洋美術館の今日につながっている。これらの点については、ここでは記さない。
この画家についてまったく知らないわけではなかった。以前にかなりの関心を抱いたことがあった。作品のいくつかは、イギリスでしばらく過ごした時にロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート美術館などで見たことがあった。ブルージュへ旅した時にもいくつかの作品に接した。
最大の関心は、ブラングィンが多才な芸術活動の一部で、「労働」というテーマに大きなかなりのエネルギーを割いていたことにあった。この画家は、短期間ウイリアム・モリスに師事した後、本格的な制作活動に入った。
「労働」の次元では、ブラングィンはトーマス・カーライル、モーリス師などのヴィクトリア朝労働観、イデオロギーを継承し、モリスの影響も受けて、労働(とりわけ男性労働)の持つ英雄的側面、社会への自己犠牲的貢献をテーマとする作品をかなり残していた。広い意味で「働く世界」の探索を続けてきた人生で、かなり関心を惹かれ、いつか暇になったら、この画家について少し詳細に立ち入ってみたいと思ったことがあった。しかし、その時間はなかなか与えられなかった。
ブラングウィンが「労働」を扱うテーマの対象として描いた人物は、筋骨たくましい男性が多く*、同時代で女性が殆どの対象であったロセッティ、レイントンなどの作風とは顕著な対比を見せている。ブラングィンの労働観については、大変興味深い点があり、記してみたいことも多いが、今はその余裕はない。
カタログによると、ブラングィンは第一次世界大戦中、イギリス情報省からクラウセンなど9人の画家とともに、大戦のさまざまな光景を記録する一人あたり6枚のリトグラフの制作依頼を受けていた。作品は1917年にロンドンの画廊で「大戦:英国の努力と理想」展で公開、販売された。しかし、彼らに求められたことは直接的に戦争を賛美する「戦争画家」ではなく、戦地あるいは後方で起きていることをそれぞれに描出することであった。それが戦争という難事に画家ができる社会貢献と考えられたようだ。
この依頼にブラングィンは「船乗りを養成する」のテーマで連作を出展し、このリトグラフはその一枚として制作された。この画家が描いた力強い労働者の姿とは、ほど遠い、いまだどこへ行くか定まらないような若者の姿である。日本やドイツにも存在した「戦争画家」の作品イメージとはかなり異なっている。
ブラングィンが抱いていた労働観は、ヴィクトリア朝の労働観・イデオロギーを継承していた。造船所経営者であった松方幸次郎が好んだ造船所の風景や筋骨逞しい労働者たちの姿は、労働が持つヒロイック(英雄的)なイメージを象徴していた。言い換えると、労働を社会への自己犠牲的貢献の行為とみなしていた。こうした画家の力強い労働者像と比較すると、この若者が体現するとみられる大志 ambition とは、画家の心底でいかに結びついていたのだろうか。ブラングィンという忘れられていたもうひとりの画家の実像を測るひとつの鍵がありそうだ。
* このブログの記事と関連して、ブラングィンの作品 Men in a Bakehouse (「パンを焼く男」:東京国立博物館所蔵、エッチング、1908年)は、しっかりと強固に描かれた厳しい労働に従事する男の姿を描いている。幸い、日本には東京国立博物館を中心に、かなり多くのブラングィン作品が残されている。
国立西洋美術館『フランク・ブラングィン展』公式ホームページ