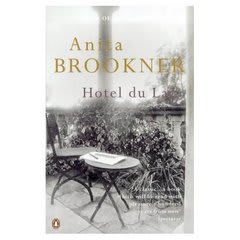
いつの間にかあたりに増殖した書籍、資料を整理している中に、Anita Brookner. Hotel du Lac (邦訳:アニータ・ブルックナー、小野寺健訳『秋のホテル』)があった。イギリス文壇最高の栄誉といわれるブッカー賞の受賞作(1984年)である。実際に読んだのは、かなり後の1995年頃であった。カズオ・イシグロの『日の名残り』を読み、映画を見た前後である。
あることから心の傷を負った主人公が、友人が手配してくれたジュネーブ、レマン湖畔のホテルで過ごす間の出来事として、話は展開する。鬱屈したストーリーでありながら、静謐な爽やかさと叙情性をもって描かれている。主人公の女性イーディス・ホウプは、ヴァージニア・ウルフに似た容貌であることになっているが、小説自体も『ダロウエイ夫人』を思わせるようなかすかな陰影を感じさせる。
美術史家としてのブルックナー
小説の内容に立ち入ることが目的ではないが、別の点で気になっていたことがあった。そのひとつは、ブルックナーが小説家になる前から18-19世紀のフランス美術史家としてコートルード美術研究所 Courtauld Institute of Art の教授であり、1967年にケンブリッジ大学のスレード・プロフェッサーに任じられていたことである。ちなみに、初代はジョン・ラスキンだった。ブルックナーはこの分野ですでに立派な業績を残していた。Watteau, Greuze, Jacque-Louis Davidなどの著書がある。美術史家としての背景がおそらく小説にも反映するのだろう。淡々としていながらも描写に陰翳があり大変美しい。なぜ、小説を書くようになったか、その背景を知りたくなった。
もうひとつ気になっていたことは、『秋のホテル』という邦訳名であった。原著の英文タイトルは Hotel du Lac であり、邦訳が出てもしばらく気づかなかった。その後、邦訳を手にして「あとがき」を見ると、訳者は名手の小野寺健氏だが、「デュ・ラック」という言葉が読者に分かりやすいものではあるまいとの編集部の考えもあって、『秋のホテル』になったと記されていた。『湖畔のホテル』では平凡すぎる、あるいは軽薄な印象を与えるということだろうか。今日まで気になっていた。
原著と翻訳の間
原題を知らずに邦訳を読んだ場合には、おそらくほとんど違和感なく受け入れているのだろう。確かに人生の秋を思わせるような印象もないではない。しかし、同時に、ジュネーブのレマン湖に近い、特別の設定をされたホテルで静かに繰り広げられるストーリーには、必ずしも「秋」という設定にしない方がよいように思われた。
こうした感想を抱きながら、その後これもふとしたことから読むことになったカズオ・イシグロのA Pale View of Hills (1982)も、小野寺氏の訳で、最初筑摩書房から刊行された時は『女たちの遠い夏』という題名で、なんとなく生硬な感じがしていたが、2001年に早川書房から文庫版となった時には『遠い山なみの光』に改題されている。
小説のホテルとはまったく関係ないと思われるが*、Hotel du Lacという同名のホテルが、ジュネーブ、レマン湖畔に存在する。この小説が刊行される前のことだが、偶然にもこのホテルの美しい屋外レストランで夕焼けに映える湖面のヨットや遊覧船を眺めながら、ひと時を過ごしたことがあった。表題を見るたびに思い浮かべる記憶の底の情景である。
Reference
Anita Brookner. Hotel du Lac. London: Granada, 1985.(『秋のホテル』小野寺健訳、晶文社、1988年)
*かなり知られているホテルであり、もしかするとブルックナーはなにかのヒントを得たのかもしれない。知りたいところではある。

























