
ウクライナ情勢が緊迫している。ロシアそしてベラルーシの国境付近に演習の名目で集結しているロシア軍は、第二次世界大戦の兵力にほぼ匹敵するともいわれている。ヨーロッパ(NATO加盟諸国)とロシアの間に挟まれ、緊張と危機感に満ちた日々を過ごすウクライナ国民の状況を見ていると、17世紀神聖ローマ帝国(ハプスブルグ家)とフランス王国との間に挟まれた形であったロレーヌ公国の姿が重なり合って見えてきた。ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593~1652)は、この地に生まれ、生涯のほとんどをここで過ごした。
17世紀、ラ・トゥールが生まれ育ったロレーヌの地政学的状況*は、このブログでも再三取り上げてきた。今日のロレーヌはフランスの北東部に位置し、美しい農村、山林地帯が展開する平和な地域だが、17世紀は戦争、悪疫、飢餓などが次々と襲う苦難の地域であった。後世、世界史上初めて「危機の時代」と呼ばれることになった。この時期、世界は小氷河期にあったともいわれる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
*N.B.
ロレーヌの名が生まれたのは、843年のヴェルダン条約でフランク王国が3分され、中央部をロタールが支配、ロタール2世の名にちなんで名付けられたロタリンジー(ロートリンゲン) のがその名の起源とされる。ロレーヌ公国は、神聖ローマ帝国とフランス王国の間で独立を保って生きることを選択した。そして、領土内に3司教区(メッス、ヴェルダン、トゥール)を含む複雑な地政学的状況にあった。ロレーヌ公国シャルル4世(ロレーヌ公在位1624-1675)の時代に、ロレーヌ公とフランス王との対立が高まった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
17世紀、ラ・トゥールが生まれ育ったロレーヌの地政学的状況*は、このブログでも再三取り上げてきた。今日のロレーヌはフランスの北東部に位置し、美しい農村、山林地帯が展開する平和な地域だが、17世紀は戦争、悪疫、飢餓などが次々と襲う苦難の地域であった。後世、世界史上初めて「危機の時代」と呼ばれることになった。この時期、世界は小氷河期にあったともいわれる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
*N.B.
ロレーヌの名が生まれたのは、843年のヴェルダン条約でフランク王国が3分され、中央部をロタールが支配、ロタール2世の名にちなんで名付けられたロタリンジー(ロートリンゲン) のがその名の起源とされる。ロレーヌ公国は、神聖ローマ帝国とフランス王国の間で独立を保って生きることを選択した。そして、領土内に3司教区(メッス、ヴェルダン、トゥール)を含む複雑な地政学的状況にあった。ロレーヌ公国シャルル4世(ロレーヌ公在位1624-1675)の時代に、ロレーヌ公とフランス王との対立が高まった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
混迷の時代、戦乱、悪疫、飢饉
ラ・トゥールが生まれた土地ヴィックからリュネヴィルに移ってからは、画家としての生活は、年を経るごとに安定し、充実したものとなった。画家の天賦の才は、時代の求めるものをしっかりと受け止め、人々の心に深く響く作品へと結実していった。自宅、工房も整い、徒弟も住み込みで本来あるべき形で画業を続ける環境ができてきた。ラ・ トゥールの心もロレーヌの画家として、この地を活動の拠点とすることに傾いていた。つかの間の安定した画業生活だった。
しかし、背後ではこうした平和で牧歌的、豊かな地というイメージを、根底から揺るがすような大激動の予兆が忍びよっていた。1620年代後半頃から、ロレーヌは、外国の軍隊が町や村々を次々と破壊、蹂躙し、悪疫が流行する困難な時期へ移りつつあった。
ラ・トゥールが生まれた土地ヴィックからリュネヴィルに移ってからは、画家としての生活は、年を経るごとに安定し、充実したものとなった。画家の天賦の才は、時代の求めるものをしっかりと受け止め、人々の心に深く響く作品へと結実していった。自宅、工房も整い、徒弟も住み込みで本来あるべき形で画業を続ける環境ができてきた。ラ・ トゥールの心もロレーヌの画家として、この地を活動の拠点とすることに傾いていた。つかの間の安定した画業生活だった。
しかし、背後ではこうした平和で牧歌的、豊かな地というイメージを、根底から揺るがすような大激動の予兆が忍びよっていた。1620年代後半頃から、ロレーヌは、外国の軍隊が町や村々を次々と破壊、蹂躙し、悪疫が流行する困難な時期へ移りつつあった。
最大の災厄は、30年戦争*といわれるヨーロッパの広範な地域で展開した戦争であった。ロレーヌもその中に巻き込まれた。この戦争がいかに過酷で深い傷跡をヨーロッパに残したかについては、今日においてもこの戦争を取り上げた数多くの研究書が刊行され続けていることからも分かる。
このブログでも「危機の時代」「悲劇のヨーロッパ」を分析したいくつかの研究を紹介してきた:
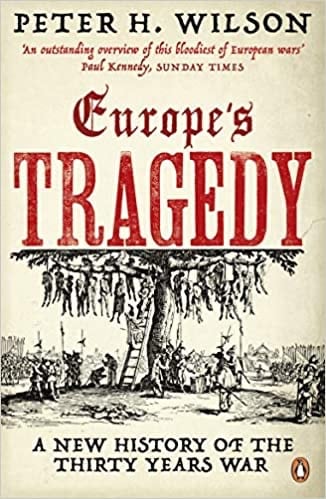
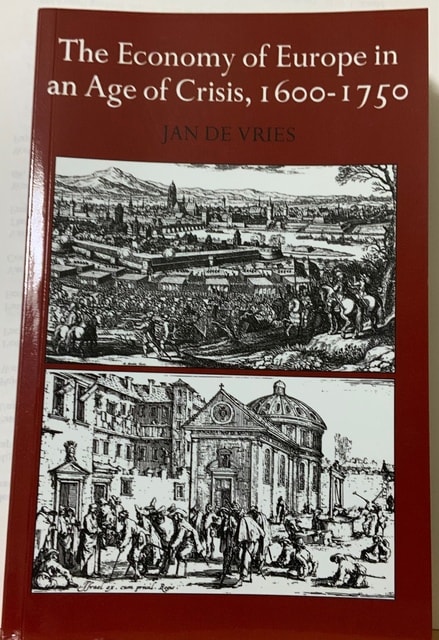
戦争と並び劣らず恐れられていたのは突如襲ってくる目に見えない悪疫の流行だった。悪疫の中ではペストが最も恐れられていたが、ロレーヌは何度かこうした災厄に襲われていた。悪疫はしばしば外国の軍隊の進入に伴って、持ち込まれた。軍隊の兵士のほとんどは、傭兵であった。そのため、しばしば「ハンガリー・ペスト」の名で知られていた。1626~27年もロレーヌではペストが流行し、人々の大きな不安と恐れの種となっていた*。こうした災厄の犠牲になるのは、ほとんどいつも農村部の農民たちであった。
*リュネヴィルの城門にはこの年、ペストのあった町からやってくる者は、入城を禁じるとの布令が出た。布令を記した画家には1フラン6グロスが支払われ、橋の上にはバリケードが築かれた。1631年、リュネヴィルの記録文書が空白になっている時も、町は激しいペストに襲われていた。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
*N.B.
30年戦争(1618-1648年)
ドイツを中心に続いた戦争。ハプスブルグ対ブルボン王家の敵対とドイツの新旧両教徒の対立を背景に、皇帝の旧教化政策を起因としもてボヘミアに勃発。新教国デンマーク、スエーデン、後には旧教国フランスも参戦。ウエストファリア条約で終了。ロレーヌ公国は戦場となった。ロレーヌの町はスペインやオーストリアのカトリック側に加担し、フランスからの攻撃の対象となった。ロレーヌの町の多くは、皇帝軍とルイ13世の国王軍との争奪戦で完全に破壊された。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
危機の現代を考えるために
ラ・トゥールが残した数少ない作品は、この時代、ローマ、パリなどで活動した画家たちの華やかなバロック風とは全く異なるものだった。イタリアでの修業などの機会が与えられれば、ラ・トゥールにもプッサンなどに代表される壮麗な宮殿画などを制作しうる技量は十分備わっていたと思われる。しかし、この画家は自らが生まれ育ったロレーヌの地で画業を全うする道を選んでいた。その結果はリアリズムに徹した画題に深く沈潜し、同じ主題をさまざまに追求する中で精神性の高い作品を多く生み出すことになった。風俗画の範疇に入る作品にしても、農民の貧しい生活を描いた《豆を食べる人々》などのように、リアリズムに徹していた。この画家の作品は、単に画面に美しく描かれているという次元には止まらない。画家が真に何を描こうとしたのか、カンヴァスの裏面にまで深く立ち入ってみたいという衝動を惹き起こす。
ラ・トゥールが残した数少ない作品は、この時代、ローマ、パリなどで活動した画家たちの華やかなバロック風とは全く異なるものだった。イタリアでの修業などの機会が与えられれば、ラ・トゥールにもプッサンなどに代表される壮麗な宮殿画などを制作しうる技量は十分備わっていたと思われる。しかし、この画家は自らが生まれ育ったロレーヌの地で画業を全うする道を選んでいた。その結果はリアリズムに徹した画題に深く沈潜し、同じ主題をさまざまに追求する中で精神性の高い作品を多く生み出すことになった。風俗画の範疇に入る作品にしても、農民の貧しい生活を描いた《豆を食べる人々》などのように、リアリズムに徹していた。この画家の作品は、単に画面に美しく描かれているという次元には止まらない。画家が真に何を描こうとしたのか、カンヴァスの裏面にまで深く立ち入ってみたいという衝動を惹き起こす。
ロレーヌがフランスに併合されて以来、激動の地で画業生活のほとんど全てを過ごしたラ・トゥールは、17世紀フランスを代表する大画家としての地位を不動のものとしている。
現代の世界は、産業革命以降の資本主義展開に伴い、17世紀にヨーロッパ社会が経験したような様々な危機的要因が大きく増幅されてきた。このブログで取り上げてきたラ・トゥール、そして時代を降って、L.S.ラウリーと、全く異なる異なるコンテクストながら、危機の時代における人間のあり方を考える大きな手がかりとなる。
続く

























