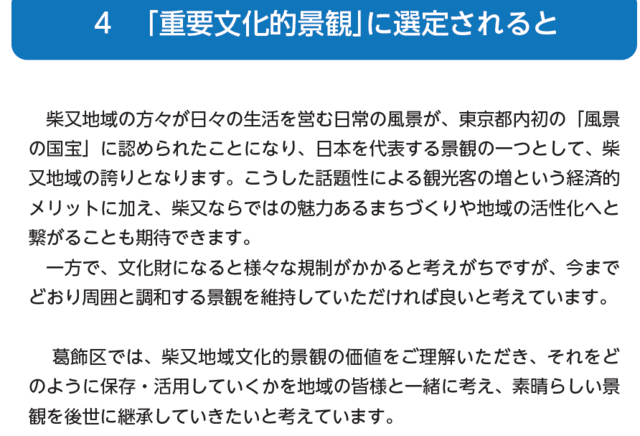大正・昭和期の柴又用水跡を歩く
(葛飾探検団・記録用 )
=柴又用水のもう1つの水源 、新八用水路=

大木が生い茂るところが、新八用水路です。
駐車場、サッカー野球場があり日曜日とあって多くの観光客が訪れて居た。

水路口は雑草で被われてわからなかった。

河川敷に水路約70~80mが続く、江戸川の河川に行く葛飾探検団

新八用水路(江戸川の取水路)を見学する団員。

遠くに矢切の渡しの渡舟が見える。
◎ この付近の江戸川は、干潮時には、素足で対岸へ歩いて渡った場所だと言います(金町に長年住む古老談)
南葛時代の古い地図を見ると、川が二叉に別れ陸の孤島があったことが地図上で明確になった。
金町の古老談を裏付けることになります。
◎ この僅か上流が『矢切の渡し』です。細川たかしのヒット曲は、ここから生まれた。
◎ 日曜日で、お客さんが渡船で楽しむ様子が、木陰から望見できた。
 ←クリック拡大
←クリック拡大
東京府南葛郡地図
江戸川に孤島があり
浅瀬であったコトが良く解る
「参考」
矢切の渡し付近は「からめきの瀬」と呼ばれていた。これは浅くて攻めやすいと言う意味で、「カラめての瀬」が変化したものと言われている。
2度にわたって国府台合戦が行われたが、この辺一帯が戦場として、葛西城に陣を取った、後北条死と里見城に陣を取った里見氏の間に江戸川を挟んで1万人の人々が命を落としたと言われている。
長閑に行き交渡しを見ているとそんなことは微塵も考えられない。
以下文献による。
↓
「大正・昭和における柴又用水における
利用と維持管理の変遷」
山科 盛人 福井 恒明 (引用)


住民の方々からのヒヤリングにより、次の情報を得た。
新八水路
↑ 火災保険図、図-15にて確認できる、江戸川と接続している水路を≪新八水路≫と呼ばれていた。
水路脇には、「新八酒屋」があったことから由来すると言う。
新八水路を介して、柴又用水への水の管理を行っていたのが、「圦番屋」(入番屋)である。
江戸川の潮の満ち干は、春先の雪溶けや台風により水位が変わる。水路に設けた堰枠への堰板の出し入れによって、水利が上がった時取水し、水位が下がった時閉じる操作を行った。
しかし、江戸川河川改修や上流の取水によって水位の低下によりこれが不可能となった。
そのために足踏み水車を使い、人力によって取水を行った。足踏み水車は、3段階繋げて取水する必要があった。1段階に3台づつ、計9台の足踏み水車が並んだと言う。足踏みの労働は、住民が交代で行い、交替時間の計測は、線香を用いて、燃え尽きるまでを交代目安とした。
昭和に入り水車に代わって、クボタ発動機〈1922年生産開始〉を用いて取水(揚水)が行われた。この発動機が故障すると、修理するものがおらず、クボタ本社の京橋までの1日がかりで修理に行った。
昭和10年ころになると、電線を引きモーターを導入して水をくみ上げた。コンクリート基盤(120cm×120cm程度)が江戸川河川敷に1基残存し、水位低下時には確認できると言う。


江戸川河川敷に、コスモスが咲いていた。

柴又の土手から眺めた山本亭
葛飾探検団は、歩いて現場実査し、自ら学び、発表し、皆さんが学んだことを共有し、記録に留めて後世への資料とします。今回は「柴又の文化的景観」ということで柴又帝釈天を中心として3部門に分かれて見て回りました。次会それぞれ感じたこと、思わぬ発見があり、その内容を皆さんとで語られることでしょう。
次回は金町浄水場の記事を掲載します。
コメ欄は閉めています。














 したと言う。
したと言う。