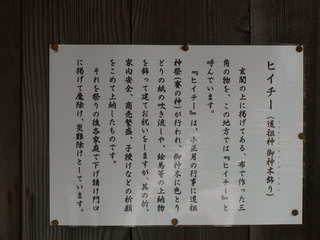戦後は今から思えば何もなかった。
自給自足・稲わらでぞうりを編み通学や遊びに使った。
その後ゴム草履になったり下駄になったり・・・。
運動靴は配給制で、
1年に1クラス(45名)に
ほんの3~5足でくじ引きで分配した。

観光地で買い求めた。
我が家の玄関に飾ってある。
家内も山行に出かけるため『足元が一番大事』という意味から
出かけるとき先ず身支度の確認。

草履の編み方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日のメモ
子供たちへの伝承文化記録(覚書)
最近の記事にショイタ、ゾウリ、半鐘、囲炉裏と昔の道具、
農家の暮らしを伝承文化として掲載しています。
縄文人は農家の貧しい家に育った。子供たちに断片的に話したことがあるが
全体像、具体的なものは何も語り継いでいない。
細かいことを話しても、現代とあまりにもかけ離れていて
『ばかばかしくて話にもならない・・・・・今は違うよ・・』と、子供たちは
聞こうともしないし、また話す本人も熱意が薄れてもきた。
子供たちも大きくなり孫がいる歳となりギャップも大きい。
こうして毎日書き綴っているのは、縄文人の半生、幼少期の農家の暮らしの
懐古(ノスタルジック)の面も多分にある。
後日に読んで何か読み取ってもらえれば幸いと思っている。
そんな意味から
『子供たちへの覚書=語り部』のつもりで記録している。
CDに保存している。
この『道具と伝承文化記録』を書くきっかけになったのは、
山梨県・忍野村に行ったときでした。
戦後の食糧難時代に農家が盛んにもてはやされ、
大事にしかも便利に使われていた農道具が、いとも簡単に
農家に軒下に風雨にさらされていた。
何か、いとうしくなり自分の心を傷つけていたように思えた。

昭和の子供たち写真集
石井美千子人形作品集から
参考文献
農家のモノ・人の暮らし大館勝治・宮本八恵子著