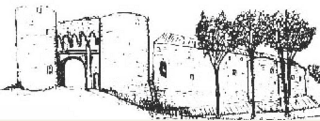ヴィックに残る城門跡
ラ・トゥールの絵を見ている間に、次第に画家が生まれ育った場所を訪ねたいという気持ちが高まってきた。幸運が味方をしてくれた。1972年のオランジュリーでの「ラ・トゥール特別展」に感銘を受けた当時、アメリカでの大学院時代以来のつき合いで、いまや生涯の友人となったK教授(経済学、社会経済史)が、当時フランス国境に近いザールブリュッケン大学に勤めていた。週末、パリから移動しては泊まり込み、夫妻と一緒に国境を越え、アルザス・ロレーヌの町や村を訪れる機会に恵まれたのである。
交通は便利とはいえない地域のため、友人の存在は大きな力となった。この時はお互いに若く、大変エネルギッシュに色々な場所を見に行った。その後も何度も訪れる機会があったが、今でも最初に目にしたブドウ畑や林が広がる起伏のある光景が目に浮かぶ。
画家の生い立ち
ラ・トゥールは、1593年3月、フランス北東部のロレーヌ地方、ヴィック=シュル=セイユでパン屋の息子として生まれた(洗礼は3月14日)。祖父は石工であった。パン屋だった父のジャン・ドゥ・ラ・トゥールは、代官や町の参事会員などとも交際があり、ヴィックではそれなりに知られた人物であった。
城郭で囲まれた小さな町であり、情報もかなり速やかに人々の間に広がったことだろう。彼が、家業とは異なる画家を志した動機、いかなる修業の時代を過ごしたのかについては、記録もなく推測の域を出ない。
当時、世代ごとの職業の転換がどの程度一般的なものであったのかも、職業や労働の領域を専門としてきた私としては大変興味があるが、今も不明なままに残されている。画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールや彼の息子エティエンヌのその後などから推測すると、才能や財産に恵まれれば、案外社会的な流動性は高かったのではないかと思われる。加えて、17世紀前半、アルザス・ロレーヌ地方は戦乱を含めて、激動の歴史的舞台でもあった。特に、ラ・トゥールの後半生はしばしば戦乱や悪疫の流行に脅かされた。
1972年に私が訪れた時は、ヴィックはモーゼル川の支流としてのセイユ川が流れる人口1500人くらいの小さな町だったが、ラ・トゥールの生まれた16世紀末から17世紀の頃は、人口も今の10倍くらいあり、かなり隆盛をきわめたようである。最初に訪れた時は、ラ・トゥールの生地ということもほとんど知られていなかったこともあり、特徴もない寂れた小さな町という印象だった。しかし、ラ・トゥールの評価が高まるにつれて、町は急速に脚光を浴び、2003年には画家の名をつけた小さな美術館も開館した。新たな資料研究の成果や作品の発見なども加わり、闇に埋もれていた画家としての生涯もおぼろげながら明らかになってきた。
さて、当時の社会状況からすれば、パン屋の息子が画家になるためには、当時の技能習得に欠かせなかった徒弟制度を経由することが普通であった。先ず近隣で知られた画家の工房に徒弟として弟子入りし、親方の画家あるいは兄弟子から画家として必要なテーマの選択、技法など基本的なことを学ぶ修業の年月を過ごすことが普通だった。当時の徒弟は、画家に限らず、大体14歳くらいでスタートし、職業や地域で異なるが、4年近い修業が必要とされた。ラ・トゥールがそうであったとすると、1604年からの4年間くらいが徒弟の時期であったと推定される。
徒弟の記録は残っていないが、当時ヴィックで名をなしていたドゴスという親方画家の工房で修業したのではないかと推定されている。というのも、いずれ記すように、ラ・トゥール家とドゴス家の間には親交があったとみられる記録が残っている。画家の生涯の後半にあたる1647年、ドゴスの姪フリオがジョルジュ・ラ・トゥールの息子エティエンヌと結婚しているからである。
ジョルジュ・ラ・トゥール自身はその後、ロレーヌ地方で画家としての名が知られるようになり、1617年、リュネヴィルの下流貴族の娘ディアーヌ・ル・ネールと結婚している。彼はその後、妻の生地であるリュネヴィルで生涯の大部分を過ごしたと推定されている。リュネヴィルはヴィックの南西20キロメートルほどのところに位置している。この地方の中心都市ナンシーも、ヴィックやリュネヴィルから直線距離で20から30キロメートルほどの近さだ。
17世紀初め、ヴィックはメスの司教管轄区、リュネヴィルはロレーヌ公爵領に属していた。ヴィックは、17世紀当時の隆盛を偲ばせるシャトーや教会などもある趣のある町だった。ロレーヌ地方は、現在のフランス北東部、アルザスの北に位置し、北はアルデンヌの森、南はヴォージュ山脈に接している。この地方は、ドイツとフランスの中間ともいうべき位置にあり、石炭や鉄の産地として、経済的豊かさにも支えられ、1000年も前から領土争奪の焦点だった。
ラ・トゥールの生きた時代、この地域は30年戦争(1618―48年)の舞台となって荒廃し、その後もたびたび戦場となった。第一次大戦、第二次大戦ではヨーロッパ最大の激戦地のひとつとなり、文字通り戦火の絶えない動乱の舞台であったといえる。最初にアルザス、そしてロレーヌ地方を訪れた時は、今に残るマジノ線のトーチカ、塹壕の跡に驚かされた。
さらに、第一次世界大戦時にはおよそ13万トンの砲弾が行き交ったといわれるヴェルダンの要塞も近くにある。第一次世界大戦でドイツが敗北し,1919年6月アルザス・ロレーヌはフランス領となった。第二次世界大戦中は一時ドイツに併合されたものの,戦後はフランスの一部として現在にいたっている。欧州共同体(EC)当時から欧州議会(本会議)は、ストラスブールに置かれている。
アルザス・ロレーヌでは戦場の跡ばかりでなく、ラ・トゥールにゆかりのある城址(ヴィックに残る城壁、城門)、教会、修道院の跡など、かなり多くの場所を訪れた。フランス側とはいえ、ドイツ語が自由に通じたことも思い出した。
ドイツ国境に近いロレーヌの町メッスでは川魚料理が名物な所があり、美しい橋を望むレストランで、勧められるままに注文したわかさぎのフライのような料理が印象に残っている(花より団子!)。