農家の佇まい、土間に入ってみると・・・
世田谷区・崖線を歩く
その5-3
古きを尋ね、新しきを知る。
少年時代を髣髴して…数々の思い出に浸かった。して・・教えられた。

この民家園の木材が厚くて大きい。
次大夫堀の「木挽きの会」が作ったのではなかろうか・・・夢を膨らませた。
そんな気がして、しげしげと見つめた。
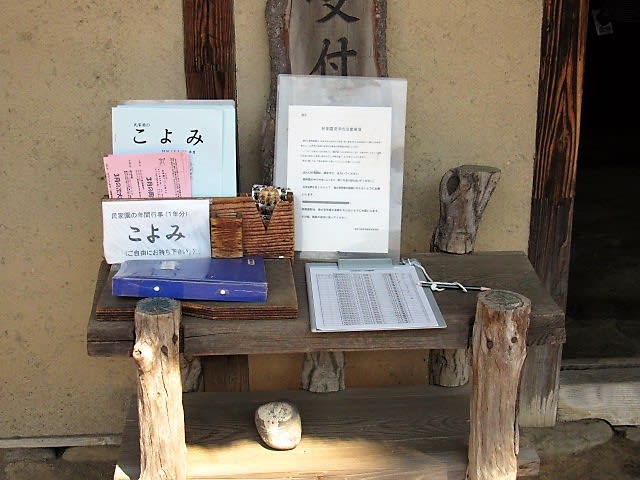
民家園入り口です。
「こよみ」を貰って来ました。
内容を見ると1月から、12月までビッシリと、1覧表となって、
正月行事、節分、春彼岸、節句、茶摘み、養蚕、十五夜、すす払い、等々
ほとんどの農家の行事がぎっしり詰まっていた。
懐かしい行事を思い浮かべるとともに、農村の民俗行事の
多いことが分かりました。
そしてこれらが、民家園で行われているという。

Fリーダーが言った。
この但し書き「茗荷の皮で編みました」・・・・、
!!!???
改めて見直しました。

1つ1つが農民にとっては生産の手段道具でした。

養蚕の蚕棚、餅つきの杵と臼、肩で担ぐ桶などが
所狭しとありました。

哀愁の煙たなびく自在鉤
煤ぼけてあり上げ下げ健在 (縄)

石臼やぐるりぐるりと回しけり
親子の会話お前何に成る (縄)

世田谷の崖線で落ち葉集めをして、畑や家畜の休み場として使われた。

トイレWC。
なぜか昔の建築様式の造りは、別棟として外にWCがありました。
今思うこと・・・。
「古き訪ねて新しきを知る」こんな言葉があります。
古のことは、この年、八十路を過ぎても鮮明によみがえる。
哀愁・思い出・懐かしい・・・・・。
これらの言葉は過去をすべてを覆いかぶせて、その境地から抜け出せない。
小さい時の学問、躾け、習慣が、如何にその人間を左右するのであろうか、つくづく思い知らされた。 山深き秩父の里では、学問などあろうはずがない、早くに親に死に別れた家庭環境でした。その日その日生活ができればそれでよかった。
茅葺の屋根の佇まい、土間、農道具、日常生活具などそんな思いがあれよあれよと蘇ってきた。
コメ欄は閉めています。
















