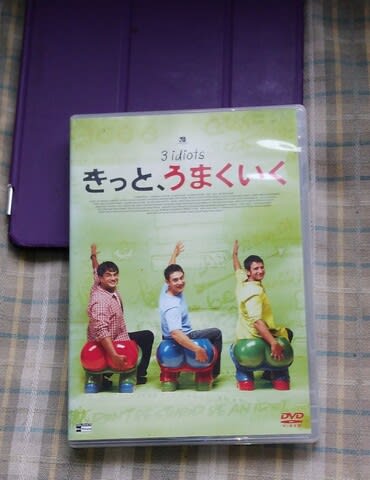久し振り(そうでもないか?)、のネットフリックス。
「シェークスピアの庭」
以下、ネタバレアリ
ロンドンで名声をあげた後、劇場の火災などもあって故郷に戻ってから、晩年のシェークスピア(1616年没)です。
1616年は日本なら大阪夏の陣の翌年に当たります。
18才で年上の女性(アン)とできちゃった婚をしています。
故郷に妻子を置いて20年にもわたって、ロンドンで作家活動をしていたので、女の子二人、男の子ひとりの3人の子どもはすべてアンが育てました。
アンは読書きができないので、結婚証明書にサインするときも、自分の名前を書けずに✖を書くしかなかったのが、悲しかったと。長女は読書きができ、お医者さんの妻となっているのですが、夫婦仲が上手くいっていません。
28才になる二女は読書きができず未婚。
唯一の男の子は少年の頃に伝染病かかって病没した。
その息子が書き残した詩を綴った詩編を大切に抱え持っている父親・シェークスピア。
息子の才能を惜しむ心が、帰郷したシェークスピアに、息子を偲んでの庭づくりを思い立たせる。
成功者であるシェークスピアは財産には不足しない。
但し、相続する男子がいないことから(娘が相続する=娘婿の財産扱い?)、2女にも結婚をしてもらいたい、というモードもあったり、、、。
シェークスピアは、息子の死の知らせを受けても、仕事に追われて帰郷することができなかった。
息子の伝染病での死が信じらない。
そのことを家族に詰問する。母親であるアンは伝染病だったと言い張る。
年月が経過してようやくハムネット(息子)の死の悲しみを一緒に暮らしてきた家族で乗り越えてきたのに、突然帰郷して蒸し返さないでほしい、と。
彼は教会で死者の記録を閲覧する。
確かに没年月日と名前は綴られていたけれど、その年の村の子どもの死者数は伝染病の流行した年の死者数とは思われない。
あまりにも、死んだ息子に執着するのを見かねて、未婚の2女は白状する。
その紙片に綴られた詩は
自分が作ったものをハムネットに聴かせたら、文字が書ける彼が書き留めたものだ、と。
アンも言う。この2女は文字は書けないけれど、韻を入れた詩作ができるのよ、と。
ハムネットには父親が褒めたたえるほどの才能の持ち主ではなく、買いかぶり過ぎたったんだと。
池でおぼれているハムネットを見つけた時、破棄された紙片も傍らに浮いていた。
16世紀後半から17世紀初め。
時代考証もしっかりされていて(日本にオランダ人がやってきた頃に重なるので、あの白い襟姿の時代です)、夜の灯りは燭台の蝋燭だけ。16歳で放校となっシェークスピアだから、流行作家となっても貴族の教養であったギリシャ語はできないので、、、などとサラリと位置づけもされている、いい作品でした。
以前に「恋に落ちたシェークスピア」を観ているので、両方見ることができて至福です。
文学史の中で名前を記憶する有名人のイメージですが、こう映画として取り上げられると興味深いです。
追記
この映画のYouTube広告 (👆クリックすると出てくる)の解説には、この映画の監督・主演は、あの「ヘンリー5世」の監督なのですね。映画通ではないので。💦
自宅での映画鑑賞は、多くの場合はひとりで、なのですが、夫にザザッとあらすじを言うと、「キミの好きそうな作品だね」と言われた。そう、同じ監督の作品「ヘンリー5世」の中のセリフも大いに気に入り、日本語字幕を書き写したものです。(そもそもが翻訳なのに、こんなことする人ってレアでしょうね~、苦笑) で、2022年の「ベルファスト」という彼の自伝ものが今年の話題作とか。3月封切。これは滅多にいかない映画館に観に行こうかしら、と思っています。
「シェークスピアの庭」
以下、ネタバレアリ
ロンドンで名声をあげた後、劇場の火災などもあって故郷に戻ってから、晩年のシェークスピア(1616年没)です。
1616年は日本なら大阪夏の陣の翌年に当たります。
18才で年上の女性(アン)とできちゃった婚をしています。
故郷に妻子を置いて20年にもわたって、ロンドンで作家活動をしていたので、女の子二人、男の子ひとりの3人の子どもはすべてアンが育てました。
アンは読書きができないので、結婚証明書にサインするときも、自分の名前を書けずに✖を書くしかなかったのが、悲しかったと。長女は読書きができ、お医者さんの妻となっているのですが、夫婦仲が上手くいっていません。
28才になる二女は読書きができず未婚。
唯一の男の子は少年の頃に伝染病かかって病没した。
その息子が書き残した詩を綴った詩編を大切に抱え持っている父親・シェークスピア。
息子の才能を惜しむ心が、帰郷したシェークスピアに、息子を偲んでの庭づくりを思い立たせる。
成功者であるシェークスピアは財産には不足しない。
但し、相続する男子がいないことから(娘が相続する=娘婿の財産扱い?)、2女にも結婚をしてもらいたい、というモードもあったり、、、。
シェークスピアは、息子の死の知らせを受けても、仕事に追われて帰郷することができなかった。
息子の伝染病での死が信じらない。
そのことを家族に詰問する。母親であるアンは伝染病だったと言い張る。
年月が経過してようやくハムネット(息子)の死の悲しみを一緒に暮らしてきた家族で乗り越えてきたのに、突然帰郷して蒸し返さないでほしい、と。
彼は教会で死者の記録を閲覧する。
確かに没年月日と名前は綴られていたけれど、その年の村の子どもの死者数は伝染病の流行した年の死者数とは思われない。
あまりにも、死んだ息子に執着するのを見かねて、未婚の2女は白状する。
その紙片に綴られた詩は
自分が作ったものをハムネットに聴かせたら、文字が書ける彼が書き留めたものだ、と。
アンも言う。この2女は文字は書けないけれど、韻を入れた詩作ができるのよ、と。
ハムネットには父親が褒めたたえるほどの才能の持ち主ではなく、買いかぶり過ぎたったんだと。
池でおぼれているハムネットを見つけた時、破棄された紙片も傍らに浮いていた。
16世紀後半から17世紀初め。
時代考証もしっかりされていて(日本にオランダ人がやってきた頃に重なるので、あの白い襟姿の時代です)、夜の灯りは燭台の蝋燭だけ。16歳で放校となっシェークスピアだから、流行作家となっても貴族の教養であったギリシャ語はできないので、、、などとサラリと位置づけもされている、いい作品でした。
以前に「恋に落ちたシェークスピア」を観ているので、両方見ることができて至福です。
文学史の中で名前を記憶する有名人のイメージですが、こう映画として取り上げられると興味深いです。
追記
この映画のYouTube広告 (👆クリックすると出てくる)の解説には、この映画の監督・主演は、あの「ヘンリー5世」の監督なのですね。映画通ではないので。💦
自宅での映画鑑賞は、多くの場合はひとりで、なのですが、夫にザザッとあらすじを言うと、「キミの好きそうな作品だね」と言われた。そう、同じ監督の作品「ヘンリー5世」の中のセリフも大いに気に入り、日本語字幕を書き写したものです。(そもそもが翻訳なのに、こんなことする人ってレアでしょうね~、苦笑) で、2022年の「ベルファスト」という彼の自伝ものが今年の話題作とか。3月封切。これは滅多にいかない映画館に観に行こうかしら、と思っています。