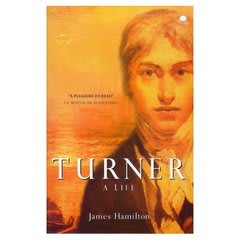絵画作品から画家の人となりや個性を推量することは、かならずしも容易なことではない。とりわけ同時代人でないほど、問題は難しくなる。この点は、17世紀の画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの研究においても大きな関心事のひとつであった。しかし、ラ・トゥールについては、画家自身が残した言葉や日記のようなものはなにもない。
作品と画家の個性などは別のものと考え、作品だけを鑑賞すればいいではないかという考えの方もおられよう。しかし、作品と画家の人間的側面、生涯などが分かれば、さらに興趣が深まるだろう。
先日J.M.W. ターナーについての文献を見ている間に、実はこのイギリス最大の国民画家ともいうべき人物のイメージと実像の間の乖離が、時が経つにつれて大変大きくなっていることに興味を惹かれた。実際、ターナーという画家には、かなり現実とは離れたイメージが意図的あるいは巧まずして形成された面がある。前者については、このブログでも触れたことがある。国民的画家としてかなり意識的にイメージ作りが行われたこともあって、才能と環境に恵まれ、「銀の匙」をくわえて生まれてきたような画家というイメージを持つ人もあるらしい。
ターナーはその生涯を通して、そして死後も名声赫々たる人物であるから、さぞかし華やかで社交的で、際だった個性の画家と思うかもしれない。自画像(1799年、24歳時)などを見ると、なかなか好青年に描かれている。しかし、これまでターナーについての研究は汗牛充棟ただならぬものがあるが、画家の個性や人となりについて掘り下げた文献はそれほど多くない。
イギリスにいる間に興味にまかせて、少し資料を渉猟してみたが、どうもこの画家はその多彩で膨大な作品と比較して、人間として記すべきものが少なかったらしい。ある資料は次のように述べている:
「実に困ったことは、ターナーは書くことがないきわめてつまらない人物であることだ(a very uninteresting man to write about)。人物という点でも生活においても、なにも、ひと目をひくような、ロマンティックな、あるいはわくわくさせるようなことがない。この画家の特徴であり、欠点でもあるのは退屈な人間ということである。彼はあらゆる点で卑俗 plebeianであり、どこにもいる労働者や商人であった。......唯一興味あることは、彼がターナーの絵を描いた男だということだ。」*
なんともイギリス人らしい皮肉ではある。しかし、ターナー自身は世渡りは大変うまかったようだ。なにしろ、1799年にはロイヤル・アカデミーの準会員、1802年には27歳という史上最年少の若さで会員に選ばれている。選ばれるまでは大変に人当たりもよかったらしい。しかし、ひとたび会員となった後は、愛想の良さはどこへやら、マナーも悪かったようだ。へきえきしたアカデミー会員のフランシス・ブルジョワ卿が「小さないやな奴(は虫類)」a little reptile と評したところ、ターナーが返した言葉は「でかいいやな奴」a great reptileであったとの逸話**が残っている。
とりわけ、ロンドンのコベントガーデンで生まれ、コクニーとして育った若い頃は行動は粗暴で、負けず嫌い、野卑なところが多かったようだ。さすがに、歳をとり、人生後半になると穏やな面も見られるようにはなったらしい。
しかし、遺書に書かれるまで、二人の娘がいることも隠されていたし、その娘たちを暖かに遇したこともなかったようだ。遺産相続でも自分の作品の保存には大きな関心を持っていたが、娘たちに特別な配慮はしていない。
負けず嫌いなことであったことも、いくつかのエピソードで分かっている。1832年のロイヤル・アカデミーの展示の際、ターナーは自分の淡い緑色で描かれた海の絵が、ライヴァルのカンスタブルが描いた鮮やかな「ウオーターロー橋の開通」の隣に掛けられているのを見るや、自室にとって返し、パレットをとってくるや一言も発することなく、自分の作品の上に赤い絵の具を塗りたくった。さすがにその後で、この部分を浮標(ブイ)の形に描き直したらしいが。びっくりしたのはカンスタブルで、「彼はここにきた。そして銃をぶっ放した」というのがやっとだった。
ターナーのこうした粗野、粗暴ともいえる行動がなにに起因するかは、必ずしも明らかではない。しかし、これまではあまり注目されなかった画家の労働者階級としての出自によるところが多分にあるように思われる。コベントガーデンの理髪屋の息子として生まれたターナーは、やはりイギリス的階級社会のひとつとしての労働者階級の特性をかなり継承していたと思われる。加えて、ターナーの家庭も、家業の理髪店は父親の人付き合いのよさなどで、なんとか維持されていたが、母親が精神を患い常にさまざまな騒ぎが絶えず、入退院を繰り返すなど、およそ正常な家庭の態をなしていなかった。
ターナーも成人して、社会的地位を確立し、栄誉に囲まれる段階になると、対人関係などにおいても奇矯な行動も少なくなり、普通の人間らしさを取り戻している。しかし、社会的階級の特徴が強く根付いていた150年ほど前の時代においては、自らが育った社会的条件から完全に自由となることは難しかったのだろう。画家としての生々しい人間像が明らかにされたからといって、それでこの偉大な画家の作品評価が変わるわけではない。しかし、希有な天才という光り輝く部分が前面に出ていた画家のイメージを、より陰翳と深みを持って描きなおすことができるのではないだろうか。
長い間、栄光と賛美に包まれていたターナーだが、死後150年余の年月を経て、作品と人間を統合した画家の実像が少しずつ明らかになっている。
References
*
Quoted by Andrew Wilton in Turner and His Time, London: Thames and Hudson, 1987, pp.6-7.
**
James Hamilton. Turner. London:Random House, 2004