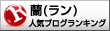あれから1年。
思わず下葉がどっかに落っこちてないかと探しましたがありませんでした。

葉繰りは1枚。
至楽よりのんびりしています。

まあ、散り斑とはいえ相当綺麗な柄ですからしょうがないのでしょう。
青光墨系と侮ってはいけないようで
地味な仔でも付いて力を添えてくれたらと思っていたところ

一本はそんな仔になってくれました。

羆の光崩れのような柄で
昔、こんな柄から散り斑も出ましたから先祖帰りしたかのようです。



もう一本の仔は中透け様の柄から天葉で散り斑、親と同芸になりそう。
これだけ役者がそろえば来年はまた勢いが復活してくるでしょう。




割り仔のほうも葉繰り1枚と生育はのんびり。
ただ、枯れる気配はなさそうでその点は安心して見ていられます。
それにつけても蘭舎栽培ですっかり姿はゆったり目になってしまいました。

3年前の姿に戻すにはこれから5年は掛かりそう。

おっと、そんなことを言う前に植え替えですね。
ミズゴケがこんな風になったら中に何かがいる証拠。
コバエが成虫になって出てきたら他の鉢にも卵を産み付けられちゃいますので。



あれから1年と4か月。
下葉を5枚も落とし天葉はちぎれ見るも無残なお姿に~~


しかし転んでもただでは起きないとしたもので
あの時の仔は無事生還。

ただ、きれいな白散り斑は影を潜めましたが。

それにもう1個仔が付きました。
こちらにも白散り斑が全面に入っています。



そんな仔の柄が本葉で薄ぼんやりした紺覆輪になるとは不思議といえば不思議です。
それでも建国ですから変異しやすい柄ということで
何度もトライすればたまには変わった柄も出てくれるでしょう。

それにしても我が家では作の掛からない品種ですが
今年は新根がいっぱい出てまだ伸びているのもあります。
もしかすれば今まで夏の暑さに弱くて傷んだのかもしれません。
今回はそれも改善されましたし今後に期待しましょう。



あれから1ヵ月。
しばらくごちゃごちゃした葉のままでしたので
てっきり仔かと思っていたのですが

いきなり花茎が勢い良く伸び出しました。

花芽か葉芽かでせめぎ合っていたのでしょうが
どうやら花芽のほうに軍配が上がってしまったようです。
花成ホルモンの分泌も通常ではないのか包が花弁化したりして変な形の花が咲きそう。
それにしても期待が大きかっただけに残念です。



ただ、救いはこの天葉。
このタイプの中透けだと真鶴を連想して
だんだん派手になるのかなと思ってしまいますが
さらに紺地が太く出てくれました。
柄的にはしばらく安泰かも。

花を摘んじゃうとまた次の花芽が出来そうですから
とりあえずは咲かせてみて木勢をちょっと鈍らせ
来年に備えましょう。



一方、神威のほうは超順調。



仔は急速に葉を伸ばしています。

柄のほうもそこはかとなく感じられ
本葉が何枚か出たら親木程度の柄にはなってくれそう。
この2鉢だけでもうまくいったりいかなかったり、目まぐるしいことです。




あれから1ヵ月。
付けが見えたら次は天葉ですが

ようやくこれぐらい伸びてくれました。

しかし春とは違い深まりつつある秋に向かって徐々にスピードダウンしているようです。
やはり至楽ということで年に葉繰り2枚は無理っぽく
1枚半がせいぜいといったところ。


仔は付けが見えてからしばらく成長が止まったかに見えましたが
ここ数日でまたやる気を出したようです。


この仔は紺地も多いことですし来年は親木サイズにまでなってくれるでしょう。

それにしても綺麗な木です。
今年一番、手に取って見る回数の多かった木です。
もうそれだけで元は引けたかも。

帝
2017年09月26日 | 帝



親木は年を重ねるごとに柄は安定してきているようです。
仔にも柄はあるもののこれからといったところ。



こちらは一本の仔の柄が上で逃げちゃいました。

まあ、普通はこんなものです。



こちらは4本ともに柄が継続中。
筋は良さそうです。
といっても元は同じ木からの株分けなんですが。

何れも葉幅引き雄大な姿にはなっているのですが若干締まりが足りないような・・・。
紫外線の当たらない蘭舎内で2作もするとこうなるのでしょうね。
葉幅はこのままでもう少しキュッと締まり
下葉にアントシアニンを散らした野趣豊かな姿を見てみたいものです。

今日からしばらく夜0時の投稿に切り替えてみますのでよろしく~




あれから2ヵ月。
葉数が少なく頼りなげな姿でしたが
1枚増えただけでちょっと様になってきました。



気になっている腰斑のような柄も健在。


ルビー根が出ないのは後冴え柄の為かと思っていましたが
天葉でもそれなりに柄は判別できます。

特にこの部分は紺覆輪中透け柄。
それで腰斑が出るのでしょう。

上でこんな柄に変わりつつあるのだとすれば
根のほうの変化も期待できそうです。




それにこのアタリ。

獅子葉のようなゴチャゴチャッとした稚葉でしたが
天葉が仲良く2枚、ダブルで出てきました。

画像では分かり難いのですが柄もありそう。
滅多にないことで行く末が楽しみです。



あれから5ヵ月。
白縞の出た木を植え替えてみました。
やっぱり気になるものですからつい、いじってみたくなります。



仔は順調に生育しあと一作くらいで独り立ちできるかも。
とはいえルビー根+時折黄虎+白縞の三芸品ですから
まずは枯らさないようしばらくこのまま様子を見ることになるのでしょう。




柄も最上ですが天葉付近を見るとどうも後冴え気味のようです。


こちらの葉の下は良い柄ですからこれもそうなってくれそう。
まさかこんな柄が出てるとは思わなかったこともありますが
後冴えのため大きくなってからじゃないと見つけられなかったのでしょう。


こんなびっくり縞から良く出てくれたものですが

更に良く見ると仔が出た下の葉にもかすかに一条の白縞が・・・。

こんな縞でも最上柄を生む原動力となりますから粗末にはできないとしたものです。
そういえば黒牡丹なんかでも背筋に白縞の入ることが時々ありますが
こっちは後暗みですからそのうちどこに入っていたのか忘れてしまいます。
人手に渡って良い柄が出た~なんて報告をいただくのはこのパターンなのでしょうね。




あれから1年半。
初めて入手したのが35年ほど前ですから作歴は長いのですが
いまだにどう良いのかしたら戸惑いの多い品種です。

葉幅引き締まった姿が好きなものですからそっちの方向で調整していますが
そうするとなかなか仔出しには恵まれなくなります。

この木は珍しく惚れ惚れするような上柄が続いますから
増やすほうに方向転換したいのですがなかなかそこまで器用じゃないですし~。




こちらは上柄に見えていたのですがいつのまにかこんな感じに。


この仔は元々派手だったのですが

これも派手気味になってしまいました。


親木も後冴え柄ですからまだ判然とはしませんが
どうやら源平柄気味になってしまった模様です。
しかし上柄維持の難しい品種ですから普通はこんなものでしょう。




これは入手してから2作ぐらいしたもの。
苗木風のヒョロい木は好みじゃないのですが
あまり花芽を付けずに仔が良く出るのはこの時期なのでしょう。




幸い、どの木にも柄がある運の良さそうな株ですから
小割りして増殖に努めようかなんて考えています。
結局は鑑賞用と増殖用のツートラックでいけば上柄も維持できるし
飽きずに長く楽しめることでしょう・・という結論に達しました。
目出度し芽出度し。




あれから1年。
普通の朝鮮鉄はいくら葉繰りしていくら仔が出るかなんて意識したことなかったのですが
現金なもので縞が入っているとじっくり見てみたくなります。
そしたら驚くことに一作で葉繰りはたったの2枚。

まあ、棚慣らし中ですし縞が入って若干弱体化してますからこんなものなのでしょう。

その割に仔のほうは派手にもかかわらず健闘しています。
それに画像を見ていて気が付きましたが反対側にもアタリが付いています。
来年以降のさらなる健闘を祈りましょう。



あれから半年。
根がたくさん出て元気ですしもう少し大きくなると思ったのですが
どうやらこの辺が大きさの限界のようです。

天葉は出始め、時折引っ掛かりそうになるのですが
今回はスムーズに伸び出しています。

ところで今までは下の葉元から順番に仔が出ていたのですが
上のほうになにやら怪しげなアタリが二つも付きました。
もしかしたら花芽かも。

変わった花が咲きそうですからちょっと楽しみです。



あれから1作。
今まで生育が渋り気味でしたが
ここにきてようやくご機嫌になってくれたようです。


今年出た仔も無事、潰れずに育ってくれました。

元が繋がっている株立ちだとお互い協力しあって養分をため込むのか
仔出しも良好のはず・・・なので来年以降に期待です。
ところで素立ち歴の長い木は木の途中から根の出ることが良くあります。
根が2、3本出たらその根下から切り離せば上のほうは若返って仔が出るし
下のほうは生長点が無くなったということで葉元から仔が出る。
・・・という我ながらナイスなアイデアを思い付きました。



それでさっそく実行してみたのが2年前です。



結果は無残。



1本じゃ偶然に左右されるかもと4本もやってみたのですが
どれからも仔が吹かずこのまま朽ち果てるのでしょう。
蜘蛛の巣まで張っているところに侘しさを感じます。

一方、切り離した上のほうはというとこれが若返りどころか作落ち。
我ながらおバカなことを実験してみたものです。

やはり萩宝扇の素立ちは葉重ねを増やしつつ大きくして力を貯めさせ
上のほうから出るアタリを待つのがベストな増やし方なのでしょう。
急がば回れということですね。




あれから2年。
こちらも昨日の国輝殿と同様、下葉がバラバラッと落ちちゃいました。
昨年夏の猛暑の際、今年のような対策をしなかったのが原因なのでしょう。

それでも葉数が少なくなってすっきりしたような気もしますし

何より仔が完全覆輪になってくれて嬉しい限り。

親木の源平覆輪のような柄は10年前からそのままですから
よくぞこんな仔が出てくれるものと感心しきりです。
喜び過ぎのような気もしますが他にも派手な覆輪がいくつもありますから
そっちにもこのパターンが乗り移ってくれればとか下心があったりします。



あれから2作。
いきなり下葉がバラバラバラッと落ちてこんな姿になっちゃいました。

葉緑素が足りないと軸も太らないのか
水遣りの水圧でもぐらぐらしますので竹串で支えています。


一応、紺中通しはしっかりしていますから枯れることはないと思いますが
これでは増えることもなさそう。

自分的には再入手も難しい貴重な品種と思っていますから
何とか維持していきたいものです。



あれから一作。
月笙というかこれは金牡丹ですが
ぼろかった下葉はどんどん枯れ落ち、今はこんなお姿に・・・。


墨が強いと成長が遅くなるものですが
この木は片側だけ強く墨が出ていて
成長速度の違いかそっちに引っ張られています。

墨の無い仔はスクスク成長。
葉が傷んでなければ全部がこんな風に育っていたのでしょう。




タイトル通りの月笙はずいぶん小さくなりましたが
もう落ちる下葉もなくなりました。
仔がたくさん出てここからがお楽しみの始まりです。


あとはこんな木が5本残っています。
何とか枯れずに育っていますが一歩間違えれば全滅・・・。
やっぱり最初からしっかりした木を求めたほうがお得かも。


あれから2年。
外棚作りと違って柄に冴えというか切れは弱まりますが
それとは引き換えに葉繰りと仔出しが良くなり姿も大きめに育つようです。




柄の冴えがイマイチとはいえほんわかした雰囲気は十分に残っていて
ふんわり目に育った葉姿ともマッチしています。
ただ片側ばかりに出る仔はいかがなものかといった感じで
また仔を外して作り直しです。