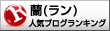羆覆輪が富貴殿のような深覆輪に変化したものが大冠です。
三年前の福岡の大会で展示をしましたが
その後直ぐに親木の天葉が芯止まり。
秋田から九州まで持ち歩くと調子を崩すことがあるものですね。
健全な頃の姿が懐かしくも恨めしい・・・。
仔が出ても派手な柄が多くウチの棚ではなかなか育ちませんです。
(この一鉢も大冠から出たハデ仔ですが結局枯れました。)
東京ドームや大会での展示は見るほうは気楽なものですが
出品される側はそれなりにリスクを背負っているものと
頭が下がる思いです。
話は変わりますが蘭の葉は三層構造になっていて
覆輪や中透けなどは周縁キメラ斑と言うのだそうです。
それぞれの層で斑が入る、入らない2通りだとすれば
2×2×2=8で8通りのパターンが考えられ
種類でいえば覆輪、大覆輪、中斑、中透け、三光中斑、逆三光中斑?
ユウレイ、青ということになります。
羆、建国殿で面白いのは
この一族で周縁キメラ斑すべてのパターンを
網羅していることです。
品種で言うと覆輪は羆覆輪、大覆輪は今回の大冠、
中斑は長寿楽、中透けは羆、三光中斑は八千代、
逆三光中斑で固定した木はありませんが
派手な羆覆輪の一部の葉に見受けられます。
また、ユウレイは新月殿、青は建国殿などの柄抜けです。
これだけでもすごいのに、それにプラスして
一枚の葉に暗む黄縞、暗まない黄縞、暗む白縞を混在させています。
各層に柄が有るか無いかだけでも8種類なのに
斑の色も何種類かあるとなると複雑さは加速度的ですね。
またそれに区分キメラ斑という縞が加わりますし
一部の柄だけ目立つ木が多いので違う雰囲気に見え
なかなか整理が出来ていない感じもします。
実際、大冠と白深覆輪では同じパターンの柄でも
がらりと雰囲気が変わります。
(昔、見たことがある白柄の羆というのをもう一度見てみたいものです)
まだわからないことはたくさんありますが
墨を流すことと泥が軸元に濃く集まって
付けから先へは散らないという特徴もあって
品種自体の見分けは意外に簡単です。
知れば知るほどすごすぎる一族ではあります。