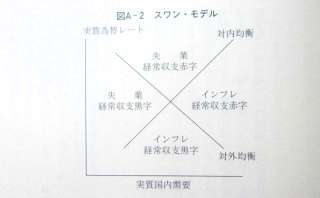久しぶりに、ウィリアム・シェイクスピアの「十二夜」を観に日生劇場に出かけた。
RSCなど英国のシェイクスピア劇団が来日しなくなるなど良質なシェイクスピア劇を、蜷川の舞台以外では、観られなくなった・・・尤も、これは、私の認識不足で、上演されているのかも知れない・・・ので、RSC(ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー)のディレクターでもあるジョン・ケアードの演出と言うことで、大いに期待したのである。
それに、美術・衣裳は、ヨハン・エンゲルス、音楽・編曲は、ジョン・キャメロンと言うのであるから、役者などが日本人だが、英国版の上演だと言うことであろう。

私の場合、シェイクスピアの舞台は、イギリスでの5年間で、殆ど主に、ストラトフォード・アポン・エイヴォンとロンドンでRSCの舞台に通い詰めながら、その楽しさを味わって来たし、蜷川の舞台も「マクベス」や「テンペスト」なども、ロンドンで観てファンになった。
今回の舞台は、 松岡和子の翻訳だが、当時は、小田島雄志訳のシェイクスピア全集にお世話になった。
ジョン・ケアード(John Caird)については、以前は、演出家に関しては殆ど意識をしていなかったのだが、彼の演出記録をチェックすると、私はイギリスで、彼の演出によるLes Misérables、A Midsummer Night's Dream、As You Like It、The Beggar's Operaを観ていることになる。
殆ど、記憶に残っていないのだが、乞食オペラ(The Beggar's Opera)は、しっかりしたオペラの舞台を観ているような感じがした気がしている。
この舞台やレ・ミゼラブルは、日本でも彼の演出で上演されたようだが、私は観ていない。
双子の兄妹セバスチャンとヴァイオラ(音月桂・二役)の乗る船が難破して、偶然にも、夫々離れてイリリアの岸にたどり着く。兄が溺れたと絶望したヴァイオラは、兄の服を着て男装してシザーリオと名乗り、オーシーノ公爵(小西遼生)に、小姓として仕える。
オーシーノは、父と兄の喪に服している伯爵家の美しきオリヴィア(中嶋朋子)に恋焦がれており、拒み続けるオリヴィアへの恋のメッセンジャーとして、シザーリオを送り込む。
ところが、オーシーノに恋してしまったヴァイオラ(シザーリオ)は、切ない気持ちを抱きながらオリヴィアの元へ向かうのだが、逆に、オリヴィアの方が、シザーリオを本当の男性だと思って恋してしまう。
一方、ヴァイオラの双子の兄セバスチャンが、同じイリリアに辿り着き、そこで偶然に出会ったオリヴィアにシザーリオと間違って恋を迫られて、何が何だか分からないままに、訪れた幸運を掴もうと、牧師の前で結婚式を挙げてしまう。
全く良く似た兄妹セバスチャンとヴァイオラの区別は服装だけと言う状態であるから、兄弟を取り違えた悲喜劇が展開されるのだが、結局はハッピーエンドで、二組の結婚が成立する。
この舞台では、同じ服装をしているシザーリオとセバスチャンの区別は、腰のバンドとタスキ掛けの飾りの色で区別して、前者は黒、後者は赤にして、音月桂は、微妙に声の表現を変えて演じている。
ところが、ラストの大詰めの舞台で、ヴァイオラとセバスチャンが同時に登場する、せざるを得ないシーンがあるのだが、蜷川歌舞伎では、菊之助に良く似たマスクをつけた別人を登場させていたが、この舞台では、良く似た別の女優を起用して、バンドとタスキを外して、どちらがどっちか分からないようにして、台詞の大半を音月桂に振って出来るだけ正面を向かせて演じていた。
この舞台では、二役が出来ても、「間違いの喜劇」では、二組の双子の兄弟は、頻繁に登場するので、良く似た役者を登場させざるを得ないのである。
このストーリーに、サブ・ストーリーとして、オリヴィアに恋する執事マルヴォーリオ(橋本さとし)が、日頃威張り散らされている腹いせに、居候の伯父サー・トービー(壤晴彦)とバカだが金持ちのサー・アンドルー(石川禅)と道化のフェステ(成河)たちに、侍女マライア(西牟田恵)がオリヴィアに似せて書いた偽ラブレターに仕掛けられた悪戯で、散々に苛め抜かれてコケにされると言う物語が加わっており、益々面白いドタバタ喜劇が展開される。
この「十二夜」を観ていると、シェイクスピアの戯曲のテーマなりキャラクターが、次々と綾織のように紡ぎだされているのが分かって面白い。
「間違いの喜劇」で、双子の兄弟と双子の従僕が間違われて展開される喜劇、そして、兄弟ではないが、良く似ている二組の恋人たちが、妖精パックの惚れ薬に翻弄されて繰り広げる互いに入れ替わる「真夏の夜の夢」の話、
また、男装して恋人のために活躍する「ヴェニスの商人」のポーシャ、「お気に召すまま」のロザリンドも男装して事態を縺れさせながら結婚すると言うハッピーエンド、
酒飲みのトービーは、「ヘンリー4世」や「ウィンザーの陽気な女房たち」のファルスタッフそっくりだし、セバスチャンを助けた友のアントーニオ(山口馬木也)などは「ヴェニスの商人」のアントーニオとよく似ており、恋の仲立ちになると騙されて貢がせられる金づるのアンドルーなどは「オセロ―」のイアーゴーに騙されるロダリーゴーと生き写し、
道化の気鋭妙洒脱な可笑しみ滑稽さアイロニー・・・、いくらでも、シェイクスピア劇のキャラクターを思い出すことが出来る。
この物語の材源は、「アポロニウスとヘラ」だと言われているが、
あのロダンが、巨大な「地獄の門」に、「考える人」など、それまでに制作した多くの彫刻作品を集めて集大成したような面白さが、この戯曲にはあって興味深い。
さて、この「十二夜」だが、強烈な印象に残っているのは、蜷川幸雄が演出した歌舞伎の「十二夜」の舞台で、シェイクスピアが歌舞伎バージョンに生まれ変わると、こんなに新鮮な舞台になるのかと言う驚きを感じた。
「十二夜」の舞台は、これまでに、RSCなど何回かは観ている勘定だが、私など、観てはすぐに忘れてしまうので、記憶は残っておらず、観た舞台でも、ケネス・ブラナーの「ハムレット」など僅かな舞台の断面やシーンなどしか残っておらず、惜しい限りである。
今回の舞台は、日本語で、日本の役者が演じているので、非常に分かり易くて、舞台も綺麗であるし面白い。
ただ、ケアードがどう思っているのかは分からないが、やはり、シェイクスピア劇を殆どキャリアの中心においてシェイクスピアどっぷりの芸術環境にあって日夜切磋琢磨している英国人役者の演じるRSCの舞台とは、全くと言っても良い程、雰囲気が違う。
娯楽作品としては、素晴らしく楽しい舞台だし、水準の高い芝居だと思うが、シェイクスピアの舞台としては、笑いにしろ、恋の交感の表現にしろ、どこか、お芝居をしていると言う感じで、滲み出てくる深刻さ真剣さなり奥深さなど、上質なシェイクスピア戯曲の味が出ていない、シェイクスピア劇を鑑賞するつもりで出かけたら、一寸肩透かしを食った、と言う感じである。
一つは、音月桂が、トークセッションで言っていたが、ケアードが、何度もシェイクスピアについて語っていて勉強になったと言うようなニャンスのことを語っていたが、まず、若い役者たちの間には、シェイクスピア劇とは何なのか、シェイクスピアそのものの理解や経験が不足しているために、シェイクスピア戯曲を演じることが如何に特別かと言う認識がないので、普通の、喜劇と捻った悲劇との綯い交ぜの悲喜劇を、真剣ながらも、普通の芝居と同じように演じていると言うことではなかろうか。
尤も、私自身は、宝塚のトップスターとして男役を演じて高みに上り詰めた音月桂の、いわば、女のヴァイオラ(変装して男のシザーリオ)、そして、男のセバスチャンを演じ分ける舞台を観たくて行ったようなものであるから、十分に愉しませて貰って満足している。
ウイキペディアでは、”現代的で華のある容姿に歌、ダンス、芝居と3拍子揃った実力派雪組トップスター”と言うことだが、
歌は、道化との二重唱で、恋心を歌う素晴らしい歌声を聞いたし、ダンスは見られなかったが、華麗(?)なサー・アンドルーとの決闘シーンを見せて貰ったし、宝塚アクセント濃厚な台詞回しの、本職の男役と本来の女を器用に演じ分ける素晴らしい芝居を見せて貰った。

「北の国から」から始まって、テレビや映画で良く観ている人気女優中嶋朋子は、勿論、二枚目俳優の小西遼生、一歩群を抜いている芸達者な橋本さとし、年季の入ったベテランの壤晴彦と青山達三、ミュージカルの舞台で経験の深い石川禅、才気煥発な演技で楽しませる西牟田恵、颯爽とした男振りを披露する山口馬木也と宮川浩に加えて、この舞台では極めて重要な歌を美声で歌いながら闊達な道化で狂言回しを演じる成河など、素晴らしい脇役陣が、存分に楽しませてくれる。
舞台は、どんどん時間や空間が飛んで行くシェイクスピアの舞台だが、固定してあるのは、舞台袖の左手に女性の石像、右手に庭園の塀と木戸口、そして、舞台中央後方に鉄製の立派な門だけで、
その間の舞台中央の回り舞台上に左右3列に設置された円弧の壁面を、上手く回して移動させながら、舞台照明を変えたり小道具をアレンジしたりして、瞬時に舞台展開を図るなど、極めてスムーズで気持ちが良い。
私の知る限り、RSCの舞台と較べれば、かなり、立派な舞台セットである。
ヴァイオリンとヴィオラとチェロの3重奏と道化などが歌うジョン・キャメロンの音楽が美しく舞台を包み込んで爽やかである。
老年大半の能・狂言や歌舞伎・文楽と違って、蜷川シェイクスピアもそうだが、圧倒的に若い観客が多くて、この日の観客の80%以上は若い女性で、とにかく、客の殆どは女性で、私のように年かさの男性客は、天然記念物的存在であった。