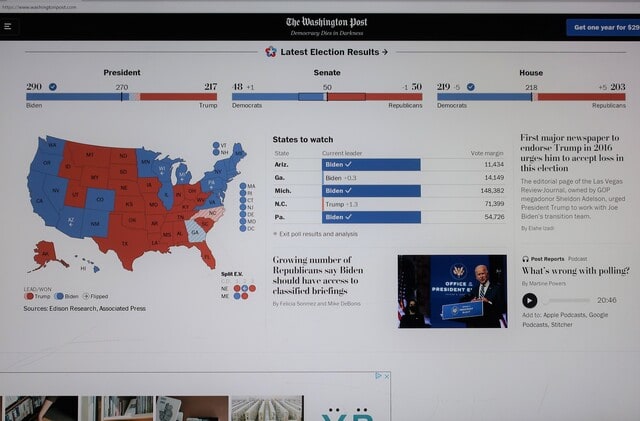ロンドンのハムステッド・ヒース公園の北端に位置するカントリー・ハウスが「ケンウッド・ハウス Kenwood House」で、フェルメールの『ギターを弾く女』、レンブラント晩年の『自画像』などの名画を所蔵するこじんまりした美術館があるのだが、敷地内の広大な庭園の片隅の大きな池の側に、野外劇場が設営されていて、野外コンサートが開催されていた。
毎年夏、数千人にもおよぶ客が音楽とピクニック、その後の花火を楽しんできたのだが、地域住民からの、夜間の騒音や放置されるゴミなどに関する苦情のために、2007年2月、イングリッシュ・ヘリテッジは、コンサートを中止して、その後場所を移して小規模で続けられているという。
私の記録は、1990年前後の思い出なので、まだ、最盛期の頃で、毎年夏、ロイヤル・オペラの野外公演を楽しみに通っていた。公演が野外と言うだけで、上演中の演目で同じ歌手の出演で、全く手抜きはない。
広大な野外公演であるから、数万枚という結構な数のチケットが発売されていた筈なのだが、即完売でその取得は至難の業であり、公演当日には、公演外の芝生上にもびっしりと観客が犇めいていた。
半円形のお椀を伏せたようなステージを前にして大きな池があって、その池畔から椅子席が並び、その後ろの小高くなって傾斜のある芝生の部分がグラス席で地面に自由に座る自由席である。
椅子席が30ポンド、グラス席が15ポンドで、劇場よりはかなり安く、全英からファンが集まる。隣席の夫人はエジンバラから来たと言っていた。
当日は、少し早く出かけても、広大な駐車場は満杯で、近くの住宅街の路上に空間を探して駐車するのだが、会場までは結構遠くなる。
この年の演目は、「トスカ」。
プラシッド・ドミンゴのカバラドッシ、マリア・ユーイングのトスカ、ユスチアス・ディアスのスカラピア。
ドミンゴはじめ男性歌手はタキシード姿、ユーイングは赤っぽいロングドレスに黒のコート。
5月から、オペラハウスでは、「トスカ」を上演していたが、ドミンゴ=ユーイング組は、限定されたスポンサー対象公演でチケットが取れず、私が観たのは、ヒルデガルト・ベーレンスのトスカ、ネイル・シコフのカラバドッシ、サミエル・レイミーのスカラピアであった。
この日のユーイングは、心なしか声が伸びず、私には、べーレンスの方が良かった。
ユーイングには、色々な思い出があるのだが、「サロメ」の、第4場の「サロメの踊り(7つのヴェールの踊り)」で全裸シーンを披露したのが印象に残っている。肉襦袢のギネス・ジョーンズとは違った強烈なサロメであった。
音はマイクを使っているので、生演奏ではあるが、大きなステレオを聴いている感じである。
むかし、ギリシャのエピダウルスの野外劇場で、観光客の一人が一番底の舞台で、カンツォーネを歌い出したのを、一番上の客席で聞いて、良く伸びた美しい声で感動したのだが、草深い公園では、マイクなしでは無理なのであろう。
野外ステージなので、観客は思い思いのビデオやカメラで写真を撮っており、私も、F2.8,80-200ミリの望遠レンズで、ドミンゴとユーイングを撮ったが、一番前の方の席ながら、遠い上に、デジタルではなかったので、豆粒のようであった。(写真は残っているはずだが、総て倉庫に収納で取り出せず、口絵者貧もウィキペディアから借用)
余談だが、舞台の合唱団の一人が、後ろを振り向いたドミンゴをフラッシュも鮮やかにスナップショットしていたが、後で、お目玉を食ったであろうか。
広大な緑地と言っても大都会の真ん中からほど近く、ヒースロー空港にも近いので、空路を逸れた飛行機の爆音が、名テナーのアリアの伴奏をする。
ロンドンの夏の夜は涼しくて虫もおらず、極めて快適である。
日が傾き始めると日暮れは早く、ドミンゴが、第3幕のアリア「星は きらめき」を歌う頃には、もう、とっぷりと日は暮れて、オペラの最後の大詰め、一瞬時が止まったかの錯覚を覚えて、暗くて陰湿なサンタンジェロ城の牢獄で死に直面したカラバドッシの心境になった全聴衆・・・水を打ったように静まりかえる。
絶望したトスカが城壁から身を翻して消えて行く断末魔のラストシーンは、まさに、オペラ全巻の終わり。
私には、劇場で観るシーンとは違って、漆黒にくすんだローマのサンタンジェロ城の姿が脳裏をかすめて、このシーンは、このような野外劇場の独壇場ではないかと感じた。
肝心のトスカを誰が歌ったのか、記憶にないのだが、同じロイヤル・オペラで、ルチアーノ・パバロッティのカラバドッシが、サンタンジェロ城の牢獄の城壁に身を預けて、涙を浮かべながら、「星は きらめき」を歌っていたのを鮮明に覚えている。
さて、一番最初に、このケンウッドで聴いたロイヤル・オペラは、「パリアッチ」と「カバレリァ・ルスチカーナ」。
同じ公演をロイヤル・オペラ・ハウスでも観たので二回だが、ピエロ・カップチャルリとエレーナ・オブラツオバの舞台に接して感激であった。
ずっと後になって、このオペラ・ハウスで、ドミンゴ指揮の「パリアッチ」を観たのだが、この時は、この演目だけの舞台であった。
このオペラを最初に観たのは、ニューヨークのMETで、ネッダは、美人の誉れ高いアンア・モッフォ、サントッツアはグレイス・バンプリーで素晴らしい舞台であった。
ところで、芝生のグラス席でも、中には、寝そべって天を仰ぎながら聴いている客もいるにはいるのだが、しかし、立錐の余地のないほどの混みよう。
野外劇場の外には、大きな緑地公園が広がっていて、その境界には金網が張ってあって生け垣が隔てているので、舞台の歌手の姿などは全く見えないのだが、客席の延長のように、全くグラス席と同じピクニックスタイルの聴衆が、びっしりと席を占めて聴いている。
この日だけは、閑静なハムステッドヒースの高級住宅街は人と車でごった返し、遠くからやってきた人は、深夜を徹して故郷へ帰るのだという。
毎年夏、数千人にもおよぶ客が音楽とピクニック、その後の花火を楽しんできたのだが、地域住民からの、夜間の騒音や放置されるゴミなどに関する苦情のために、2007年2月、イングリッシュ・ヘリテッジは、コンサートを中止して、その後場所を移して小規模で続けられているという。
私の記録は、1990年前後の思い出なので、まだ、最盛期の頃で、毎年夏、ロイヤル・オペラの野外公演を楽しみに通っていた。公演が野外と言うだけで、上演中の演目で同じ歌手の出演で、全く手抜きはない。
広大な野外公演であるから、数万枚という結構な数のチケットが発売されていた筈なのだが、即完売でその取得は至難の業であり、公演当日には、公演外の芝生上にもびっしりと観客が犇めいていた。
半円形のお椀を伏せたようなステージを前にして大きな池があって、その池畔から椅子席が並び、その後ろの小高くなって傾斜のある芝生の部分がグラス席で地面に自由に座る自由席である。
椅子席が30ポンド、グラス席が15ポンドで、劇場よりはかなり安く、全英からファンが集まる。隣席の夫人はエジンバラから来たと言っていた。
当日は、少し早く出かけても、広大な駐車場は満杯で、近くの住宅街の路上に空間を探して駐車するのだが、会場までは結構遠くなる。
この年の演目は、「トスカ」。
プラシッド・ドミンゴのカバラドッシ、マリア・ユーイングのトスカ、ユスチアス・ディアスのスカラピア。
ドミンゴはじめ男性歌手はタキシード姿、ユーイングは赤っぽいロングドレスに黒のコート。
5月から、オペラハウスでは、「トスカ」を上演していたが、ドミンゴ=ユーイング組は、限定されたスポンサー対象公演でチケットが取れず、私が観たのは、ヒルデガルト・ベーレンスのトスカ、ネイル・シコフのカラバドッシ、サミエル・レイミーのスカラピアであった。
この日のユーイングは、心なしか声が伸びず、私には、べーレンスの方が良かった。
ユーイングには、色々な思い出があるのだが、「サロメ」の、第4場の「サロメの踊り(7つのヴェールの踊り)」で全裸シーンを披露したのが印象に残っている。肉襦袢のギネス・ジョーンズとは違った強烈なサロメであった。
音はマイクを使っているので、生演奏ではあるが、大きなステレオを聴いている感じである。
むかし、ギリシャのエピダウルスの野外劇場で、観光客の一人が一番底の舞台で、カンツォーネを歌い出したのを、一番上の客席で聞いて、良く伸びた美しい声で感動したのだが、草深い公園では、マイクなしでは無理なのであろう。
野外ステージなので、観客は思い思いのビデオやカメラで写真を撮っており、私も、F2.8,80-200ミリの望遠レンズで、ドミンゴとユーイングを撮ったが、一番前の方の席ながら、遠い上に、デジタルではなかったので、豆粒のようであった。(写真は残っているはずだが、総て倉庫に収納で取り出せず、口絵者貧もウィキペディアから借用)
余談だが、舞台の合唱団の一人が、後ろを振り向いたドミンゴをフラッシュも鮮やかにスナップショットしていたが、後で、お目玉を食ったであろうか。
広大な緑地と言っても大都会の真ん中からほど近く、ヒースロー空港にも近いので、空路を逸れた飛行機の爆音が、名テナーのアリアの伴奏をする。
ロンドンの夏の夜は涼しくて虫もおらず、極めて快適である。
日が傾き始めると日暮れは早く、ドミンゴが、第3幕のアリア「星は きらめき」を歌う頃には、もう、とっぷりと日は暮れて、オペラの最後の大詰め、一瞬時が止まったかの錯覚を覚えて、暗くて陰湿なサンタンジェロ城の牢獄で死に直面したカラバドッシの心境になった全聴衆・・・水を打ったように静まりかえる。
絶望したトスカが城壁から身を翻して消えて行く断末魔のラストシーンは、まさに、オペラ全巻の終わり。
私には、劇場で観るシーンとは違って、漆黒にくすんだローマのサンタンジェロ城の姿が脳裏をかすめて、このシーンは、このような野外劇場の独壇場ではないかと感じた。
肝心のトスカを誰が歌ったのか、記憶にないのだが、同じロイヤル・オペラで、ルチアーノ・パバロッティのカラバドッシが、サンタンジェロ城の牢獄の城壁に身を預けて、涙を浮かべながら、「星は きらめき」を歌っていたのを鮮明に覚えている。
さて、一番最初に、このケンウッドで聴いたロイヤル・オペラは、「パリアッチ」と「カバレリァ・ルスチカーナ」。
同じ公演をロイヤル・オペラ・ハウスでも観たので二回だが、ピエロ・カップチャルリとエレーナ・オブラツオバの舞台に接して感激であった。
ずっと後になって、このオペラ・ハウスで、ドミンゴ指揮の「パリアッチ」を観たのだが、この時は、この演目だけの舞台であった。
このオペラを最初に観たのは、ニューヨークのMETで、ネッダは、美人の誉れ高いアンア・モッフォ、サントッツアはグレイス・バンプリーで素晴らしい舞台であった。
ところで、芝生のグラス席でも、中には、寝そべって天を仰ぎながら聴いている客もいるにはいるのだが、しかし、立錐の余地のないほどの混みよう。
野外劇場の外には、大きな緑地公園が広がっていて、その境界には金網が張ってあって生け垣が隔てているので、舞台の歌手の姿などは全く見えないのだが、客席の延長のように、全くグラス席と同じピクニックスタイルの聴衆が、びっしりと席を占めて聴いている。
この日だけは、閑静なハムステッドヒースの高級住宅街は人と車でごった返し、遠くからやってきた人は、深夜を徹して故郷へ帰るのだという。