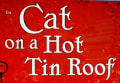日刊工業新聞が、創刊95周年記念として、日本産業人クラブ連合会と共催で、標記シンポジウムを開催したので参加した。
元気印の今を時めく中小企業のトップたちが立って、その企業経営の底力の秘密を開陳すると言う非常に興味深い会合となり、その後、懇親会に入り、中小企業の人々との交わりがあった。
これらの優良中小企業の成功話を聞いていて、悉く共通しているのは、ブルーオーシャン市場の開拓に成功して、好業績を上げ続けていると言うことであった。
このブログでもずっと書き続けて来た私の思いでもあるので、ここで、これらの企業のケースを借りて再説してみたいと思う。
ブルー・オーシャンとは、W・チャン・キムとレネ・モボルニュが、「ブルー・オーシャン戦略」で展開した理論で、共通して優良企業が好業績を持続している要因は、ブルー・オーシャン(新しい市場)の開拓とその成功による発展成長にあることを発見したことから生まれた理論である。
好業績やその持続を実現させているのは、産業や企業に内在する要因などではなくて、新しい市場空間を切り開き、ブルー・オーシャンの開拓に成功し、需要を創造し大きく押し上げたその企業の戦略にあったのである。
ブルー・オーシャン戦略とは、コスト競争や従来型の差別化戦略で、ライバル企業との競争に打ち勝つという手法ではなく、競争のない未知の市場空間を開拓することによって、買い手や自社にとっての価値を大幅に高めるとともに、競争を無意味にしてしまうバリュー・イノベーションにあると言うことで、このブルー・オーシャン市場では、競争を前提とした戦略論の常識であるコスト競争で勝つか差別化で勝つかと言う「価値とコストはトレードオフ」と言う関係を覆し、差別化と低コストを同時に実現することによる成長発展である。
したがって、このシンポジウムに登壇した中小企業は、悉く、その分野でのオンリー・ワン企業で、自分の道を自分自身で切り開いてわが道を行くことによって活路を見出しているのであるから、モデルもなければ、競争相手さえないと言うパイオニアである。
しかし、市場に恵まれて技術などの優位だけに胡坐をかいている良くある創業ベンチャーのような脆弱な企業ではなく、経営戦略や企業体質・システムなどがしっかりしていて、経営そのものに問題のない優秀な企業家によって経営されていると言うことである。
旺盛なチャレンジ精神を持続しながら、絶えず時代の潮流に敏感に対応した経営の舵を取り、街の中小企業から、宇宙産業や原子力産業などの高度なハイテクの世界までにも製品やサービスを提供するのであるから、日本の中小企業の底力の凄さには目を見張るものがある。
基調講演に立ったのは、合成樹脂製品の金型製造から事業を展開した大成プラス(株)の成冨正徳社長で、合成樹脂をメインにしたデザイン・設計・金型製造販売・輸出入およびノウハウ・技術の提供・ライセンス供与を行いながら、接合をコンセプトにしたオリジナル技術をベースに設備なき製造業を目指しており、日本のトップ自動車メーカーなどへハイテク部品を提供するのは勿論、独自に開発した技術は特許で300件を超え、海外にも進出して、既に6件のライセンスパートナーを持つと言う。
他所で出来ないような相談ばかり来るのだが、顧客と対面するのではなく、横に座って、客と同じ目線に立って仲間意識で問題点を検討し、失敗を繰り返しながら解決策を炙り出しソリューションを導き出すのだと言う。
単なる下請けではなく、ものの作り方を一緒に考えて解決するもの作りのパートナーだと言う意気込みである。
この何か役に立つことがないかと待ち構えていて、誰も何処も解決できないような要求が来れば、出来るか出来ないか考える前に仕事を引き受けて挑戦すると言うもの作り精神の横溢した技術者・職人魂は、どの成功中小企業にもある共通した特徴である。
面白いのは、ラシャ問屋からスタートしたヒーティング技術ノウハウでは断トツの坂口電熱(株)で、NOと言わない技術開発に徹した対面R&D開発によるオーダーメイド戦略を社是としており、既に、世に送り出した製品は300万点を超えると言うのだから恐れ入る。
ヒーターと言うヒーターは言うに及ばず、温度センサーやコントローラー、絶縁材料まで「加熱」に関するアイテムは常に9000アイテムを取り揃えていると言うことだが、
この会社は、年商40億程度の中小企業ながら、NPOを設立して地域社会への貢献をしているのみならず、海外からの私費留学生への奨学金を支援する財団を設立して延べ200人に及ぶと言う「社業を通してご恩返しを」と言う企業理念を推し進めていると言う見上げたエクセレント・カンパニーである。
この会社の蜂谷真弓社長は、非常にチャーミングな若いレディで、滔々と会社の未来像を熱っぽく語っており、日本の新しい会社像が見えてくるようで頼もしい。
もう一つの分かり易いケースのブルー・オーシャンは、臼井努社長が語った東西テクノス(株)のビジネス・モデルで、メーカーがサポートを打ち切ってしまってサービス切れとなった製品の修理・保守・メインテナンス一切を引き受けると言う戦略で、計測機器の修理から始まって、医療、情報、通信分野等の各種機器、システムを何処のメーカー製品でもワンストップでサービス対応すると言うマルチベンダー・サービスで、仕事は、原子力発電所にまで及んでいると言う。
産学協同の進展など、中小企業の先端科学や技術へのアプローチなども垣間見えて来たが、やはり、日本のベンチャーなり中小企業は、教育や科学、経済社会的なバックグラウンド等が違うので、シリコンバレーで生まれ出るような、全くクリエイティブで革新的なブルー・オーシャンではなく、目的が明確であるとか、ソリューションがはっきりしている場合などのブレイクスルーの追及や、既存技術やノウハウの深掘りと言った持続的イノベーションに向かう方が向いているのであろう。
元気印の今を時めく中小企業のトップたちが立って、その企業経営の底力の秘密を開陳すると言う非常に興味深い会合となり、その後、懇親会に入り、中小企業の人々との交わりがあった。
これらの優良中小企業の成功話を聞いていて、悉く共通しているのは、ブルーオーシャン市場の開拓に成功して、好業績を上げ続けていると言うことであった。
このブログでもずっと書き続けて来た私の思いでもあるので、ここで、これらの企業のケースを借りて再説してみたいと思う。
ブルー・オーシャンとは、W・チャン・キムとレネ・モボルニュが、「ブルー・オーシャン戦略」で展開した理論で、共通して優良企業が好業績を持続している要因は、ブルー・オーシャン(新しい市場)の開拓とその成功による発展成長にあることを発見したことから生まれた理論である。
好業績やその持続を実現させているのは、産業や企業に内在する要因などではなくて、新しい市場空間を切り開き、ブルー・オーシャンの開拓に成功し、需要を創造し大きく押し上げたその企業の戦略にあったのである。
ブルー・オーシャン戦略とは、コスト競争や従来型の差別化戦略で、ライバル企業との競争に打ち勝つという手法ではなく、競争のない未知の市場空間を開拓することによって、買い手や自社にとっての価値を大幅に高めるとともに、競争を無意味にしてしまうバリュー・イノベーションにあると言うことで、このブルー・オーシャン市場では、競争を前提とした戦略論の常識であるコスト競争で勝つか差別化で勝つかと言う「価値とコストはトレードオフ」と言う関係を覆し、差別化と低コストを同時に実現することによる成長発展である。
したがって、このシンポジウムに登壇した中小企業は、悉く、その分野でのオンリー・ワン企業で、自分の道を自分自身で切り開いてわが道を行くことによって活路を見出しているのであるから、モデルもなければ、競争相手さえないと言うパイオニアである。
しかし、市場に恵まれて技術などの優位だけに胡坐をかいている良くある創業ベンチャーのような脆弱な企業ではなく、経営戦略や企業体質・システムなどがしっかりしていて、経営そのものに問題のない優秀な企業家によって経営されていると言うことである。
旺盛なチャレンジ精神を持続しながら、絶えず時代の潮流に敏感に対応した経営の舵を取り、街の中小企業から、宇宙産業や原子力産業などの高度なハイテクの世界までにも製品やサービスを提供するのであるから、日本の中小企業の底力の凄さには目を見張るものがある。
基調講演に立ったのは、合成樹脂製品の金型製造から事業を展開した大成プラス(株)の成冨正徳社長で、合成樹脂をメインにしたデザイン・設計・金型製造販売・輸出入およびノウハウ・技術の提供・ライセンス供与を行いながら、接合をコンセプトにしたオリジナル技術をベースに設備なき製造業を目指しており、日本のトップ自動車メーカーなどへハイテク部品を提供するのは勿論、独自に開発した技術は特許で300件を超え、海外にも進出して、既に6件のライセンスパートナーを持つと言う。
他所で出来ないような相談ばかり来るのだが、顧客と対面するのではなく、横に座って、客と同じ目線に立って仲間意識で問題点を検討し、失敗を繰り返しながら解決策を炙り出しソリューションを導き出すのだと言う。
単なる下請けではなく、ものの作り方を一緒に考えて解決するもの作りのパートナーだと言う意気込みである。
この何か役に立つことがないかと待ち構えていて、誰も何処も解決できないような要求が来れば、出来るか出来ないか考える前に仕事を引き受けて挑戦すると言うもの作り精神の横溢した技術者・職人魂は、どの成功中小企業にもある共通した特徴である。
面白いのは、ラシャ問屋からスタートしたヒーティング技術ノウハウでは断トツの坂口電熱(株)で、NOと言わない技術開発に徹した対面R&D開発によるオーダーメイド戦略を社是としており、既に、世に送り出した製品は300万点を超えると言うのだから恐れ入る。
ヒーターと言うヒーターは言うに及ばず、温度センサーやコントローラー、絶縁材料まで「加熱」に関するアイテムは常に9000アイテムを取り揃えていると言うことだが、
この会社は、年商40億程度の中小企業ながら、NPOを設立して地域社会への貢献をしているのみならず、海外からの私費留学生への奨学金を支援する財団を設立して延べ200人に及ぶと言う「社業を通してご恩返しを」と言う企業理念を推し進めていると言う見上げたエクセレント・カンパニーである。
この会社の蜂谷真弓社長は、非常にチャーミングな若いレディで、滔々と会社の未来像を熱っぽく語っており、日本の新しい会社像が見えてくるようで頼もしい。
もう一つの分かり易いケースのブルー・オーシャンは、臼井努社長が語った東西テクノス(株)のビジネス・モデルで、メーカーがサポートを打ち切ってしまってサービス切れとなった製品の修理・保守・メインテナンス一切を引き受けると言う戦略で、計測機器の修理から始まって、医療、情報、通信分野等の各種機器、システムを何処のメーカー製品でもワンストップでサービス対応すると言うマルチベンダー・サービスで、仕事は、原子力発電所にまで及んでいると言う。
産学協同の進展など、中小企業の先端科学や技術へのアプローチなども垣間見えて来たが、やはり、日本のベンチャーなり中小企業は、教育や科学、経済社会的なバックグラウンド等が違うので、シリコンバレーで生まれ出るような、全くクリエイティブで革新的なブルー・オーシャンではなく、目的が明確であるとか、ソリューションがはっきりしている場合などのブレイクスルーの追及や、既存技術やノウハウの深掘りと言った持続的イノベーションに向かう方が向いているのであろう。