新春の国立劇場の歌舞伎は、音羽屋の華やかな舞台「通し狂言 世界花小栗判官」であった。
歌舞伎座のアラカルトの見取り公演とは違って、復活通し狂言と言う斬新さと何を見せてくれるかと言う時めきや期待を抱かせてくれて、非常に興味深いのである。


室町時代、足利義満への復讐と天下掌握を企てる謎の盗賊・風間八郎(菊五郎)は、足利家の重宝「勝鬨の轡」「水清丸の剣」を強奪。足利家の執権・細川政元(時蔵)は風間の野望の阻止を図り、風間に父を殺害された小栗判官(菊之助)は、紛失した重宝と風間の行方を詮議し、風間と政元・判官の対決を軸に、歌舞伎が展開される。
HPの説明を借りると、
菊五郎演じるスケールの大きな悪の権化風間の暗躍を軸にして、荒馬・鬼鹿毛を鮮やかに乗りこなす馬術の名手・判官の曲馬乗り、風間と政元との虚々実々の駆け引き、照手姫(尾上右近)の危機を救う元・小栗の家臣浪七(松緑)の命懸けの忠義と壮絶な立廻り、離れ離れになっていた判官と照手姫の邂逅がもたらす長者の後家お槙(時蔵)と娘お駒(梅枝)の悲劇、熊野権現の霊験が判官と照手姫に起こす奇跡など、
ビジュアルにもサウンドにも舞台全体に面白い趣向を加えるなど工夫に工夫を重ねての演出で、非常に楽しませてくれた。
早い話、小栗判官の菊之助の乗る荒馬・鬼鹿毛など、張り子の馬と言うよりは、競馬馬のサラブレッドのような颯爽としたスマートな素晴らしい姿であり、並の舞台馬とは違って、それだけに、菊之助の雄姿が脚光を浴びるのである。
小栗判官伝説に基づく判官と照手姫の物語もこの歌舞伎の軸なのだが、菊之助と尾上右近の華麗な舞台も華を添えていて素晴らしい。
お槙(時蔵)と娘お駒(梅枝)と言う親子コンビの芸の素晴らしさは流石で、このあたりに、伝統芸術の凄さを感じた。
勿論、この舞台は、菊五郎あっての歌舞伎なのは言うまでもないが、松緑の骨太の演技は特筆もので、彦三郎父子兄弟、團蔵、権十郎、萬次郎、秀調と言ったベテラン脇役陣の活躍も見逃せない。
余談だが、新春の国立劇場には、羽子板のディスプレイなど華やかな展示がされていて面白い。





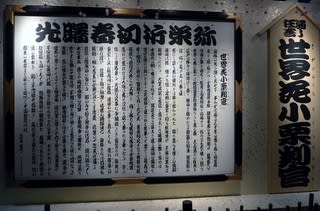
この日、和服姿の観客に加えて、きもの学院の人たちが参集していて、客席が日頃以上に華やかであった。



さて、開場時間には、時雨程度であったが、開演中に雪が降り始めて、一気に雪景色に包まれた。
休憩時の雪景色は、以下の通りだが、
終演時には、歩くのにも困るほどの大雪となり、這う這うの体で自宅に辿りついた時には、わが庭は雪一色。







歌舞伎座のアラカルトの見取り公演とは違って、復活通し狂言と言う斬新さと何を見せてくれるかと言う時めきや期待を抱かせてくれて、非常に興味深いのである。


室町時代、足利義満への復讐と天下掌握を企てる謎の盗賊・風間八郎(菊五郎)は、足利家の重宝「勝鬨の轡」「水清丸の剣」を強奪。足利家の執権・細川政元(時蔵)は風間の野望の阻止を図り、風間に父を殺害された小栗判官(菊之助)は、紛失した重宝と風間の行方を詮議し、風間と政元・判官の対決を軸に、歌舞伎が展開される。
HPの説明を借りると、
菊五郎演じるスケールの大きな悪の権化風間の暗躍を軸にして、荒馬・鬼鹿毛を鮮やかに乗りこなす馬術の名手・判官の曲馬乗り、風間と政元との虚々実々の駆け引き、照手姫(尾上右近)の危機を救う元・小栗の家臣浪七(松緑)の命懸けの忠義と壮絶な立廻り、離れ離れになっていた判官と照手姫の邂逅がもたらす長者の後家お槙(時蔵)と娘お駒(梅枝)の悲劇、熊野権現の霊験が判官と照手姫に起こす奇跡など、
ビジュアルにもサウンドにも舞台全体に面白い趣向を加えるなど工夫に工夫を重ねての演出で、非常に楽しませてくれた。
早い話、小栗判官の菊之助の乗る荒馬・鬼鹿毛など、張り子の馬と言うよりは、競馬馬のサラブレッドのような颯爽としたスマートな素晴らしい姿であり、並の舞台馬とは違って、それだけに、菊之助の雄姿が脚光を浴びるのである。
小栗判官伝説に基づく判官と照手姫の物語もこの歌舞伎の軸なのだが、菊之助と尾上右近の華麗な舞台も華を添えていて素晴らしい。
お槙(時蔵)と娘お駒(梅枝)と言う親子コンビの芸の素晴らしさは流石で、このあたりに、伝統芸術の凄さを感じた。
勿論、この舞台は、菊五郎あっての歌舞伎なのは言うまでもないが、松緑の骨太の演技は特筆もので、彦三郎父子兄弟、團蔵、権十郎、萬次郎、秀調と言ったベテラン脇役陣の活躍も見逃せない。
余談だが、新春の国立劇場には、羽子板のディスプレイなど華やかな展示がされていて面白い。





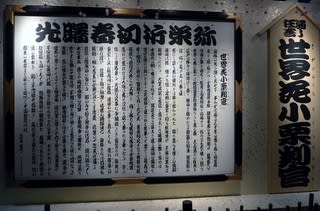
この日、和服姿の観客に加えて、きもの学院の人たちが参集していて、客席が日頃以上に華やかであった。



さて、開場時間には、時雨程度であったが、開演中に雪が降り始めて、一気に雪景色に包まれた。
休憩時の雪景色は、以下の通りだが、
終演時には、歩くのにも困るほどの大雪となり、這う這うの体で自宅に辿りついた時には、わが庭は雪一色。























































































