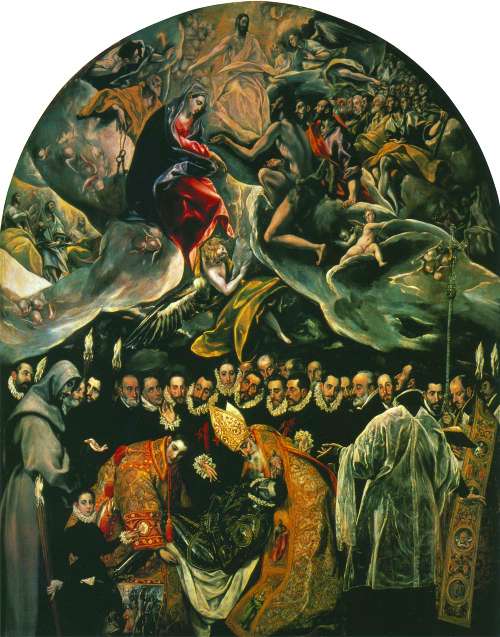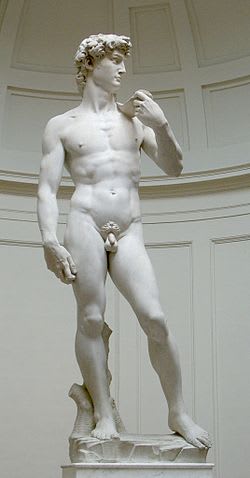トーマス・フリードマンが、「レクサスとオリーブの木」で、1999年の半ばの時点で、マクドナルドを有する任意の二国は、夫々に、マクドナルドが出来て以来戦争をしたことがないと言うデータを武器にして、”紛争防止の黄金のM型アーチ理論”を打ち立てた。
マクドナルドのある国は、中流階級が現れるレベルまで発展したので、最早、失うものの方が多いので、戦争はしない。と言う理論である。
更に、フリードマンは、「フラット化する世界」において、デル・システムのようなジャスト・イン・タイム式サプライ・チェーンで密接に結合された国々の間では、旧来の脅威を駆逐(?)するので戦争など起こらないと言う「デルの紛争回避論」を展開し、マクドナルドに象徴される生活水準の全般的傾向よりも、ずっと地政学的な冒険主義を防止する効果があると説いている。
ところが、ジョン・J・ミアシャイマーは、「大国政治の悲劇」において、経済やビジネス関係の連鎖など、平和維持には何の関係もなく、とにかく、経済大国となれば、必ず、軍事力を強化して覇権を狙う危険な国になるので、中国が世界経済のリーダーになれば、その経済力を軍事力に移行させ、北東アジアの支配に乗り出してくるのは確実である。と力説していることは、先月、ブックレビューで紹介した。
中国が民主的で世界経済に深く組み込まれているかどうかとか、独裁制で世界経済から孤立しているかどうかとかは重要な問題ではなく、どの国家にとっても、自国の存続を最も確実にするのは、覇権国になることだからであると、
多くのアメリカ人が、もし、中国の急速な経済成長が続いて「巨大な香港」へとスムーズに変化し、中国が民主的になってグローバル資本主義システムに組み込まれれば、侵略的な行動は起こさずに、北東アジアの現状維持で満足するであろうから、アメリカは経済的に豊かで民主的になった中国と協力して、世界中に平和を推進することが出来ると言うような甘いアメリカの関与政策が失敗するのは確実である。と、アメリカのリベラル派の対中国観を一蹴している。
これと同じ、と言うよりも、もっと強烈な中国脅威論を、中西輝政教授が、「迫りくる日中冷戦の時代」で展開していて、非常に興味深い。
急速な経済成長を遂げた中国が、国力の増大にまかせてアジア太平洋への露骨な成長政策を取ったことによって、アメリカは、従来の「関与」政策から、「抑止」政策に転じて、今や、中国を盟主とする全体主義勢力と、アメリカを中心とする民主主義勢力とがアジア太平洋地域で対峙する、新たな冷戦が始まったのだと説く。
さて、論点の、経済的な依存関係があれば、冷戦的対立や戦争が起こらないのかと言うことだが、答えは否で、歴史上、経済の相互依存関係がどれだけ深くても、戦争が起こっている事例は数限りなくあると言う。
「フォリーン・アフェアーズ」で、ドラッカーが、グローバル・エコノミーが国民国家を凌駕してしまうのではなく、必ず国民国家が勝利を収めて、両国の経済を分断すると、第一次世界大戦で、オーストリアのフィアットが戦車を製造してイタリア兵を殺戮した例を挙げているのが面白い。
日米が開戦した太平洋戦争を考えても、あるいは、これ以上ないほどの緊密な相互依存関係にある国内での内戦の勃発を考えても、経済の相互依存が軍事対立や戦争を防ぐことが出来ないことは自明であって、日中の経済関係についても、国家を超えて「相互依存はもはや死活問題と言えるほど深い」と言うことは絶対にあり得ない。と言うのである。
EUは、ユーロ問題によって、今や、「金融面の内戦」状態に突入していて、経済的な依存関係は、決して平和を保障しないばかりか、国家間対立をむしろ加速させる場合もあるとまで言う。
中国と日本の関係について、中西教授は、現代中国がはらむ「大いなる危うさ」として、
あれだけの暴虐な天安門事件
台湾の武力統一政策の継続
尖閣諸島紛争に伴うフジタ社員の拉致・拘束とレアアース対日禁輸と言う国際法と貿易ルールの公然たる無視等による日本威嚇
を列挙して、中国が如何に経済大国となり日本やアメリカと経済関係が深まっても、根本的に「パートナー」と成り得ず、常に「脅威」の源であり続けると主張している。
中西教授が、日本人の84%が中国に対して悪い印象を持っているとする世論調査を引用して、この水準は、ポイント・オブ・ノーリターンを越えていて、日中友好の時代は終わったのだと論じている。
丹羽前中国駐在大使が、「将来は大中華圏の時代だから、日本は中国の属国として生きて行けばよく、それが、日本が幸福かつ安全に生きる道です」と言ったと本書で引用していて、もし、本当だとすれば、極めて由々しき問題だと思うのだが、フリードマンが正しいかどうかは別として、どうしても、中国経済にどっぷりと関わっている経済界は、経済関係優先であって、融和政策なり、従属政策に陥り易いのは事実であろう。
私は、世界中の大方が、中国が、現状の経済成長を維持して順調に先進国への道を進んで行き、世界一の大国になると考えているようだが、必ずしも、それ程上手く行く筈がなく、共産党一党独裁と腐敗政治、公害問題と格差拡大による国民生活の窮乏と生活環境破壊、中西教授が指摘するようにロシア韓国までも含めた中国包囲網の国際的反撃、チベット・ウイグル問題、南シナ海東シナ海での紛争による国際外交の孤立、その他不安定な国際情勢etc. いくらでも巨大な落とし穴が待ち構えていて、途中で頓挫する可能性が高いと思っている。
まず、第一に、開花して啓蒙されてきた中国国民が黙っていないであろうと思う。
いずれにしろ、平和であって欲しいと思っているし、中国の偉大な歴史や文化文明には畏敬の念を禁じ得ないが、私の現在の対中国観は、どちらかと言えば、ミアシャイマーや中西教授に近いと思っている。
しかし、大切なのは、もう、後のなくなった宇宙船地球号に共存共栄する人類が、如何に、サステイナブルな生活環境を必死になって維持して行くかを考えれば、いがみ合ったり紛争に明け暮れている場合ではないと言う認識を持つことだと思っている。
マクドナルドのある国は、中流階級が現れるレベルまで発展したので、最早、失うものの方が多いので、戦争はしない。と言う理論である。
更に、フリードマンは、「フラット化する世界」において、デル・システムのようなジャスト・イン・タイム式サプライ・チェーンで密接に結合された国々の間では、旧来の脅威を駆逐(?)するので戦争など起こらないと言う「デルの紛争回避論」を展開し、マクドナルドに象徴される生活水準の全般的傾向よりも、ずっと地政学的な冒険主義を防止する効果があると説いている。
ところが、ジョン・J・ミアシャイマーは、「大国政治の悲劇」において、経済やビジネス関係の連鎖など、平和維持には何の関係もなく、とにかく、経済大国となれば、必ず、軍事力を強化して覇権を狙う危険な国になるので、中国が世界経済のリーダーになれば、その経済力を軍事力に移行させ、北東アジアの支配に乗り出してくるのは確実である。と力説していることは、先月、ブックレビューで紹介した。
中国が民主的で世界経済に深く組み込まれているかどうかとか、独裁制で世界経済から孤立しているかどうかとかは重要な問題ではなく、どの国家にとっても、自国の存続を最も確実にするのは、覇権国になることだからであると、
多くのアメリカ人が、もし、中国の急速な経済成長が続いて「巨大な香港」へとスムーズに変化し、中国が民主的になってグローバル資本主義システムに組み込まれれば、侵略的な行動は起こさずに、北東アジアの現状維持で満足するであろうから、アメリカは経済的に豊かで民主的になった中国と協力して、世界中に平和を推進することが出来ると言うような甘いアメリカの関与政策が失敗するのは確実である。と、アメリカのリベラル派の対中国観を一蹴している。
これと同じ、と言うよりも、もっと強烈な中国脅威論を、中西輝政教授が、「迫りくる日中冷戦の時代」で展開していて、非常に興味深い。
急速な経済成長を遂げた中国が、国力の増大にまかせてアジア太平洋への露骨な成長政策を取ったことによって、アメリカは、従来の「関与」政策から、「抑止」政策に転じて、今や、中国を盟主とする全体主義勢力と、アメリカを中心とする民主主義勢力とがアジア太平洋地域で対峙する、新たな冷戦が始まったのだと説く。
さて、論点の、経済的な依存関係があれば、冷戦的対立や戦争が起こらないのかと言うことだが、答えは否で、歴史上、経済の相互依存関係がどれだけ深くても、戦争が起こっている事例は数限りなくあると言う。
「フォリーン・アフェアーズ」で、ドラッカーが、グローバル・エコノミーが国民国家を凌駕してしまうのではなく、必ず国民国家が勝利を収めて、両国の経済を分断すると、第一次世界大戦で、オーストリアのフィアットが戦車を製造してイタリア兵を殺戮した例を挙げているのが面白い。
日米が開戦した太平洋戦争を考えても、あるいは、これ以上ないほどの緊密な相互依存関係にある国内での内戦の勃発を考えても、経済の相互依存が軍事対立や戦争を防ぐことが出来ないことは自明であって、日中の経済関係についても、国家を超えて「相互依存はもはや死活問題と言えるほど深い」と言うことは絶対にあり得ない。と言うのである。
EUは、ユーロ問題によって、今や、「金融面の内戦」状態に突入していて、経済的な依存関係は、決して平和を保障しないばかりか、国家間対立をむしろ加速させる場合もあるとまで言う。
中国と日本の関係について、中西教授は、現代中国がはらむ「大いなる危うさ」として、
あれだけの暴虐な天安門事件
台湾の武力統一政策の継続
尖閣諸島紛争に伴うフジタ社員の拉致・拘束とレアアース対日禁輸と言う国際法と貿易ルールの公然たる無視等による日本威嚇
を列挙して、中国が如何に経済大国となり日本やアメリカと経済関係が深まっても、根本的に「パートナー」と成り得ず、常に「脅威」の源であり続けると主張している。
中西教授が、日本人の84%が中国に対して悪い印象を持っているとする世論調査を引用して、この水準は、ポイント・オブ・ノーリターンを越えていて、日中友好の時代は終わったのだと論じている。
丹羽前中国駐在大使が、「将来は大中華圏の時代だから、日本は中国の属国として生きて行けばよく、それが、日本が幸福かつ安全に生きる道です」と言ったと本書で引用していて、もし、本当だとすれば、極めて由々しき問題だと思うのだが、フリードマンが正しいかどうかは別として、どうしても、中国経済にどっぷりと関わっている経済界は、経済関係優先であって、融和政策なり、従属政策に陥り易いのは事実であろう。
私は、世界中の大方が、中国が、現状の経済成長を維持して順調に先進国への道を進んで行き、世界一の大国になると考えているようだが、必ずしも、それ程上手く行く筈がなく、共産党一党独裁と腐敗政治、公害問題と格差拡大による国民生活の窮乏と生活環境破壊、中西教授が指摘するようにロシア韓国までも含めた中国包囲網の国際的反撃、チベット・ウイグル問題、南シナ海東シナ海での紛争による国際外交の孤立、その他不安定な国際情勢etc. いくらでも巨大な落とし穴が待ち構えていて、途中で頓挫する可能性が高いと思っている。
まず、第一に、開花して啓蒙されてきた中国国民が黙っていないであろうと思う。
いずれにしろ、平和であって欲しいと思っているし、中国の偉大な歴史や文化文明には畏敬の念を禁じ得ないが、私の現在の対中国観は、どちらかと言えば、ミアシャイマーや中西教授に近いと思っている。
しかし、大切なのは、もう、後のなくなった宇宙船地球号に共存共栄する人類が、如何に、サステイナブルな生活環境を必死になって維持して行くかを考えれば、いがみ合ったり紛争に明け暮れている場合ではないと言う認識を持つことだと思っている。