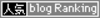目的を定めてそれを保持するという人類の持つ能力は(拙稿の見解によれば)、仲間との協力のために必要だから、人類の身体に備わったものでしょう。
家族で生活するために食料を保存する。つまみ食いしない。その目的を共有する必要があります。狩りの仲間と獲物を包囲する。皆で獲物を担いで運ぶ。言語で目的を表現し共有する必要があります。つまり狩猟採集生活の中で、仲間と一緒に活動する、社会のようなものを形成するためには、言葉で表現される目的を共有していなければなりません。
原始人が仲間と協力して落とし穴を掘る場合、ウサギを捕まえる目的なのか、イノシシを捕まえる目的なのかで穴の場所も大きさも深さも違う。どんな動物を捕まえようとしているのか、行動の途中で目的がぶれてしまうとうまく協力できません。ウサギとかイノシシとかいう言葉を使わないとまったく不便です。仲間と協力するために、まずは目的を共有して行動の過程でその目的を変わらないように維持する。目的を言語表現してその言葉を仲間で共有する。現代社会では、契約とか、計画とか、スローガンとか、校訓とか、憲法とかの形を取ったりもします。
目的を言語化し仲間と共有する。そういう仕組みが人類の身体に備わるようになったのでしょう(拙稿21章「私はなぜ自分の気持ちが分かるのか(6)」)。
人類は(拙稿の見解によれば)仲間と緊密な連携行動をする必要から、目的というものを使うようになった。次の段階として、目的を使うことに習熟してくると、これをいろいろな別の用途に使うことができるようになります。
まず、人間は、他人、他の集団、あるいは動物、あるいは気象や化学変化など非生物の自然現象、その他すべての事象に対して、その目的を問うことができるようになる。幼児が「なぜ」「どうして」と親に質問する段階ですね。「象さんはなぜお鼻が長いの?」とかです。
人類の進化過程で、物事の目的を問うことで、その物事がこれからどのように変化していくのかを予測することができるようになったと思われます。目的を推定することが予測することになるという認知機構が人類の身体に備わったといえます。
「象さんはなぜお鼻が長いの?」と子供が聞けば、大人が「お手々の代わりに食べ物をお口に運べるようにお鼻が長いのよ」と答えてくれるでしょう。すると子供は「じゃあ、象さんはお鼻でお箸を持つの?」と言ったりします。
この場合、子供は象の鼻の目的を知ることでその鼻の用途を予測しています。子供は、象の鼻を、人間が手を使ってする仕事をすることを目的として存在しているものであると理解し、そうであればどのような予測が可能なのかを考えることができます。こうして子供は象の鼻がどう動くものであるかを推定する能力を身につけることになります。
人類の認知機構は(拙稿の見解では)、物事が変化推移する過程の予測を(その物事が内包する)目的を推定するという方法で実行します。人類はそのような物事の予測を仲間と共同して行う。そこから(拙稿の見解では)人類の言語が発生しました(拙稿26章「「する」とは何か?」 )。
人間は、仲間の動作、表情あるいは音声表現と共鳴することで物事の予測を共有します。私たちの身体が無意識のうちに働くその結果を、私たちは物事の現実として身体で実感していると感じます。私たちが、物事が当然そうなると感じるとき(拙稿の見解によれば)、それは仲間がそう感じていることを感じ取っていることからくる感覚である、つまり現実である、ということになります。
こういう現実認識をしている私たち人間は、物事を予測しなければならないと感じるとき、その物事が起きる目的(物事が内包する目的)を知ろうとする。そうすることで仲間とともに現実であるその物事に対応して連携行動を取ることができます。
そのために物事の動きの目的を知りたい。それを問う言葉として「なぜ」という疑問詞ができた、といえます(拙稿31章「私はなぜ、なぜと問うのか(6)」)。