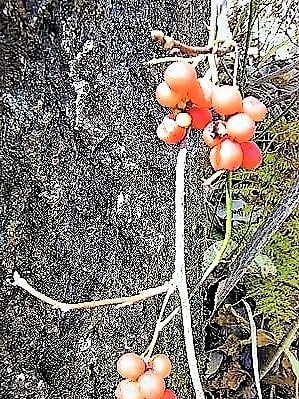サラシナショウマ(晒菜升麻)
<キンポウゲ科サラシナショウマ属>
山地の林内や林縁で白い花の穂が目立つ。
草丈は60~120センチになり、
葉は2~3回分かれる複葉。
花は両性花と雄花があり、
多数穂状につきブラシのように見える。
5~10ミリの花柄があることでイヌショウマと見分けられる。
高尾山では、もう花が終わっているものが多く、
1センチほどの袋状になった果実がよく見られた。
サラシナ(晒菜)とは、
若菜を茹でて水に晒して食べる、ま
たは茹でる前に冷水に1日くらい晒してアクを抜くと言う意味で、
ショウマ(升麻)とは漢方薬の生薬の名前。

もう、殆ど花が散った状態でした。