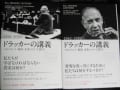ブラジル経済には、まだまだ、課題が沢山残ってはいるが、私は、インフレーションの激しい不安定な軍人大統領の時代を知っているので、
ハーパー・インフレを終息させた1994年のレアル・プランの功績には絶大なものがあり、その後、世紀末のアジアやロシアなどの新興国危機に直面して、1999年に、為替を固定相場制から変動相場制に切り替え、インフレターゲットを導入したものの、財政責任法を制定して更にプライマリーバランス目標の徹底的維持を図るなど、カルドーゾ蔵相(後に大統領)の実施した絶妙なマクロ経済政策の舵取りがなければ、今日のBRIC'sの雄としてのブラジルはなかったのではないかと思っている。
その後のルーラ政権が、市場経済重視の前政権の基本方針を受け継ぎ、更に、マクロ政策の健全化を促進し、2005年には、IMF借入を完済し、2007年には純債権国に転換し、2009年には、ガイトナー財務長官から、世界的金融危機救済者として感謝されたと言うのであるから、正に、今昔の感しきりである。
このレアル・プランの少し前に、コロル政権が実施したコロル計画で、貿易の自由化、外資導入と公営企業の民営化を実施して、それまでの輸入代替工業化政策で国際競争力のない脆弱な工業部門と非効率な公営企業による劣悪な工業サービス、植民地時代の時代遅れの統治制度や富の偏在等々を一挙に排除しようとしたのを、「従属理論」の権威であるカルドーゾ教授が新自由主義的な経済政策で引き継いだのである。
さて、ローターは、ブラジルの農業について、アマゾンの南部に広がる広大な熱帯サバンナ・セラードの農業開発、農牧リサーチ会社エンブラパの活躍、そして、アフリカへの技術移転などについて農業スーパーパワー・ブラジルを語っている。
実は、このセラードだが、30年前、田中角栄によって始まり、ブラジルの広大な荒れ地を開拓し、日本の技術で緑の農地に変えたのだが、残念ながら、ローターは一言も日本について言及しないし、現在では、ブンゲ、カーギル、ADMなど穀物メージャーに抑えられて、日本の姿は見る影もない。
このセラードは、2億ヘクタールで、日本の2.5倍の面積で、地球上に残った唯一の農業開発可能地だと言うのだが、そして、ブラジルの農産物、野菜や果物を育てたのは、すべて、日本人移民だと言うのだが、食料を海外に依存している日本の食糧安全保障の見地から言っても、あまりにも、今日の日本のブラジルとの関係は希薄となっている。
酸性の土地に石灰を撒いて土地改良して荒れ地を蘇らせた日本の多くの農業学者や役人たちが、ブラジルで果たした熱帯農業の開発や品種改良や作物開発など、高度なバイオ技術の移転が実を結んで、ブラジルは、今や、この分野では、世界最先端を行くようだが、このセラードの開発ノウハウと技術を、アフリカ諸国に持ち込んで、農地開発を行おうとしている。
ところで、比較的上手く進行して経済発展を続けているブラジルだが、ローターは、そのブラジル経済が完全にその持てる能力を発揮できないボトルネックについて言及している。
まず、最初は、国土の広範囲に及ぶインフラの劣悪さ不十分さである。
十分なドックも倉庫もない貧弱な港湾を筆頭に、空港、高速道路、鉄道など不備未整備は甚だしく、2016年のリオのオリンピックは大丈夫かと言った状態である。
次に酷いのは、非効率で汚職塗れの官僚システム。
500年前のポルトガル人移民そのままのメンタリティを根本的に変える必要があるのだと指摘して、例えば、証明書や許認可や公的文書の取得は勿論のこと、あらゆるお役所仕事では、延々と長い列が出来て時間の浪費が甚だしいと言う。
1980年代に、この問題を解決するために、脱官僚省を設置したようだが、調査と申告受領役人を増やしただけで、国民の嘲笑を買い潰れててしまった。
この非効率極まりない役所仕事を上手く取り仕切るのが、金を払えば中に入って何でも処理してくれるヨロズ代行業のデスパシャンテで、個人的にも、人コネや賄賂で処理するブラジル流解決法ジェイトが威力を発揮するのだが、これは、既に説明済みなので解説は省略する。
上から下まで、賄賂とキックバックなど役人を喜ばせることなら何でも有効だとローターは言うのだが、このブラジルの評判を貶めている透明性の欠如、法律や規則よりも人間関係が優先すると言うブラジルでのビジネスは、外国人には、大変なのだが、法治国家の機能が働かないアミーゴ社会に順応する以外に道がないと言うことであろう。
その他に、ローターは、ブラジルの課題として、教育の貧困、異常な所得格差や貧困問題等々の克服について論じているが、とにかく、世界の格付け会社が、ブラジルの格付けをアップグレイドし、サンパウロ証券取引所が、世界第4位となり、益々、発展の勢いだと言うことであるから、ブラジル経済は、もう、はるか以前にテイクオフしたと言うことであろう。
とにかく、限りなく豊かで、輝かしい未来を秘めたブラジルを無視して、明日の人類社会を語れなくなったのである。
ハーパー・インフレを終息させた1994年のレアル・プランの功績には絶大なものがあり、その後、世紀末のアジアやロシアなどの新興国危機に直面して、1999年に、為替を固定相場制から変動相場制に切り替え、インフレターゲットを導入したものの、財政責任法を制定して更にプライマリーバランス目標の徹底的維持を図るなど、カルドーゾ蔵相(後に大統領)の実施した絶妙なマクロ経済政策の舵取りがなければ、今日のBRIC'sの雄としてのブラジルはなかったのではないかと思っている。
その後のルーラ政権が、市場経済重視の前政権の基本方針を受け継ぎ、更に、マクロ政策の健全化を促進し、2005年には、IMF借入を完済し、2007年には純債権国に転換し、2009年には、ガイトナー財務長官から、世界的金融危機救済者として感謝されたと言うのであるから、正に、今昔の感しきりである。
このレアル・プランの少し前に、コロル政権が実施したコロル計画で、貿易の自由化、外資導入と公営企業の民営化を実施して、それまでの輸入代替工業化政策で国際競争力のない脆弱な工業部門と非効率な公営企業による劣悪な工業サービス、植民地時代の時代遅れの統治制度や富の偏在等々を一挙に排除しようとしたのを、「従属理論」の権威であるカルドーゾ教授が新自由主義的な経済政策で引き継いだのである。
さて、ローターは、ブラジルの農業について、アマゾンの南部に広がる広大な熱帯サバンナ・セラードの農業開発、農牧リサーチ会社エンブラパの活躍、そして、アフリカへの技術移転などについて農業スーパーパワー・ブラジルを語っている。
実は、このセラードだが、30年前、田中角栄によって始まり、ブラジルの広大な荒れ地を開拓し、日本の技術で緑の農地に変えたのだが、残念ながら、ローターは一言も日本について言及しないし、現在では、ブンゲ、カーギル、ADMなど穀物メージャーに抑えられて、日本の姿は見る影もない。
このセラードは、2億ヘクタールで、日本の2.5倍の面積で、地球上に残った唯一の農業開発可能地だと言うのだが、そして、ブラジルの農産物、野菜や果物を育てたのは、すべて、日本人移民だと言うのだが、食料を海外に依存している日本の食糧安全保障の見地から言っても、あまりにも、今日の日本のブラジルとの関係は希薄となっている。
酸性の土地に石灰を撒いて土地改良して荒れ地を蘇らせた日本の多くの農業学者や役人たちが、ブラジルで果たした熱帯農業の開発や品種改良や作物開発など、高度なバイオ技術の移転が実を結んで、ブラジルは、今や、この分野では、世界最先端を行くようだが、このセラードの開発ノウハウと技術を、アフリカ諸国に持ち込んで、農地開発を行おうとしている。
ところで、比較的上手く進行して経済発展を続けているブラジルだが、ローターは、そのブラジル経済が完全にその持てる能力を発揮できないボトルネックについて言及している。
まず、最初は、国土の広範囲に及ぶインフラの劣悪さ不十分さである。
十分なドックも倉庫もない貧弱な港湾を筆頭に、空港、高速道路、鉄道など不備未整備は甚だしく、2016年のリオのオリンピックは大丈夫かと言った状態である。
次に酷いのは、非効率で汚職塗れの官僚システム。
500年前のポルトガル人移民そのままのメンタリティを根本的に変える必要があるのだと指摘して、例えば、証明書や許認可や公的文書の取得は勿論のこと、あらゆるお役所仕事では、延々と長い列が出来て時間の浪費が甚だしいと言う。
1980年代に、この問題を解決するために、脱官僚省を設置したようだが、調査と申告受領役人を増やしただけで、国民の嘲笑を買い潰れててしまった。
この非効率極まりない役所仕事を上手く取り仕切るのが、金を払えば中に入って何でも処理してくれるヨロズ代行業のデスパシャンテで、個人的にも、人コネや賄賂で処理するブラジル流解決法ジェイトが威力を発揮するのだが、これは、既に説明済みなので解説は省略する。
上から下まで、賄賂とキックバックなど役人を喜ばせることなら何でも有効だとローターは言うのだが、このブラジルの評判を貶めている透明性の欠如、法律や規則よりも人間関係が優先すると言うブラジルでのビジネスは、外国人には、大変なのだが、法治国家の機能が働かないアミーゴ社会に順応する以外に道がないと言うことであろう。
その他に、ローターは、ブラジルの課題として、教育の貧困、異常な所得格差や貧困問題等々の克服について論じているが、とにかく、世界の格付け会社が、ブラジルの格付けをアップグレイドし、サンパウロ証券取引所が、世界第4位となり、益々、発展の勢いだと言うことであるから、ブラジル経済は、もう、はるか以前にテイクオフしたと言うことであろう。
とにかく、限りなく豊かで、輝かしい未来を秘めたブラジルを無視して、明日の人類社会を語れなくなったのである。