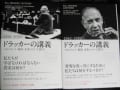ドラッカーの半世紀以上に亘る講義を選別集大成した本の後半部分がこの本である。
沢山あるドラッカーの著作の様に、切れ味の良いパルテノン神殿のように構築された学問の息吹とは、大分毛色の変わった、ある意味では、ピントの定かではない、あっちこっちに脱線した、時には支離滅裂の間口の広い講義録で、生身のドラッカーが滲み出ていて、非常に面白い。
私が興味を感じたのは、最後のクレアモントで行った4回の「会社の未来」と言う講義で、晩年に会社について、ドラッカーはどう考えていたか知りたかったのである。
冒頭に、企業は未来があるのかと聞かれて、「ありますよ。今までと違った形になる。所有者によるコントロールから、戦略によるコントロールへ移行する。あるいは、事業を関係した巨大集積企業から、提携や相互強調に基づくある種の同盟へ移行する、と言う議論です。」と答えている。
後者については、どんな仕事をしようが、その仕事は会社の中ですると言う基本的な前提を放棄し、今は、毎日取り組んでいない仕事は外部委託(アウトソーシング)すると言う基本的前提に変ったとしている。
社内の力だけで仕事を完結するためには、コアコンピタンスが必要で、アウトソーシングするのは、コストの節約ではなく、知識の生産性を向上させるためだと言う。
別な所で、情報化時代の今日、平和な時代には、国家も企業も大きいと言うことには、もはや何の現実的な優位性もなくなったと言っているのだが、ドラッカーの優等生である筈の日本企業は、合併に合併を重ねて、益々、何でもワングループで完結できる総合企業を目指しているのだが、どう言うことであろうか。
それに、日本企業は、アウトソーシングもオープンビジネス・モデルへの転換も遅々として進まず、ブラックボックス的な知財管理と自前のイノベーション追及に拘り過ぎているような感じがするのだが、どうであろうか。
ドラッカーは、戦略によるコントロールについては語っていないが、かと言って、日本企業が、所有者によるコントロール段階にあるとも思えない。
ドラッカーは、成果とは何かと言うところで、厳しい競争の世界において、ビジネスの組織が存在する目的は、変化を生み出すことと変化を活かすことにあると説いて、その際、競争を仕掛けてくる相手は、同じ製品を作る、或いは、同じサービスを考えている企業とは限らず、どこから競争相手が飛び込んでくるか分からない時代になったのであるから、
絶え間のない変化やイノベーションの視点から成果を定義し直す決断に迫られていると言う。
この外部の異業種からの競争については、内田早大教授の異業種格闘技説で展開されているのだが、ドラッカーは、更に、どんな業種であっても、企業を取り巻く重要な変化は、いつの場合でも、顧客でない人たちがいる外部から起こると説くなど、顧客ではない顧客から、競争相手でない競争相手から、強烈な挑戦を受けていることを随所で説いて、チャレンジ&レスポンスの重要性を強調している。
マイケル・ポーターでも、自分でも、内側から外側を向いて説いて来たが、経営とは何かを理解したければ、多くの場合、組織の内部を外から見つめること、組織の外における成果から考え始めなければならないと言うのである。
次に、「情報を握る者が実権を握る」と言うのは大昔からの名言だが、今や、インターネットの発達のお蔭で、情報は顧客へ移転し続けていると言う。
そして、インターネットには距離の概念がないので、あらゆるものが、ローカルなマーケットになってしまったのだが、何がマーケットなのか、顧客が欲しがっているのは何かと言う面においては、情報と言う観点から定義される傾向が益々強くなると言う。
インターネットによる情報革命は、根本的な変化の前兆であり、マーケットのみならず、組織もビジネスも定義しなおさなければならなくなったと言うのである。
もう一つ、この講義で、ドラッカーは、欧米諸国が支配してきた国際経済が、多極化した経済へ行く、そうした過程の初期の段階にあり、また、アメリカによる現在の経済的支配は一時的現象で、しかもそれは、急速に終わりに向かっていると言う。
面白いのは、世界の構成単位が国ではなく経済圏、NAFTA、南米のメルコスール、EUと言った経済圏に移行を始めており、経済圏が新しい上部構造として、世界経済の主なエージェントとして急速に表舞台に現れていると言う見解である。
この経済圏は、内部では自由貿易を許すが、外部に対しては、極端な保護主義的な姿勢を取っているので、新たな重商主義の時代に突入することになるのだが、経済圏が輸出を促進し輸入を抑えようとする方策など上手く機能しないことは分かっていると言う。
しかし、フラット化したグローバル時代になっており、ボーダーレスで、テクノロジーの発展とICT革命によって、人モノ金情報が、自由に国境を越える今日において、経済圏などと言う組織が、世界の交易交流を阻害するような働きをするのであろうか。
中国やインド、それに、ブラジル、益々元気な次に続く新興国のパワー炸裂を考えれば、旧秩序など一挙に吹き飛んでしまう筈である。
沢山あるドラッカーの著作の様に、切れ味の良いパルテノン神殿のように構築された学問の息吹とは、大分毛色の変わった、ある意味では、ピントの定かではない、あっちこっちに脱線した、時には支離滅裂の間口の広い講義録で、生身のドラッカーが滲み出ていて、非常に面白い。
私が興味を感じたのは、最後のクレアモントで行った4回の「会社の未来」と言う講義で、晩年に会社について、ドラッカーはどう考えていたか知りたかったのである。
冒頭に、企業は未来があるのかと聞かれて、「ありますよ。今までと違った形になる。所有者によるコントロールから、戦略によるコントロールへ移行する。あるいは、事業を関係した巨大集積企業から、提携や相互強調に基づくある種の同盟へ移行する、と言う議論です。」と答えている。
後者については、どんな仕事をしようが、その仕事は会社の中ですると言う基本的な前提を放棄し、今は、毎日取り組んでいない仕事は外部委託(アウトソーシング)すると言う基本的前提に変ったとしている。
社内の力だけで仕事を完結するためには、コアコンピタンスが必要で、アウトソーシングするのは、コストの節約ではなく、知識の生産性を向上させるためだと言う。
別な所で、情報化時代の今日、平和な時代には、国家も企業も大きいと言うことには、もはや何の現実的な優位性もなくなったと言っているのだが、ドラッカーの優等生である筈の日本企業は、合併に合併を重ねて、益々、何でもワングループで完結できる総合企業を目指しているのだが、どう言うことであろうか。
それに、日本企業は、アウトソーシングもオープンビジネス・モデルへの転換も遅々として進まず、ブラックボックス的な知財管理と自前のイノベーション追及に拘り過ぎているような感じがするのだが、どうであろうか。
ドラッカーは、戦略によるコントロールについては語っていないが、かと言って、日本企業が、所有者によるコントロール段階にあるとも思えない。
ドラッカーは、成果とは何かと言うところで、厳しい競争の世界において、ビジネスの組織が存在する目的は、変化を生み出すことと変化を活かすことにあると説いて、その際、競争を仕掛けてくる相手は、同じ製品を作る、或いは、同じサービスを考えている企業とは限らず、どこから競争相手が飛び込んでくるか分からない時代になったのであるから、
絶え間のない変化やイノベーションの視点から成果を定義し直す決断に迫られていると言う。
この外部の異業種からの競争については、内田早大教授の異業種格闘技説で展開されているのだが、ドラッカーは、更に、どんな業種であっても、企業を取り巻く重要な変化は、いつの場合でも、顧客でない人たちがいる外部から起こると説くなど、顧客ではない顧客から、競争相手でない競争相手から、強烈な挑戦を受けていることを随所で説いて、チャレンジ&レスポンスの重要性を強調している。
マイケル・ポーターでも、自分でも、内側から外側を向いて説いて来たが、経営とは何かを理解したければ、多くの場合、組織の内部を外から見つめること、組織の外における成果から考え始めなければならないと言うのである。
次に、「情報を握る者が実権を握る」と言うのは大昔からの名言だが、今や、インターネットの発達のお蔭で、情報は顧客へ移転し続けていると言う。
そして、インターネットには距離の概念がないので、あらゆるものが、ローカルなマーケットになってしまったのだが、何がマーケットなのか、顧客が欲しがっているのは何かと言う面においては、情報と言う観点から定義される傾向が益々強くなると言う。
インターネットによる情報革命は、根本的な変化の前兆であり、マーケットのみならず、組織もビジネスも定義しなおさなければならなくなったと言うのである。
もう一つ、この講義で、ドラッカーは、欧米諸国が支配してきた国際経済が、多極化した経済へ行く、そうした過程の初期の段階にあり、また、アメリカによる現在の経済的支配は一時的現象で、しかもそれは、急速に終わりに向かっていると言う。
面白いのは、世界の構成単位が国ではなく経済圏、NAFTA、南米のメルコスール、EUと言った経済圏に移行を始めており、経済圏が新しい上部構造として、世界経済の主なエージェントとして急速に表舞台に現れていると言う見解である。
この経済圏は、内部では自由貿易を許すが、外部に対しては、極端な保護主義的な姿勢を取っているので、新たな重商主義の時代に突入することになるのだが、経済圏が輸出を促進し輸入を抑えようとする方策など上手く機能しないことは分かっていると言う。
しかし、フラット化したグローバル時代になっており、ボーダーレスで、テクノロジーの発展とICT革命によって、人モノ金情報が、自由に国境を越える今日において、経済圏などと言う組織が、世界の交易交流を阻害するような働きをするのであろうか。
中国やインド、それに、ブラジル、益々元気な次に続く新興国のパワー炸裂を考えれば、旧秩序など一挙に吹き飛んでしまう筈である。