監督 スティーブン・フリアーズ 出演 ジュディ・デンチ、スティーブ・クーガン
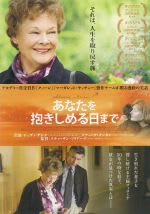
息子の消息を探す母親。息子はアメリカに養子として引き取られた。母親はアイルランドからアメリカまで息子を探しに行く。で、アメリカに着いたとたんに、息子はすでに死んでいるとわかる。
あ、これではストーリーの展開のしようがない。
と、思ったらそうでもない。まるで森鴎外の「渋江抽斎」である。「渋江抽斎」は、鴎外の評伝のなかでは、あっと言う間に死んでしまう。このあと、どう書くのか。何を書くのか。
ほんとうのおもしろさは、ここから。
ひとの人生は死んだらおしまいではない。死ぬまでは、視線はそのひとに集中してしまうが、死んでしまうと彼のまわりの人間に目が広がる。そして、他人のなかにいる彼が、なんといえばいいのか、非常に豊かである。ひととひととの関係において、ひとはいろいろな表情をみせる。ちがった姿をみせる。それは、そのひとだけに視線が向いているときには見落としてしまう何かである。どうしても、自分とそのひとという関係でしかみることができないからね。
で、同時に、それはその息子を探していた母親についてもいえる。
息子を探しているときは、息子を探す母でしかないのだが、息子が死んでしまうと、探すということが微妙にかわってくる。息子を探すというよりも、「時代」を探す、「社会」を探す--からさらに進んで、「生きる」を探すという具合に。
ジュディ・デンチはいっしょに養子に引き取られた少女(妹)を尋ねて息子の様子を聞く。息子の恋人(ゲイ)を尋ねて息子の様子を聞く。そこで、息子がしっかり自分の幸せをつかんでいたことを知る。笑顔と誇らしげな顔、愛されている悦びの顔。さらにはアイルランドのことを忘れず、つまり母親のことを忘れずに、母親を探していたことを知る。アイルランドの修道院まで尋ねてきていたことを知る。母親が息子を愛しているように、息子はずーっと母親を愛していたということを知る。遺体(遺骨)はアイルランドに埋葬されているということも知る。
生きているあいだは、遠かった「愛情」が、死んでからなまなましく動きはじめる。息子は死んでいないのに、こころは今を生きて動いている。で、その生きているこころのために、ジュディ・デンチは修道院の嘘を突きつめに行く。何が親子の愛情を引き裂き、その対面を邪魔したのかを問いつめる。このとき、ジュディ・デンチはひとりではない。息子といっしょに生きている。息子といっしょに行動している。
いやあ、すごいですねえ。ジュディ・デンチの最高の演技。引き込まれていく。
クライマックス。息子は養子に引き取られ(無理やり養子として里親のもとに引き取られ)、親子のあいだが引き裂かれた--というのではなく、なんと、養子引き取りがビジネスとして存在していた。修道院が未婚の母とこどもを世話するするとみせかけて、養子斡旋で金を稼いでいた、こどもを売っていたということがわかる。そして、それを母親には秘密にしていた。息子にも、母親の情報を与えず、秘密にしていた。そういうことがわかったあとで。
ジュディ・デンチは、修道院の責任者(?)に対し、「私はあなたを赦す」と言う。「なぜ怒らないんだ」と問いただすジャーナリストに「許しには苦しみがともなう。(私は苦しみを背負っている。その苦しみによって相手を赦す)」と言う。これはまるで十字架を背負うキリストみたいだが--そこには苦しみと同時に不思議な安らぎのようなものがある。赦すということをとおして、ジュディ・デンチは「自由」になっている。息子との関係を引き裂かれた悲しみから解放されている。解放されていると言ってしまうと、ちょっと違うのかもしれないけれど……。
彼女は、いま、息子といっしょにいる。死んでしまったけれど、息子はいままでよりもさらに鮮明にジュディ・デンチのなかに生きている。その「生」そのものを共有できたから、共有することで愛し合ったから、ジュディ・デンチは修道院のしたことを赦すのである。ジュディ・デンチはいっしょに息子の消息を追ってくれたジャーナリストに「書かないで」と一度は言うのだが、最後には「やっぱり書いて」と言う。ことばのなかで、もういちど母と息子の愛は生きる。生きるだけではなく、永遠に生き続ける。そう気がつくからである。その愛が生きるとき、修道院の犯した罪は死ぬ--と書くと、うーん、なんだか宗教の教科書みたいでいやだが。
しかし、これは、すばらしい作品だなあ。地味だけれど2014年のベストワンと言ってしまいたいなあ。
ジュディ・デンチの愛の赦しが声高でないように、すべての影像が実に静かだ。その静かさのなかに、すべてが隠れている。息子がアイルランドを忘れていないということをギネスのマークから探っていくところなんか、とてもいいなあ。ジャーナリストは一度その息子に会っているが、よくおぼえていなというのもいいなあ。何よりも、ジュディ・デンチをただ崇高なひとという感じで映画にするのではなく、あまり教養もないふつうのおばさん(おばあさん)として描いているのもいい。好きな小説は、恋愛大衆小説。読んだストーリーを的確に要約できる。それを楽しく語っているのもいい。さらに、そのおばさんの大衆恋愛小説好みをジャーナリストが「そんな本なんか」とばかにしているのもいい。ジュディ・デンチのことを立派な女性というふうに見ていないことが、逆にジュディ・デンチの演じた女性の美しさを引き立てている。ジュディ・デンチとは対照的なスティーブ・クーガンの演技もいい。
何も新しいことはない。新しい影像、肉眼では見ることのできない不思議な影像はない。感覚を切り開くような音楽もない。そういう「新奇な何か」がまったくない、ということろがとてもすばらしい。新しい影像も音楽もないのだけれど、ここに描かれた愛の形はけっして古びない。そういう強さがすばらしい。この愛には力がある。
この映画は、力を与えてくれる。力を実感させてくれるのである。
(中州大洋4、2014年04月09日)
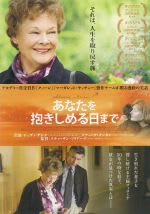
息子の消息を探す母親。息子はアメリカに養子として引き取られた。母親はアイルランドからアメリカまで息子を探しに行く。で、アメリカに着いたとたんに、息子はすでに死んでいるとわかる。
あ、これではストーリーの展開のしようがない。
と、思ったらそうでもない。まるで森鴎外の「渋江抽斎」である。「渋江抽斎」は、鴎外の評伝のなかでは、あっと言う間に死んでしまう。このあと、どう書くのか。何を書くのか。
ほんとうのおもしろさは、ここから。
ひとの人生は死んだらおしまいではない。死ぬまでは、視線はそのひとに集中してしまうが、死んでしまうと彼のまわりの人間に目が広がる。そして、他人のなかにいる彼が、なんといえばいいのか、非常に豊かである。ひととひととの関係において、ひとはいろいろな表情をみせる。ちがった姿をみせる。それは、そのひとだけに視線が向いているときには見落としてしまう何かである。どうしても、自分とそのひとという関係でしかみることができないからね。
で、同時に、それはその息子を探していた母親についてもいえる。
息子を探しているときは、息子を探す母でしかないのだが、息子が死んでしまうと、探すということが微妙にかわってくる。息子を探すというよりも、「時代」を探す、「社会」を探す--からさらに進んで、「生きる」を探すという具合に。
ジュディ・デンチはいっしょに養子に引き取られた少女(妹)を尋ねて息子の様子を聞く。息子の恋人(ゲイ)を尋ねて息子の様子を聞く。そこで、息子がしっかり自分の幸せをつかんでいたことを知る。笑顔と誇らしげな顔、愛されている悦びの顔。さらにはアイルランドのことを忘れず、つまり母親のことを忘れずに、母親を探していたことを知る。アイルランドの修道院まで尋ねてきていたことを知る。母親が息子を愛しているように、息子はずーっと母親を愛していたということを知る。遺体(遺骨)はアイルランドに埋葬されているということも知る。
生きているあいだは、遠かった「愛情」が、死んでからなまなましく動きはじめる。息子は死んでいないのに、こころは今を生きて動いている。で、その生きているこころのために、ジュディ・デンチは修道院の嘘を突きつめに行く。何が親子の愛情を引き裂き、その対面を邪魔したのかを問いつめる。このとき、ジュディ・デンチはひとりではない。息子といっしょに生きている。息子といっしょに行動している。
いやあ、すごいですねえ。ジュディ・デンチの最高の演技。引き込まれていく。
クライマックス。息子は養子に引き取られ(無理やり養子として里親のもとに引き取られ)、親子のあいだが引き裂かれた--というのではなく、なんと、養子引き取りがビジネスとして存在していた。修道院が未婚の母とこどもを世話するするとみせかけて、養子斡旋で金を稼いでいた、こどもを売っていたということがわかる。そして、それを母親には秘密にしていた。息子にも、母親の情報を与えず、秘密にしていた。そういうことがわかったあとで。
ジュディ・デンチは、修道院の責任者(?)に対し、「私はあなたを赦す」と言う。「なぜ怒らないんだ」と問いただすジャーナリストに「許しには苦しみがともなう。(私は苦しみを背負っている。その苦しみによって相手を赦す)」と言う。これはまるで十字架を背負うキリストみたいだが--そこには苦しみと同時に不思議な安らぎのようなものがある。赦すということをとおして、ジュディ・デンチは「自由」になっている。息子との関係を引き裂かれた悲しみから解放されている。解放されていると言ってしまうと、ちょっと違うのかもしれないけれど……。
彼女は、いま、息子といっしょにいる。死んでしまったけれど、息子はいままでよりもさらに鮮明にジュディ・デンチのなかに生きている。その「生」そのものを共有できたから、共有することで愛し合ったから、ジュディ・デンチは修道院のしたことを赦すのである。ジュディ・デンチはいっしょに息子の消息を追ってくれたジャーナリストに「書かないで」と一度は言うのだが、最後には「やっぱり書いて」と言う。ことばのなかで、もういちど母と息子の愛は生きる。生きるだけではなく、永遠に生き続ける。そう気がつくからである。その愛が生きるとき、修道院の犯した罪は死ぬ--と書くと、うーん、なんだか宗教の教科書みたいでいやだが。
しかし、これは、すばらしい作品だなあ。地味だけれど2014年のベストワンと言ってしまいたいなあ。
ジュディ・デンチの愛の赦しが声高でないように、すべての影像が実に静かだ。その静かさのなかに、すべてが隠れている。息子がアイルランドを忘れていないということをギネスのマークから探っていくところなんか、とてもいいなあ。ジャーナリストは一度その息子に会っているが、よくおぼえていなというのもいいなあ。何よりも、ジュディ・デンチをただ崇高なひとという感じで映画にするのではなく、あまり教養もないふつうのおばさん(おばあさん)として描いているのもいい。好きな小説は、恋愛大衆小説。読んだストーリーを的確に要約できる。それを楽しく語っているのもいい。さらに、そのおばさんの大衆恋愛小説好みをジャーナリストが「そんな本なんか」とばかにしているのもいい。ジュディ・デンチのことを立派な女性というふうに見ていないことが、逆にジュディ・デンチの演じた女性の美しさを引き立てている。ジュディ・デンチとは対照的なスティーブ・クーガンの演技もいい。
何も新しいことはない。新しい影像、肉眼では見ることのできない不思議な影像はない。感覚を切り開くような音楽もない。そういう「新奇な何か」がまったくない、ということろがとてもすばらしい。新しい影像も音楽もないのだけれど、ここに描かれた愛の形はけっして古びない。そういう強さがすばらしい。この愛には力がある。
この映画は、力を与えてくれる。力を実感させてくれるのである。
(中州大洋4、2014年04月09日)
 | 危険な関係 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |



























