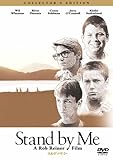樋口伸子『ノヴァ・スコティア』(石風社、2010年10月11日発行)
詩とは何か。樋口伸子『ノヴァ・スコティア』には、その答えの手がかりが書かれている。「声と声」という作品。
「ノブコ ノブコ
心配せずに帰っておいで・父母」
六年前から十月になれば出るという
毎年からなず朝刊に出るという
ひとが教えてくれた尋ね人
あなたのことじゃないよねぇ
もちろん わたしのことじゃない
ちちははは死んで数十年
わたしはここにいる
ここにいます
信子さん おはよう
延子さん こんにちは
伸子さん こんばんは
宣子さん おやすみなさい
順子さん いただきます
暢子さん ごちそうさま
お元気でいてください
わたしの知っているのぶ子さん
わたしの知らないノブコさん
「ノブコ ノブコ 帰っておいで」
角を曲がると知らない声がする
つむじ風が吹く
大勢のノブコたちが
落葉にまじって舞い散る
六年たっても同じ呼びかけが
新聞の片隅に父母より
橋を渡るとき覚えのある声がする
「心配しないで帰っておいで」
水面 光 海猫の一群が
名を呼びながら旋回する
わたしのことかも知れない と思う
わたしのことにちがいない と思う
きっと帰ろう と思う
呼びかける声の方へ
「ノブコ」が「わたし」ではないことを知っている。「頭」では、その事実はわかりきっている。なぜなら「わたし」の「父母」は死んでいる。だから新聞に尋ね人の広告(?)を出すことはできない。
けれども、「わたしのことかも知れない と思う/わたしのことにちがいない と思う」。間違いであると知っていても、そう思ってしまう。それは「頭」で思うのではないのだ。「肉体」で思うのだ。
樋口は、「ことば」へ向かって「思う」のではなく、「呼びかける声」の方へ向かって思うのである。「声」は「耳」で聞くものである。
いま、ここにある耳は、その声を聞こえないと主張する。
けれど、樋口の「肉体」のなかにある「耳」、いわば「肉耳」が聞き取るのだ。
肉眼ということばがあるのだから「肉耳」ということばがあってもいいような気がする。しかし、ふつうにはそういうことばを聞かないところをみると、耳は目(眼)よりも無意識に近くて、肉といっしょにしか存在しえないものなので、だれも「肉耳」ということばを思いつかなかったのかもしれない。
--眼は、耳に比べると肉体から分離し「頭」へと組み込むことができるものなのかもしれない。「百聞は一見にしかず」ということばがあるが、どうも「眼」の方が「耳」よりも「認識」においては信頼されている感じがする。「認識」において重要な役割を果たしているようである。眼は認識(頭)に結びついているというのは、そういう「ことわざ」からも窺い知れる。その「ことわざ」を逆に考えると、耳は眼よりも百倍も「認識」から遠い。「頭」から遠いことになる。
その、「頭」から遠いもの、「声」の方へ樋口は接近していく。「肉耳」をたよりに、間違えることで、間違いの向こう側まで行ってしまおうとする。
ここに、樋口の詩がある、そして、あらゆる詩がある、と私は思う。(あるいは、そんな具合に「誤読」したい、と私は思うのだ。)
「頭」(知識)で整理すれば完全に間違っている。けれど、その間違いを「肉体」は自分のなかでねじ曲げて正しいものにしてしまう。「思う」ということばで、すべて「正しい」何かにかえてしまう。「頭」で「考える」のではなく、「肉体」で「思う」ことで、その「思う」のなかにある何か「正しい」ものをつかみ取ってしまうのだ。
それは、この詩では「帰っておいで」という父母の「声」が持っている「正しさ」である。「帰っておいで」は実は「帰っておいで」というよりも、「いつでも受け止めるよ」ということばを言い換えたものである。ことばはいつでもさまざまに言い換えられる。そして、どんなに言い換えても、「肉体」はかわらない。「ノブコ」がいて「父母」がいて、その「肉体」があるとき、ことばがどんなに変わっても、そこでは「肉体」は出会うしかないのである。「肉体」と「肉体」が出会う。それが「帰っておいで」であり、ここには書かれていないが「受け止めるよ」ということなのだ。
その「声」にならなかった「声」、「受け止めるよ」を「肉耳」は聞くのである。
「声にならない声」とは、「ことばにならないことば」でもある。それは「ことばにならないことば」だから書かれることはない。つまり、眼で読むことはできない。ただ「肉耳」で聞くしかないのである。
「ことばにならないことば」。それは「ことば以前のことば」であるときもあれば、「ことばを超えたことば」であることもあるだろう。どちらにしろ、その「声」を「肉耳」は「一聞」で納得してしまう。
詩とは、「百見は一聞にしかず」という世界かもしれない。
*
「肉耳」と「眼」。聞くことと見ること--そのことから樋口の詩を見ていくと「夏休み」はとてもおもしろい。
困ったものを見てしまった
八月の森の家で
ああ 困ったものを
見てしまった
空洞(うろ)になった古木の切株
大きな耳に似た突起
うちわに似たスピーカーに似た
樹の大耳が笑っている
あわてるな(消去 削除 取消)
見たものを消す呪文はないものか
耳が怖い あっても怖い
なくても怖い
計画的に眠りについた
計画的にたのしい夢を
おやすみ おやすみ
あれは空耳
樋口は、まず「見る」。「見てしまった」と書いているが、その見たものとは古木の切り株の変な形である。それは大きな耳に似ている。
それからが、とてもおもしろい。
樹の大耳が笑っている
耳が笑う。こういうことばは「日本語」にはない。目で笑うということばはあっても、耳で笑うとは言わない。そして、たいていは口で笑う。笑うとき「声」が出る。
「耳が笑う」は、「耳で笑い声を聞く」ということかもしれない。
樋口は書いていないが、「見てしまった」のあと、見ることをとおして「聞いてしまった」のだ。笑い声を。そして、その「笑い声」は実は樋口の耳ではなく、「切り株の耳」が聞いたものである。「切り株の耳」が聞いたものを、「切り株の耳」が「笑っている」と勘違いする。錯覚する。
そのとき。
樋口の「肉耳」は「切り株の大耳」そのものである。「肉耳」は「大耳」になっている。区別がつかない。
それは「笑い声」を切り株の大耳が「発している」のか、それとも「聞いている」のか区別がつかないのと同じことなのだ。
区別がつかないことを「媒介」にして、「肉耳」と「切り株の大耳」は「ひとつ」になってしまうのである。
そして「区別がつかない」ということを利用して(?)、樋口は、それを「空耳」といってしまう。幻だと、言ってしまう。目で見たもの、切り株の大耳の形をした突起は「幻」として消してしまうことはないが、聞いたことを、それはほんとうはなっかたもの、樋口の「肉体」のなかで何かが鳴り響き、それを勘違いしたもの--「肉体」のそとには存在しないもの、存在しない「音」としてしまう。
それにしてもおもしろいものだなあ、と私は、ちょっと飛躍する。
見たものをそのまま受け入れるのに、聞いたものを受け入れない。見たものを肯定しながら、聞いたものを否定する。それも、その音が存在しない、音が幻であるというかわりに、「耳」がニセモノであるという。
「空耳」という。
見たものが幻なら「幻影」という言い方ができる。聞いたものの場合はなんというのだろう。「幻音(げんおん)」というものがあるかどうか、よくわからない。よくわからないけれど、「幻音」のかわりに、肉体は「空耳」ということばを受け入れるのだろう。
見たものは、それが幻であるときは、その対象のせいにする。しかし、聞いたものの場合は、対象を非難する(?)ことはしないで、自分の「耳」のせいにして「空耳」という。
目(眼)と耳は、どうも変な力関係にあるなあ。
そして、この変な関係を、樋口は「耳」にちかづく形で樋口のものにしている。そこから樋口の詩がはじまっている。
ざ ざ ざ
困ったものがやって来る
ざざ ざざざざ ざ
耳の行列が耳を振りふり
声もなく夜を笑いながら
聴き耳を立てて
森の家の窓に貼りつく
知らない知らない
あたしはなあんにも
おやすみ おやすみ
これも空耳
明ければ青ぞら 蝉のこえ
雲の帽子で頭をかくせば
空のことは空に聞け
耳のことは耳に聞け
「見てしまった」ではじまった世界が「聞け」でおわる。ここにも樋口の「肉耳」の世界の特徴がよくでている。
「見ろ」ではなく「聞け」。
どこかで、何かが、ねじまがっている。まあ、そう言ってしまえば、無関係な読者としては安心だけれど、あ、おもしろいと感じてしまうと、ずぶずぶずぶずぶっと樋口の「肉体」の、眼と耳のさかいめのない世界へまで入り込んでしまったような気がしてくる。