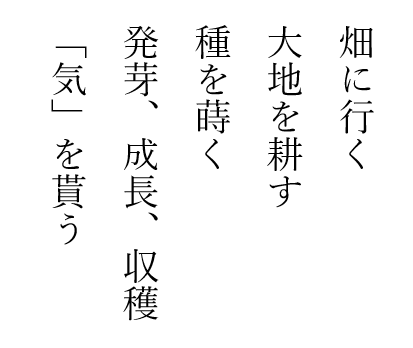人生100年時代・林住期から游行期
& 終末医療
=死生観=

「林住期」五木寛之著、読み終えて納得した。
ラジオ深夜便9月号を開いた。
ラジオ千一夜で「百歳人生折り返し」で、又も五木氏が語っていた。
もう1つ「南杏子著・『穏やかな終末』を読み、合点した。
静かなブームとの事でした。

「林住期」、人生のピークと言うのは無謀だろうか。
人生前半の50年は、世のために働いた。50歳から75歳までの25年間。
後半人生こそが、人間が人間らしく自由気ままに社会に迷惑かけないように、
自ら人生を生きるべきであると語っている。
読み終えて納得・了解・合点した。

1、学生期・・25歳ころまで
2、家住期・・25歳から50歳ころ
3、林住期・・50~75歳ころ
4、游行期・・75歳以降
100歳人生を箱根駅伝に例えるならば、
折り返し地点(人生の頂点)を箱根の山で迎え、いま復路を下る。
林住期の始まりで、あまり全速力で走るより、ゆったり周りの景色を楽しみたい。
往路が1回目の人生であるなら、復路折り返は二回目の人生の事始め。
◎ 旅に出ることなく、游行の人となる。
これから70代、80代の新しい人生の選択。
游行期という人生を考え思い返してみると、自分自身の欲望をかなえるだけでなく、
大切な人に負担を掛けない生き方の選択なのであろう。
これは自らを大事にするとともに、周辺の人・伴侶を大切にすることである。
明日を見つけて、元気なアクティブシニアでありたい。
自治体の掲げる“生涯自立”のコンセプト「食事」「運動」「生きがい」をそれぞれ
研究し、実践し、アクティブに生きることこそ大切である。
セカンドライフ(第二の人生)を考えるとき、多くの自治体で生涯学習や情報交換
の場、さまざまな催しやイベント、ビジネスが展開されている。
行事にアクテブに参加することでしょう。
100歳人生社会は新たな道筋、一歩一歩ゆっくりと未知の世界に
足を踏み入れようとしています。
◎ 60代に入ったら、先ず一人になってみる。
人間最後は、一人で死んでいく覚悟することである。
『穏やかな終末』≪サイレント・ブレス≫・南杏子著が多くの人達に読まれている。
終末医療・看取る医療が必要と説いている。
サイレント・ブレスとは、「静かな息」『穏やかな息』という意味だそうです。

死は負けではなくゴールである。
―――ガンの権威であった、名誉教授が末期がんに侵され、
患者自身が「治らないから無駄な延命はするな」と、治療や点滴を全部拒否した。
この老教授は「治療はいらん、動物は食べられなくなったら死ぬ」という
人間の原点に戻った発想である。
印象的な言葉で、元気である内は、どんな治療も効く。
海上や地面すれすれに飛ぶ飛行機は、墜落する危険が大きい。
それと同じように倒れ掛かった家に、つっかい棒をしたり、
壁を塗り替え、屋根を修理するよりもより、
寄り添う治療(サイレント・ブレス)が大切であると説いている。
大きな重機を入れて、家をつぶしてしまうような医療ではありません。
著者は「人は必ず死ぬ。死を受け入れる医師が必要、患者を愛してあげよ!」
そこで「延命」を主な目的にせず、
医者は患者の身体に出来うる限り、痛みを与えない緩和ケアを行う。
そうすることで、患者に安らかな最期を迎えてもらう。
これが終末期医療の在り方だと、著者は言い切っている。

死のゴールから逆算して、少しでも心地よい終末医療を心掛けたい。
残された時間を楽しみたい。減塩など制限食でなく美味しく味合う、お酒やたばこも
楽しみたい、苦しいリハビリは無理をすることはない。
同僚に、腎臓がんで逝った人がいる。担当医に直言した。
私は「タバコ大好き人間です。吸わせて下さい」と言い切り、
息を引き取るまでタバコを吸ったと言う。
五木寛之著「林住期」と、南杏子著・『穏やかな終末』が
NHKラジオ深夜便9月号に、解説付きで掲載されていたので貪るように読みました。・・だが、私の意見は1つも述べていない。
一言だけ言うならば、
「静かな息」『穏やかな息』
老教授の「治療はいらん、動物は食べられなくなったら死ぬ」の、
意見に従いたい。
私も魂の存在は信じたいと思います。
≪人は死なない≫
https://www.youtube.com/watch?v=HLVeGlGYdEw
コメント欄は閉めています。




















 、どの様に運ばれて来たのか?
、どの様に運ばれて来たのか?




 、
、 したそうです。
したそうです。