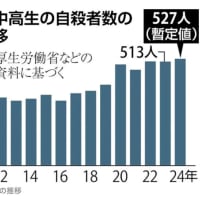帝国憲法は1889年(明治22年)2月11日に発布された。これを主導したのが、伊藤博文であり井上毅である。伊藤は岩倉使節団が担ってきた、富国強兵・国家の近代化を大前提に憲法を作成した。
日本の知識層はこの間懸命に近代化を模索していた。明治元年から5年の間にアメリカだけでも、600人もの留学生を送っている。
後に大正デモクラシーの基礎となる人たちが懸命に、日本の骨格となる憲法つくりを模索していた。私擬憲法は、明治12~14年をピークに日本各地で作成された。
中でも植木枝盛の草案と、千葉卓三郎の後に五日市憲法と称される憲法は、近代国家と国民の基本的人権を取り入れたものであった。
国を変えるのは武力ではなく言論であると言っていた、千葉卓三郎の主張は敗戦後の新憲法が公布されるまで、実質的にお蔵に入れられたままであった。
ビスマルクに傾倒していた伊藤博文たちは、結局こうした一般社会での論議を無視する形で、帝国憲法を作り上げた。
天皇の軍隊の統帥権は見直す機会を踏みにじり、国務大臣の輔弼(天皇に進言し了解を取り付ける)を必要条件とし、結果として天皇を侵すべからずと、軍隊の力が無限に大きくなったのである。
結果として、帝国憲法の交付は健全なこの国の議論の展開・発展を阻害することになった。
新憲法はこうした枝盛や千葉たちの思想が、鈴木大蔵たちによって取り込まれることになったのである。
今また、アメリカに後押しされてこの国の健全な論議の発展を阻害し、武力こそが正義のように主張する一派が、憲法改悪を企んでいる。