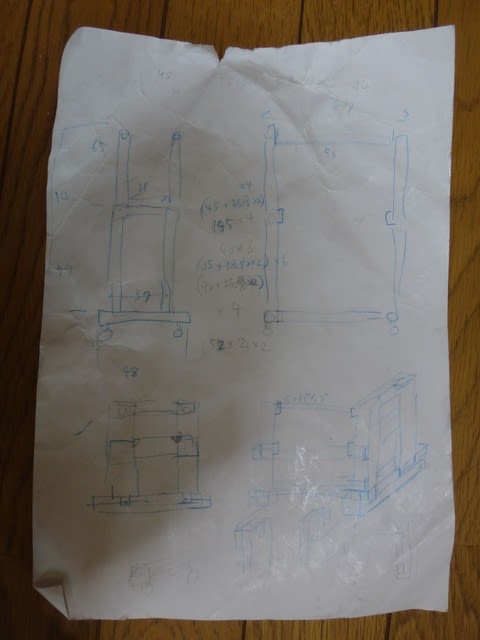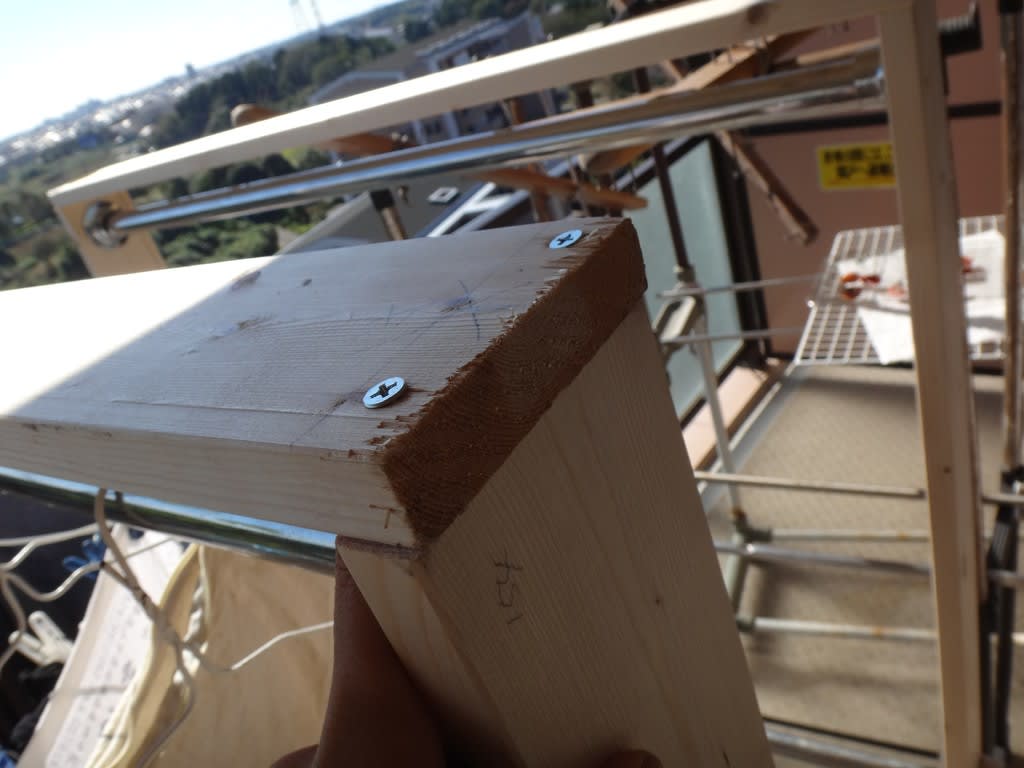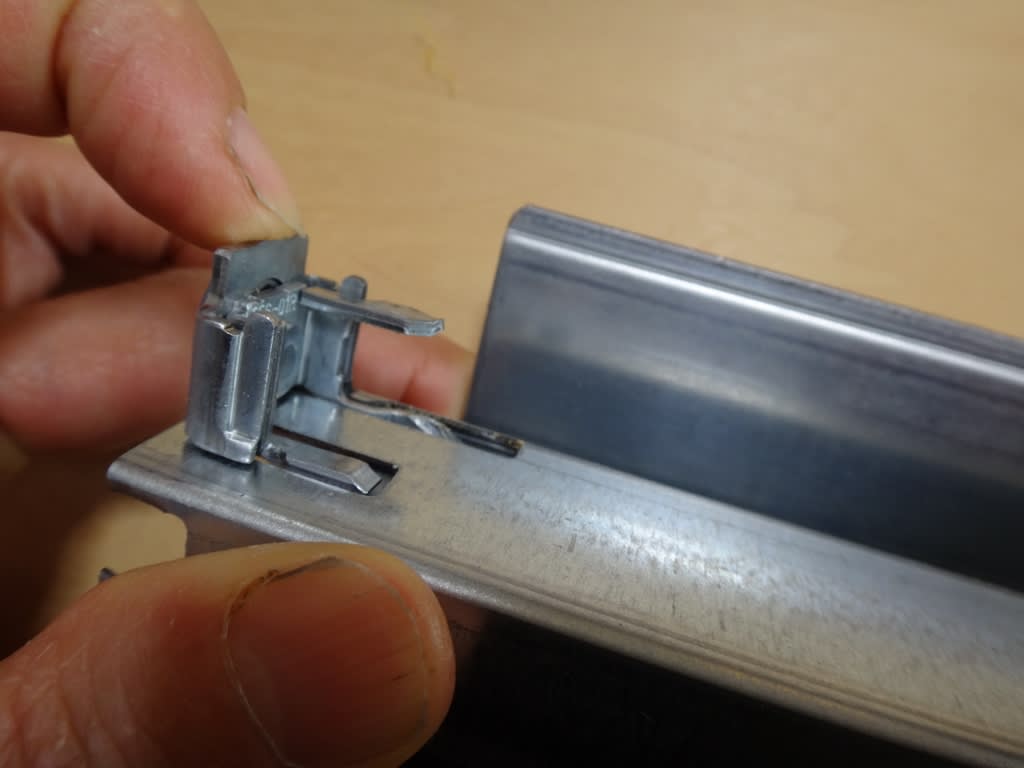しばらく前のDIYです。
===
台所の突き当たりの壁は、コンクリートに壁紙が直に貼ってあるものです。
この壁面に、ちょっとした棚というか、ぶら下げられるようなバーというか、そういうものをとりつけたい、と思い立ちました。
コンクリートなので、ネジ留めはしにくいです。
なので100円ショップで、熱で溶かしてくっつけるフック、というものを買ってとりつけてみました。
 |
こんな感じのもの。
(これは天井面につけています)
接着剤面を火であぶり、とろけたところをぎゅっと押しつけて接着するというものです。
|
このフックが両端に来るようにして、間には棒をしばりつけて、とりあえず何かハンギング出来るようになりました。
ところが、台所の壁に使われていたのは、防汚加工のしてある壁紙。
(そういえば、油汚れなども、洗剤を使えばよく落ちます)
接着剤もくっつきにくいようなしくみです。
何度もポロン、とはがれてしまい(フックに引っ掛けていたものもガラガラと落ちた)、諦めました。
どうしたものか。
世の中に私のような希望を抱いている人は絶対いるはずで、それに応じた商品も開発されているはずですよね。
ただ、名前が分からない。
で、通販雑誌を念入りに見ていたら、突っ張りラックというものがみつかりました。
 |
突っ張りラック、壁面ラック、という言葉で検索すると色々と出てきます。
壁際に棒を突っ張らせて、その手前にはスノコ状の板がある、という構造のものです。
(すみません、写真は借り物です)
これを買っちゃおうかな?
でも、とても汚れる台所だし、まずは試してみたいだけだし、お金はあんまりかけたくない・・・。
|
手当たり次第に検索すると、この突っ張りラックに類似したものを、自分で作っている方のブログをみつけました。
使うのは、ボルトの先っぽに「足」がついたアジャスターと、その受けになるもの(ナット的なもの。アジャスター金具というようです)。
(こんな金具が存在することも知りませんでしたし、名前も知らないので検索しようがありませんでしたが、なんとかたどり着けて、ネットってすごい!)
もしくは、2x4材にすっぽりかぶせる、ピラーブラケットというものもあります。
 |
これがアジャスターとアジャスター金具。
つっぱり装置が自分で作れてしまいます。
|
 |
こちらがピラーブラケット。2x4材にはめこんで使うものです。
ひとつ2000円近くします。
使用例は例えばこちら。
|
ビラーブラケットは簡単そうですが、ちょっと高価なのと、2X4材限定なのが悩みどころ。
厚さ2インチは約5cm。ずいぶんごっつい木材です。
1x4材(厚さ2.5cm)くらいの、薄べったい、ちゃちなものでいいのだけれど・・・・・。
チャレンジするなら、アジャスター方式かな。
もしくはもっと原始的な方法・・。
台所は、床も壁も梁も、しっかり固いコンクリートです。
キッチリの長さの木材を押し込んで、更にくさびを打ち込めば、固定されるのではないかしら?
まずは原始的方式を試して、切り間違えたり、うまく行かなかったら、もう少し短くカットして、アジャスター方式にしてみよう。
2.5mの1x4材2本とパーツを購入し、階段で10階まで持って帰ってきました。(木材が長いのでエレベーターに乗れなかった)
固定の補助にするため、超強力両面テープも買ってみました。(とっても高価でびっくり!ピラーブラケットが買えてしまったかも!?)
最終的には、こうなりました。(むさ苦しい写真が続きますがご容赦を)
 |
1x4材には両面テープも貼って、壁とくっつけてあります。(巾木はそのまま)
板がわずかに反っていたので、丸まっている猫背の背中側を壁におしあてて、むりやり「気をつけ」をさせている向きにしてみました。
|
 |
上端は、くさび。
入るだけ押し込んで、打ちつけました。
いずれガタつきが出てくるだろうから、その時打ち込み直そうと、短く切らずそのまま。
|
 |
棚をつけてみました。
(棚板は、クロゼットリフォームに使った羽目板)
この下にも棚板が2段あります。
|
 |
下の方にはバーを。
スプレーボトルなどを引っ掛けておくのに丁度いいようです。
(左のボックスは拭き掃除用ボロ布入れとしてIKEAで買ったものなのだけど、サイズがいまいち。もう少し大きいものが欲しいな・・)
|
実はこの工作をしたのは、数年前。
多分すぐ壊れるだろうからと、ブログ記事にするのは様子見にしていましたが、意外にもまだ壊れません。
もはや、いつ作業したのか思い出せません。
2013年の夏に、間仕切り破壊工事を父とやったのですが、その時、父に「あたためフック+金属棒」の状態を見られた気がします。
(で、「何とかならないの?」(あんまり格好良くないねえ)、という反応だった記憶が)
ということは、2013年より後で、去年じゃないから、2015年頃までの間。
(クロゼットの羽目板張り作業は2015年で、その余り材をこの棚板に使っていますが、それより前にこの突っ張り構造は出来上がっていたはず)
オシャレとはほど遠いですが、自分なりに使いやすくなってきている記念として、記事にしておきます。