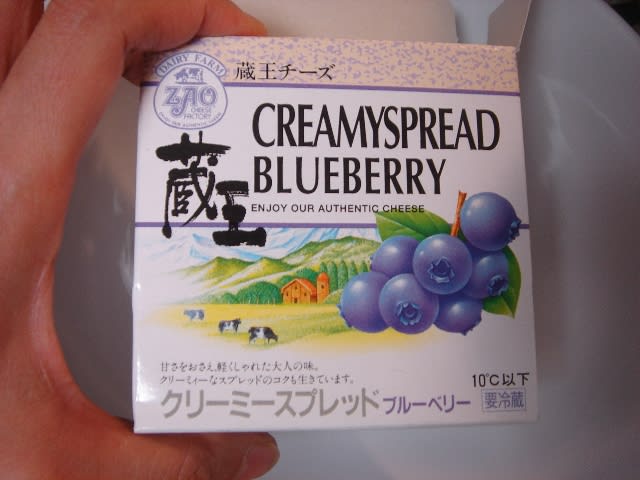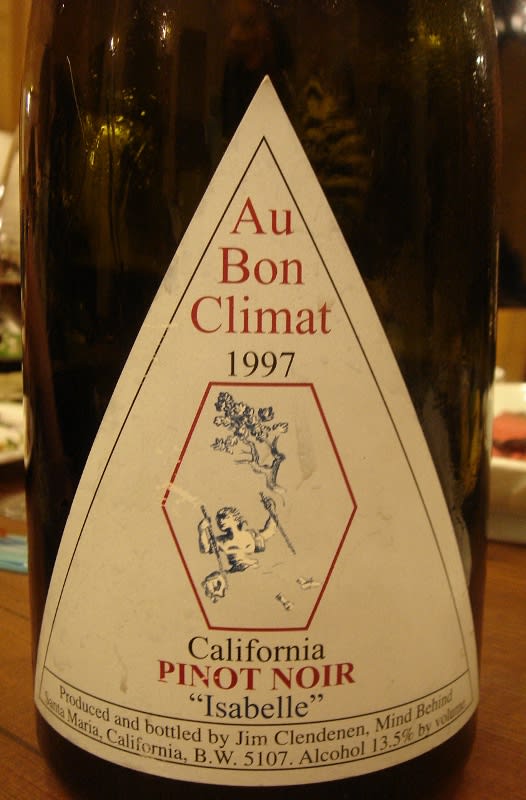【年越しパーティーシリーズ】
年越しパーティ―:12/31夜(前編)(前菜・魚料理)
年越しパーティ―:12/31夜(中編)(肉料理)
年越しパーティ―:12/31夜(後編)(デザート・お酒)
年越しパーティ―:1/1昼(前編)(朝の軽食と、午前の部前半)
年越しパーティ―:1/1昼(後編)(午前の部後半)
年越しパーティ―:元旦のティータイム(おめでたい和菓子)
○
年越しパーティー:グラスフュージング(道具)(グラスフュージングの作品例と材料)
年越しパーティー:グラスフュージング(作品その1)(みんなの作品;箸置きスタイル)
年越しパーティー:グラスフュージング(作品その2)(みんなの作品;自由なスタイル)
年越しパーティー:グラスフュージング(作品その3)(みんなの作品;自由なスタイル)
-----------------------------------------------------
元旦の昼下がり、お茶とお菓子のあとは、グラスフュージング大会です。
グラスフュージングとは、ガラスとガラスを加熱によって溶着させる技法です。なんと紀元前からある技法なのですが、吹きガラスの発達にともなって衰退しつつありました。が、近年、美しい色板ガラスの開発で、再び見直されてきたそうです。
検索してみると、アクセサリーのような小さな作品から、お皿などの食器サイズ、そしてステンドグラスや欄間まで、各種の作品が作られているようです。
例えばこちらを参照してみて下さい・・・
・フュージンググラス教室もある「るりいろ工房」の
HP ・アクセサリー工房「glass pada」の
HPガラスを焼くというと大変な装置が必要そうですが、小さなものであれば、家庭用(単機能)電子レンジと小さな炉(キルン)を使って焼けるのです!ビックリ。
わらびさん・ふみえさんが電子レンジ(2台)、専用釜、カラスのパーツ、ピンセットなどなど各種道具をセッティングして下さいました。
まずはわらびさんから簡単なレクチャーがありました。
(作業手順)
・板ガラスの上に、好きなパーツをピンセットで配置してまずデザインする。
・デザインが決まったらそれぞれのパーツをエタノールでよく拭く(焼き上がった後の曇りの原因になる)。
・拭いた部材に仮止め用ボンドをつけ、再びピンセットで配置・接着する。
(気を付けること)
・5cm以内の大きさ(電子レンジ用釜の直径にあわせて)
・板ガラス2枚に模様を挟むスタイル、または、板ガラスの上に模様を乗せるスタイルどちらでもよい。
・最終的に、板ガラス2枚程度の厚みがあった方が焼成中に割れたりしにくい
・材料はみなガラスなので、ガラスの粉やエッジに気を付ける。
・(今回は用意して頂いた材料を使うので問題ないが)ガラス素材はメーカーによって膨張率が違うので、別メーカーのものを組み合わせないこと。
主なメーカーは、ブルズアイ(アメリカ)、アーティスタ(ドイツ)、スペクトラム(アメリカ)、ウロボロス(アメリカ)。わらびさんはブルズアイ(だったかな?)で統一していらっしゃいます。
・・・と書いてもさっぱり分からないですよね。
まずは先生(わらびさん・ふみえさん)のお手本作品と、道具をご紹介しますね。
みなさんだったらどんな作品を作るでしょうか。
生徒達(パーティ参加者のみなさん)の作品は、次の記事でご紹介します。
(写真はクリックすると拡大します)

|
今回のパーティでも大活躍だった箸置きです。
長方形の模様入り台ガラスの上に粒状のガラスを載せ、(比較的軽く)焼いて接着させたものです。 |
こちらはお皿。
上の箸置きは、粒状の盛り上がりを残す手法でしたが、
こちらは模様がお皿の面にすっかり埋まり込んでいます。
溶ける、というガラスの性質ならではですよね。
黒い円盤形のガラスに、オレンジやラメの板ガラスを乗せ
てあるのだと思います。
|
表面が平ら、ということは、一番上に透明板ガラスを乗せているのでしょうか。
一度焼いて全てのパーツを溶着させ、ゆっくり冷まし、更にお皿型にするために、もう一度専用の型に乗せて入れて熱を加えてお皿のくぼみを作り、またゆっくり冷ます、という手順ではないかと思います。このような大きな作品は、通っていらっしゃる工房の、焼成用大型電気炉とゆっくり冷ますための高温庫(正式名称はなんというのでしょう)を使われたのだと思います。 |

|
小さいペンダントサイズの作品です。どうぞ拡大して見て下さいね。
とても複雑なデザインで、一体どうやって作ったのかさっぱり分かりません! |

|
トンボのように具象的な模様もいいですよね!
でもこれはベテランのわらびさん・ふみえさんの作品なので、私のような初心者は、こんなレベルを期待してはいけません・・・。うむうむ。 |

|
さて、材料をご紹介します。
これは台となる板ガラスです。これをもとに、各自の好みの大きさ、形にわらびさんがカットして下さいました。
「先生~、これ~」とみんなが押し寄せて、昔の美術の授業を思い出しました。 |

|
透明な板ガラスに、予め模様が入っているものもあります。
|

|
不透明な色ガラスもありますね。
|

|
右側は、模様として使う粒状のガラスです。
このパーツはなんと手作りなのですよ!
板状のガラスを細かく砕き、それを一度焼くとこのような、水滴が丸くなるように、こんな風なコロコロと可愛い粒状のガラスが出来上がるのです。 |

|
とっても綺麗・・・。
このままでおはじきとして使えそう(ちょっと小さいか)。
大きめの粒は、完全な球体にならず、ややいびつなまるっこさで、それもまた可愛いです。
瑪瑙のように筋の入っている粒は、板ガラスを2枚重ねて溶着し、それを割って焼いて粒状にしてあるのではないかと思います。 |

|
これはきっと高級な部材だと思います。ヴェネツィアングラスの文鎮の中にこういうものが入っていますよね。
金太郎飴のように長い棒状のものを購入し、短く切って焼いてあるのだと思います。
|

|
透明ガラスに、キラキラしたラメがかかっています。
|

|
黒いガラスに、多色使いの箔模様が入っている、シックな素材もあります。これはと~っても高級なガラスなのだそうです。
真ん中の細長いものがカットした状態。左下はそれをさらに細かくし、粒状に仕上げてあります。 |

|
高級素材はやはり、キラキラ輝いて綺麗・・・・。
|

|
上の高級素材を、つぶつぶに加工したものです。
|

|
これは、ダンナサマが撮影していたもので、「ザクザク」という道具だそうです。
ガラスを挟んで細かく割るものだそうです。ザクザク音がするからこんな名前だとか。にゃるほど。
その細かいものを少し焼いて、ツブツブのパーツを作るのかな。 |
さて、どんな作品が出来るかな?