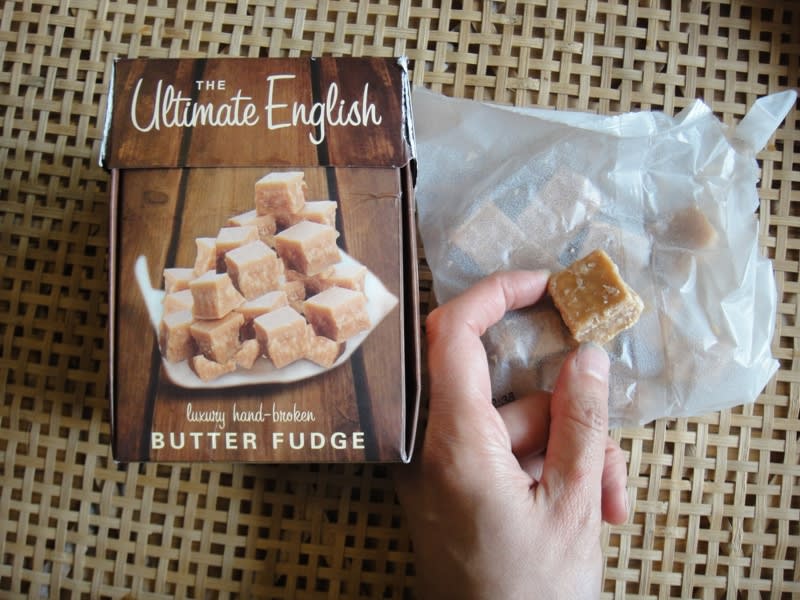今年はMy畑のニンニクが割とよく出来ました。
原因は、不明。
去年は全然ダメだったのに何故だろう。
リン酸系肥料をしっかりやっておいたのがよかったのかな?
来年につなげたいものだけれど・・・。
畑のものは、豊作なら豊作で、後が大変です。
お店で売られている状態にするまで、かなりの手間とコツが必要なのです。
(スーパーに並んでいる農産物ひとつとっても、実は最新の技術と研究の賜なのだなと実感します)
ニンニクの収穫後は、乾燥がポイント。
畑友の話を聞くと、折角の大豊作の年、乾燥に失敗してしまい大半を腐らせてしまったことがあるとか。
も、勿体ない!
プロは専用の乾燥場所を使うなど先端技術を導入していますが、家庭菜園の場合は特別な道具もないし、なるべくシンプルな作業に留めたいですよね。
今年は要領が分からず、ベランダで何度も並べ直したり、皮を剥いてみたりなど、心配でいじり回していましたが、なんとなく方向性が見えてきたので、来年のため整理してみたいと思います。
■■ニンニクの収穫とその後 (試行錯誤中)
■ニンニクの収穫
・葉っぱの大半が黄色くなってきたら収穫時期。
茎のつけ根がやわやわに腐って、引っ張って抜こうとすると千切れてしまうものは畑におきすぎだが、これらも勿論食べられる(完熟ともいえるかも)。
・販売用ニンニクの場合、底部が「水平」ならば適期、根っこ側が出っ張っているならば未成熟、玉がふくれて根っこが窪んでいる(そして先端がぱっかり開いている)場合はやや適期を過ぎているという指標がある。
しかしこれは、形が規格外になってまうし、この後の根切り作業の際に不便、という営業上の理由が主だと思われる。
家庭菜園の場合は未成熟で収穫するよりも、充分成熟させた方が後悔がないと思います。
・大きいものから収穫し、小さいものはもうしばらく畑におく、という手もあるかも。
■収穫後
・畑でまずしばらく、根っこの土が払える程度に乾かす。
(2011年は6/20に全部引っこ抜き、翌日持ち帰りました)
持ち帰る際には、なるべく土をよく払う。
・収穫後、しばらく畑で放置して乾かすという手もある。
抜いたあとは、玉をマルチの上に乗せておかないように要注意。必ず土の上におく。
天候がよい場合はマルチが非常に高温になり、ニンニクが「煮えた」状態になる(経験有)。
煮えてしまうと、表面から見ると皮が緑色になり、剥くとニンニクが飴色っぽくなっている。
私は、畑にずっと置いて葉っぱが枯れ腐っていくのがあまり好きではないので、基本的に早めに持ち帰る方針です。
このあと三つ編みニンニクを作りたい場合も、葉を腐らせないために、畑から早めに持ち帰る方がよいです。
・葉っぱはそのままにして、持って帰ってベランダの床に並べる。
葉っぱをつけておくことで葉からの蒸発散を期待し、この後の乾燥を速やかに進めようという目論見(自己流だけど)。
この後、なるべく扇風機の風をあて続ける。
・なるべく持ち帰った日のうちに、玉の上10cmくらいよりすぐ上から上側に向かって、茎を切り裂くようにタテに切り目を入れる。この時珠芽があれば、軸ごと折り、それを包む「皮」も含めて取り除く。
珠芽を包む皮は腐りやすいので要注意。
ニンニクの表面や茎を包む皮は、乾いてしまうとカサカサパリパリだが、実は大変に乾きにくい。
可及的速やかに乾かさないと、腐敗やカビ・変色の原因になるので、幾層にも皮が重なって湿っぽい軸は切り開くとよい。
傷んでいないニンニクは、お腹が減ってしまいそうないい匂いだが、皮が腐ったりなど傷みがあると悪臭になるので、変な匂いがしたらよくチェック。よけておきすぐ使うか、粒にバラして干すなど注意する。
なお、皮の一部が腐っているくらいならば、基本的には玉には影響はない。
・根切り作業。
タマネギはもしゃもしゃした部分を刈り込むだけですが、ニンニクの場合は根のつけ根の盤茎を切り取ることが多いようです。
これをすることで底部からも乾燥が促進されそうな気がするので、私も真似しています。
西洋では必ずしも盤茎を切り取る文化はないようですが、ニンニク収穫時期の気候が全く違うからではないかな。
日本の高温多湿さはおそらく桁違い・・・。
玉が太って根のところが窪んでいるものは、玉を傷つけないように気を付ける。
玉を傷つけるおそれがある場合は、無理に盤茎ごと切る必要はないかも。
この段階くらいまで、ベランダに平らに並べ、扇風機で風をあてる。
・根切りが終わり、葉っぱがすっかり変色してカサカサになってきたら、束ねて更に干す。
2週間程度、扇風機をたまにあてながら、干し続ける。
(風通しよく平らにおいておけるのであれば、束ねない方がいいかも。
でも場所ふさぎなので束ねたいですよね)
なお、玉を上にしてぶら下げるのはよくないです(ニンニクの茎に住む虫は上に進む性質があり、迷走して玉をかじってしまうため)
・軸部分を持ってみて、しっとり感がなくなり、よく乾いてきたら、軸上部を切り取り、いわゆるニンニクの形にする。表面の薄皮を一枚剥くと、真っ白で格好いい(売ってるみたいな)ニンニクになりそう。
そうだ、折角葉っぱごと持ち帰った訳なので、三つ編みニンニクに挑戦しちゃおうかな?
それほど沢山ないので、何十個も束ねた立派な三つ編みは無理だけど、最低3個でも出来るはずよね??
切り取った枯れた茎葉は、畑に戻す。
ニンニクの匂い成分は防虫効果もあるというし、例えばズッキーニの周りに敷いておくというのはどうかな・・・・。
■保存
・当分は束ねて風通しのよい冷暗所に吊しておく。
・紙袋に入れて冷蔵庫に入れてもよい。
(ビニールは蒸れてカビの原因になるので不可)
2018.5追記:ニンニクは冷蔵すると芽が出やすくなるので、長期の冷蔵保存はおすすめしません。常温のキッチンに吊るして、なるべく秋頃までに使い、冬と春の分用には念のため冷凍や乾燥を準備しておくのがいいです。(生でも春頃までもつものも幾つかはあるけれど、どんどん芽が出たりフカフカになってしまったりして歩留りが悪いです)
・たとえ収穫直後からずっと冷蔵庫にいれておいても、冬には芽が出てきてしまう(経験有)。
11月頃までには調理加工して適宜保存、もしくは粒のまま冷凍がおすすめ。
(追記)収穫直後の乾燥をきっちりやると、吊しておいても保存性がいいような気がする。
・ニンニクを沢山使う加工品とその保存
バーニャカウダソース(冷凍)
ニンニク醤油漬け(冷蔵)
韓国ダレ(醤油・おろしニンニク・ニラ又は葱・ゴマ・胡麻油・粉唐辛子)(冷蔵)
バジルペースト(冷凍)
エスカルゴバター(バター・ニンニク・パセリ)(冷凍)
・生をそのまま冷凍する場合は、粒にばらし、皮つきで冷凍。冷凍庫から出して1分くらい経つと簡単に皮が剥けます。
スライスして冷凍も出来るが、霜がついて合体してしまいやすいし、粒のままでも数分おけば解けて包丁が入れられるので、粒ごとがおすすめ。
・皮むきの手間はありますが、よく使うサイズ(みじん切り、スライス等)に切って瓶に入れ、オリーブオイルを完全に浸るまでたっぷり注ぐ。この状態で冷蔵または冷凍もおすすめです。冷蔵するとオリーブオイルは固まるので、調理を始めたとき、きれいな菜箸でニンニクとオイルをお箸でフライパンに取出し、炒め物などを開始する、という手順。
■■畑友の収穫作業(三つ編みを作らない場合)2018.5追記
畑友は、軸をカットしてコンテナで保存する方式なので、次のような方法で収穫作業をしているそうです。
・ニンニクを掘り上げ、畑の土の上に置いておく(マルチの上は不可。熱で煮えて傷んでしまう)
・かなり長めに畑で乾かす。途中雨が降ってもまた晴れるので気にしない。
・軍手でこするだけで表面の皮が剥けるくらいよく乾いたら、回収作業。
・畑にて、剪定ばさみ的なものを持って、軸を短くカット、そして根っこを丸刈りみたいな感じで短くカット。表皮のパリパリ落ちる部分をこすってきれいにする。
・これらをまとめて畑から持ち帰り、通気性のあるコンテナで保管
茎葉をつけたまま、畑の直射日光下でよく乾燥させ、残渣(切り落とした茎葉、根っこ、土のついた表皮など)は畑で処理して、持ち帰る分量は最小限に、家ではゴミを出さない、という、とっても合理的な方法です。(この方法に至るまではいろいろ試行錯誤されたようです)
■■プロの作業手順
●収穫・乾燥
・葉が30-50%黄変し、球の盤茎部とりん片の尻部がほぼ水平になった時期に収穫。
・収穫と同時に茎部分、根をカット(根は出荷前にもういちど整えるようです)
手作業というサイトも見ましたが、栽培規模によっては各種機械を使って作業するようです。
(茎葉刈払機、マルチ巻取機、収穫機、整列茎根切機・・・など。)
・機械で強制的に乾燥。35度程度。
温度設定は、高すぎるとニンニクが煮えてしまい低すぎると腐敗するので、プロでも大変気を遣うようです。
・乾燥直前の球重量に対し30~35%減量した時点で、盤茎部に爪が立たない状態で乾燥終了。
建築用水分計を活用すると、乾燥終了の判断の参考にできる。
乾燥期間は概ね2~3週間程度。
●調整(出荷前に綺麗にすること)
・茎を1.5cm以内に切断し、表皮を1~2枚剥いで根を完全に除去する。
出荷規格に従い、1kgネット詰めか小袋詰め。
●貯蔵
・農家保管で萌芽や発根を抑えられる限界は一般に10月位まで。出荷はそれまでに行う。
・11月以降長期保管しながら出荷していく場合は、JA等の-2℃冷蔵庫に乾燥終了後直ちに保管。
この場合、2月出庫までが目安。
・3月以降まで出荷を行いたい場合は、-2℃冷蔵庫から出庫後、熱処理を行う産地が多い。
熱処理は冷蔵よりさらに萌芽発根を抑える効果がある、処理温度や処理時間によっては障害が発生する場合があるので指導機関に相談する。
■参考情報
みんなの農業広場 ニンニクの作業体系
ニンニクの栽培方法 個人の方のブログですが大変よくまとまっています。参考サイトへのリンクも多数
青森県田子町のニンニク収穫風景
根切りしたニンニクの写真(千葉の農家さんのブログ)
ニンニクの出荷前の調整のようす
ニンニク作業(根切り等)専用の、刃が湾曲した包丁 青森ではこちらが主流だとか (刃物で有名な岐阜県関市の河合のこぎり店のHP)
ニンニク作業用の剪定鋏スタイルのハサミ 山形のスタイルはこちら (山形の花楯産業のHP)
ニンニク包丁を買った方のブログ記事
三つ編みニンニク garlicbrade の写真(英語サイト) 根はもじゃもじゃ部分を刈り込んであるだけです
盤茎つきのままの三つ編みニンニクの写真(英語サイト) こちらでもニンニク収穫の話題が。
これは珍しい、裏側から見た三つ編みニンニクの写真
ほかにも、garlicbraid で検索すると写真色々出てきます。
(追記)
■My畑のニンニク関連記事
●2011年
ニンニクの珠芽について
うちの品種は花が咲くのではなく、こぶ状のむかご(珠芽)が出来るタイプだということが分かりました。
収穫とその後の処理 (この記事)
試行錯誤中。翌年、もっとよい乾燥方法(茎に切り目を入れる)を思いつきました。
三つ編みニンニク
初めて挑戦。可愛くできました。
●2012年
収穫・乾燥
茎に縦に切り目を入れて干したら、すごく乾きやすくてよかったです。
乾燥方法再考
干し方は、玉を上にして吊すと問題があるということが分かり、玉を下に干すようにやり直しました
珠芽を植えたものの収穫
珠芽からもちゃんとニンニクが出来るということが分かりました。
三つ編みニンニク作り
前年とは玉の配置をちょっと変えてみたりもしました。
かなり力はいるけれど、可愛いものが出来るので好きな作業です。
ニンニク保存
スライスを干してニンニクチップに。また微塵切りをオイル漬けにしました。
他にも保存方法のアイデアをまとめました。
●2013年
4月頃、葉っぱが青々
今年は小粒の鱗片や珠芽も沢山植えてみました。どうなることか、楽しみです。