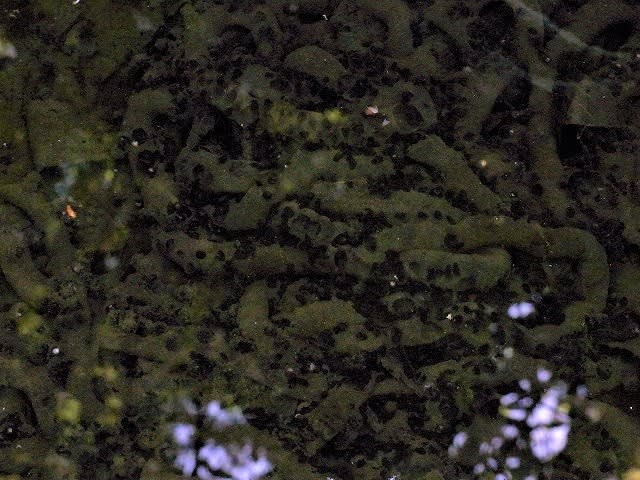シロヤブケマン(白藪華鬘)
<ケシ科キケマン属>
ムラサキケマンの花の白色の花の事を、シロヤブケマンと言う。
ここ、「クロスケの家」付近では、殆どがムラサキケマンでは無くて、
このシロヤブケマンが多い。
葉は2~3回羽状に細かく裂ける。
花序は直立し、花茎の上にたくさんつく。
チゴユリ
チゴユリ(稚児百合)
<イヌサフラン科ホウチャクソウ属>
小さくて可愛い百合に似た花を、稚児(小さな子供)に
例えて名づけられた。
明るい林床や草地に生え、以前はユリ科だったが、
近年、イヌサフラン科になった。
スズメノテッポウ
スズメノテッポウ(雀鉄砲)
<イネ科スズメノテッポウ属>
穂を抜きとつて、葉を折り返し息を吹きかけて皆さん、
上手に草笛を吹いていました。
まっすぐな花の穂を鉄砲に見立てた。
休憩
クロスケの家のトトロ
オタマジャクシ
★昆虫コーナーは、たぶんシオヤトンボ
水田の上をキラキラ翅を光らせながら飛んでいた。
シオヤトンボ(塩屋蜻蛉)
<トンボ目トンボ科>
成虫で飛び回るのは、4月~7月まで、
春から夏にかけてよく見られるが、活動期間は短い。
平地の沼や池,水の張った田んぼに発生する。
俳句は季語蝌蚪(かと)
蛙の子・お玉杓子(おたまじゃくし)・蝌蚪の紐(かとのひも)
などと使う。
蝌蚪ひとつ諸行無常と手を出せり 江 ほむら






















































 ミミガタテンナンショウ(耳型天南星)
ミミガタテンナンショウ(耳型天南星)