 21カ国の地域が参加するアジア太平洋経済協力会議(APEC)は昨日(20日)首脳宣言を採択して閉幕した。宣言では、イギリスのEU離脱や米大統領選挙結果などを念頭に、『自由貿易が格差を生むという懸念を払拭するため、社会のあらゆる階層に働きかける必要がある』というものであった。
21カ国の地域が参加するアジア太平洋経済協力会議(APEC)は昨日(20日)首脳宣言を採択して閉幕した。宣言では、イギリスのEU離脱や米大統領選挙結果などを念頭に、『自由貿易が格差を生むという懸念を払拭するため、社会のあらゆる階層に働きかける必要がある』というものであった。としながらも、冒頭で『不平等や不均衡な経済成長による不確実性の高まりが、グローバリゼーションに疑問を投げかけ、保護主義の台頭を促している』と、極めて的確な指摘もしている。
自由貿易とは新自由主義の核心の一つで、国内的には小さな政府を目指し政治の介入を極力なくし、経済活動は市場原理に任せるというものである。因みに、アベノミクスは市場に介入する大きな政権そのもので、新自由主義は政権奪取に主眼を置いた極右思想が選択したツールといえる。安倍晋三は経済政策に全く興味がないか無知でしかなく、政策上大きな矛盾を抱えているといえる。
何の制約もない経済競争なら、大きな資本がか必ず勝つ。市場原理は弱者を叩くのが原則である。弱きをくじき強きを助け、自らが弱きものにならないよう、懸命に経済活動をするのが原則である。敗者が際限なく生まれるシステムともいえる。新自由主義は大量の敗者を吐き続け、格差社会になるのは避けられない。敗者の存在が市場経済に刺激を与え、勝者を目指す妄想が競争のエネルギーとなる。それが新自由主義である。
翻って、政治とは税金を介した富の再配分をすることが最大の命題てある。少なくとも、近代の政治史は手法や理念に違いはあっても、総じて富の再配分を政治がやると宣言してきた歴史ともいえる。
自由貿易は格差を生むのは当然の結果である。経済成長が人類にとっての命題ではない。経済成長は際限なく続くものではない。APECは反対者を、”ホゴシュギ”と忌み嫌う集団催眠術にかかる制度である。










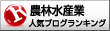

 写真は9月に起きたJR北海道根室線の新得で起きたものである。大雨で線路が流出して、いまだに復旧していない。バスので乗客を繋いでいる。北海道では札幌、帯広・釧路を結ぶ大動脈である。数少ないドル箱路線でもある。日高線(鵡川ー様似、116キロ)は昨年1月の高波に洗われて復旧のさ中に、9月の台風の被害で普及費が倍の86億円にもなっている。広大な北海道の鉄路は、天災の直撃を受けることが少なくない。
写真は9月に起きたJR北海道根室線の新得で起きたものである。大雨で線路が流出して、いまだに復旧していない。バスので乗客を繋いでいる。北海道では札幌、帯広・釧路を結ぶ大動脈である。数少ないドル箱路線でもある。日高線(鵡川ー様似、116キロ)は昨年1月の高波に洗われて復旧のさ中に、9月の台風の被害で普及費が倍の86億円にもなっている。広大な北海道の鉄路は、天災の直撃を受けることが少なくない。 JR西日本は今日(1日)、島根県江津市と広島県三次市を結ぶ三江線の廃止を沿線6市町に表明した。利用者数の低迷が理由で、今月末までに国土交通省中国運輸局に廃止届を提出する。早ければ来年9月に廃線となる。
JR西日本は今日(1日)、島根県江津市と広島県三次市を結ぶ三江線の廃止を沿線6市町に表明した。利用者数の低迷が理由で、今月末までに国土交通省中国運輸局に廃止届を提出する。早ければ来年9月に廃線となる。 昨日は渥美清さんが亡くなって、20回目の命日であった。放送各局は渥美清の特集をたくさん組んでいる。渥美清と言えば、男はつらいよのフーテンの寅こと車寅次郎が殆ど重なって見える。若いころは、プロデュース永六輔の”夢であいましょう”というNHKテレビのバラエティー番組で、渥美清を見ていた。男はつらいよシリーズは、ほとんど劇場では見ていない。20作以降と思うが何作か見たような気がする程度である。テレビの放送では何度も見ている。全作品を3度以上は見ていると思う。懐かしく思いおこされることが少なくない。
昨日は渥美清さんが亡くなって、20回目の命日であった。放送各局は渥美清の特集をたくさん組んでいる。渥美清と言えば、男はつらいよのフーテンの寅こと車寅次郎が殆ど重なって見える。若いころは、プロデュース永六輔の”夢であいましょう”というNHKテレビのバラエティー番組で、渥美清を見ていた。男はつらいよシリーズは、ほとんど劇場では見ていない。20作以降と思うが何作か見たような気がする程度である。テレビの放送では何度も見ている。全作品を3度以上は見ていると思う。懐かしく思いおこされることが少なくない。
 45人もの殺傷事件(うち19人死亡)が神奈川県の障がい者施設で起きた。戦後最も多い凄惨な殺害事件と言える。大麻をやっていたとかいろいろ報道はあるが、大森衆議院議長に殺害予告を送りつけている。障がい者は社会悪で家族への負担が大きく抹殺すべきというのである。人々の感情のわずかなスキに、大きなくさびを入れて広げるのである。
45人もの殺傷事件(うち19人死亡)が神奈川県の障がい者施設で起きた。戦後最も多い凄惨な殺害事件と言える。大麻をやっていたとかいろいろ報道はあるが、大森衆議院議長に殺害予告を送りつけている。障がい者は社会悪で家族への負担が大きく抹殺すべきというのである。人々の感情のわずかなスキに、大きなくさびを入れて広げるのである。 国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は今日(10日)、タックスヘイブンの利用実態を暴いた「パナマ文書」に関し、約21万社のペーパーカンパニー名をホームページ上で公開した。これはパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」の約40年分の内部資料である。わずか一社の資料なのであって、秘匿性が高く世界の企業家や金満家が税逃れのために、実体のない会社ペーパーパンパに―を作って利用している。
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は今日(10日)、タックスヘイブンの利用実態を暴いた「パナマ文書」に関し、約21万社のペーパーカンパニー名をホームページ上で公開した。これはパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」の約40年分の内部資料である。わずか一社の資料なのであって、秘匿性が高く世界の企業家や金満家が税逃れのために、実体のない会社ペーパーパンパに―を作って利用している。









