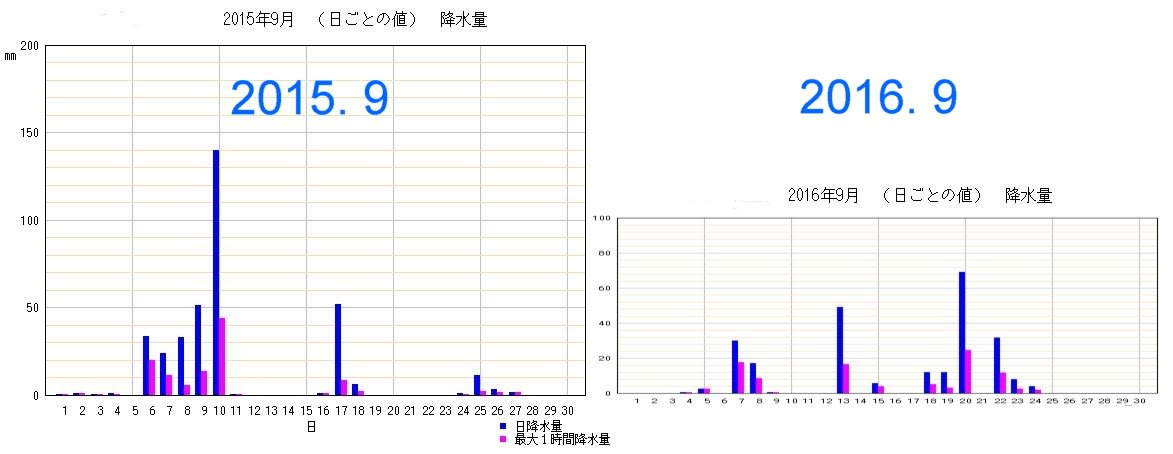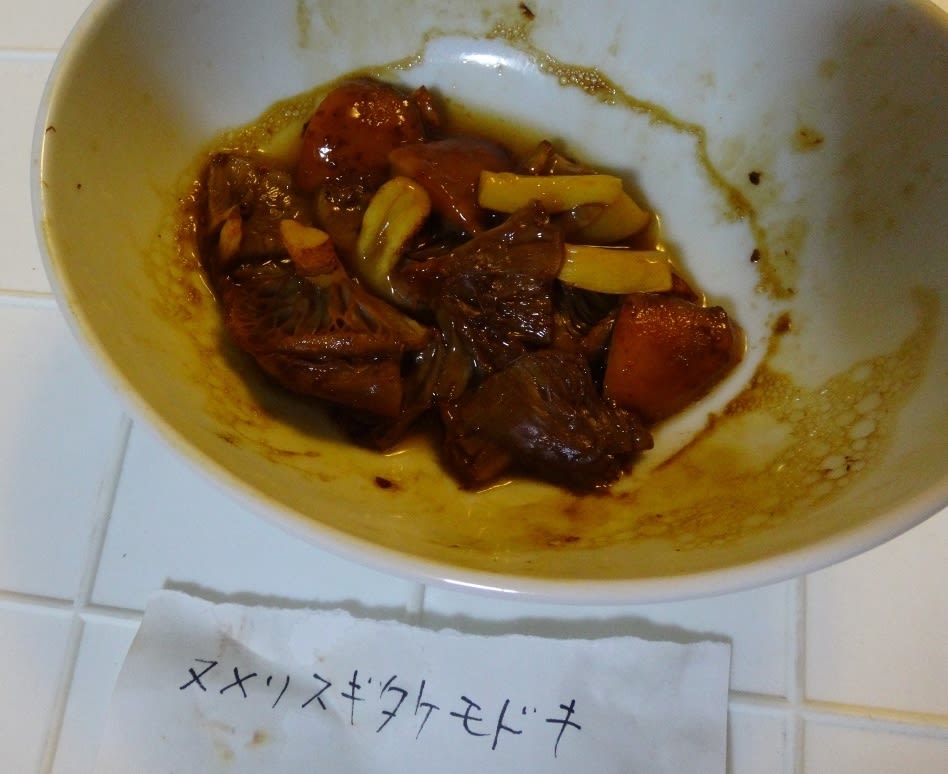先日の連休、お友達5人と富山・岐阜方面に、2泊の旅行に行ってきました(誘って下さってありがとうございました)。
22日は、miyakoさんに案内して頂いて、ナメコ・ムキタケ狩りに連れて行って頂きました。
miyakoさんは、晩秋はほぼ毎週末のようにきのこ狩りに出かけるのだそうです。
わらびさんご夫妻、duckbillさんご夫妻と私の5人で、miyakoさんのナワバリを案内して頂きました。
北陸の山の中なので、どんなに寒いかと恐れておりましたが、ここのところのあたたかさは北陸にも及んでいて、雲は多めでしたが寒さはそれほどでもありませんでした。
車に乗りながら、「あっ、あれ! あの枯れ木にムキタケ出てますね。ああ、こっちの木にもナメコが。」とmiyakoさんが実況中継して下さいますが、私にはさっぱり見えてきません。
まずは手取り足取り、探し方を教えて頂きました。
●なめこの探し方①
・枯れ木を捜す。
この時期、生きている木でも、葉っぱは全部落ちてしまっていますが、枯れ木は、枝先端が細い枝がついていない(枯れ落ちている)ところから分かる。ただし、樹皮がついていない程腐ったものはダメ。
・幹にぽこぽこと何か出ていないかチェック。
ムキタケは大きなものもあり、結構分かり易いです。
ムキタケと同じ木に、ナメコが出ていたりします。
幹の根元付近までチェックして、下の方まできのこが出ているようならば、ライバルがまだ採っていないということ。
大抵は、誰かが既に収穫してあり、ずっと高いところに残るだけになってます。
 |
(写真の向きが変ですが)中央がきのこが出ている枯れ木。
先端には小枝がなく、幹がキノコでぼこぼこしているのが分かるでしょうか。
|
 |
こういうのがムキタケ。
これらは全体が茶色くなってしまって既に育ちすぎですが、ほどよい大きさのものはヒダ側が白いです。
|
 |
これは丁度良い若さのムキタケ。
木の幹から引き剥がすように収穫します。
|
はじめのインストラクションを受けたのは、灌木もチクチクしているし結構急な坂でした。
ひゃー、なめこ採りって大変だ~と思いましたが、これはまだ足慣らしでした。
少し移動して、それはもう、すごい急斜面の場所に。
「ここ登ってみましょ~う。」
「は~い(ひええぇぇ)。」
各自斜面にとりついて、きのこを探索。
この斜面がものすごいです。
もちろん道などはない、単なる山の斜面。
じっと立っていることも無理なくらいの急斜面なので、葉を落とした灌木(クロモジ)の枝につかまりながら、足というよりむしろ手に力を入れて、少しずつ進みます。
つんつんした灌木の枝に髪の毛やら眼鏡やらひっかけながら、めげずに前進。
(途中眼鏡をはじき飛ばされて、結構ピンチでしたが運良くみつかりました)
両手両足を全部使って、手でつかむもの、足をおく場所をよくよく考えながら進むところは、木登りに通じるところがあります。
たまにズルっとズッコケルので、手で(丈夫な)何かを掴んでおくのは重要!
うっかりつかんだものが枯れ木だったりすると、「あ~れ~」とすってんころりんです。
こういう進み方は、難しいけれど面白くて、きのこ探しを忘れてしまいそうになる程(というか進むだけで精一杯)。
比較的薄着だったのに、汗びっしょりになります。
なんか爽快!
でも肝心なきのこが全然なくて、ひとまず道まで降りてきました。
急斜面は、登るのより降りる方が更にスリリング。両足ともずっこけて、両手でぶらさがってしまったこともありました。
斜面から降りてきたduckbillさんと、休憩がてら道路をてくてく歩いていたら、「あっ!」というduckbillさんの声。
●なめこの探し方②
・なめこは倒木にも生えるので、足下にも要注意。
(ムキタケは、今回は立っている枯木でのみ見かけました。倒木にも生えるけれど、比較的枯れたばかりの木に生えることが多いそうです)
・車の運転席(なめこ採りプロ達)からぱっと見えない谷底側の枯れ木も穴場。
 |
duckbillさんの視線の先、道路の擁壁のすぐ下の倒木に、わんさかとなめこが!
|
 |
大きさと成長段階の揃ったナメコ達がずららららっと☆
なめこってこうやって生えるんだ~、と感激でした。
|
 |
倒木よりもっと下の谷底にもナメコが生えている枯れ木(立木)がありました。
この木などは随分細いのですが、沢山生えていました。
(太さは発生の有無にはあまり関係ないのかも。太い方がより長い期間出てくるかもしれませんが)
同じ枯れ木に、成長段階の違うナメコが生えていることも意外でした。
これはかなり古びたナメコ。
|
 |
で、別の場所にはギリギリ食べられるくらいの若さのナメコ。
|
 |
こちらには、妖精のようなナメコベビー達。可愛い☆
|
 |
仏像の螺髪のよう・・?
|
 |
この谷底の枯れ木から、巨大なナメコが採れました。
(duckbillさんが発見!)
掌よりも大きいサイズ!
|
 |
こんなに大きくてもババじゃなくて、食べ頃なのですよ☆
すごくラッキ~。
|
●ナメコ・ムキタケの収穫方法・しまい方
・手が届くところのナメコは、ハサミで軸を切るようにして収穫。(樹皮を傷つけないようにした方が、来年のためにもよいとのこと)
収穫したなめこは、ネバネバして水分も多いので、紙箱などではなく、金属製の柄付きザルを置いておいて、そこに放り込むと便利。
・通常のきのこはビニールなどの密閉状態だと蒸れて傷みやすいが、ナメコは逆。
収穫後のナメコは、ビニール袋に詰めて、なるべく空気を抜くようにしてぎゅっと口をしばる。
水分多め・密閉状態の方が日保ちするそうです。これもまた目からウロコ。
・手が届かない場所のナメコ・ムキタケは、伸縮アルミポールにタモ網とスクレイパーをくくりつけた秘密兵器を使う(写真参照)。
この武器が大変に有効で、きのこが生えている場所に正対するように立ってこそげると、「こんころり~ん」、ときのこが網に転げ落ちてきて、感動的でした。
 |
きのこ狩り用秘密兵器。
miyakoさんが自作されたものです。
スクレイパーは、100円ショップにもありますが、ちゃんとしたものの方が切れ味がいいそうです。
このアルミポールは3段式で、とっても長くなるのですが、作ったmiyakoさん自身、この日まで2段だけだと思い込んでいたそうです。
|
 |
ターゲットとなるきのこに正対するように伸ばし、きのこのつけ根をこそげると、ころりん、と網に入ってきます。
採集マニアとしては、この道具を他の採集にも使えないかと考えてしまいました。
|
 |
手が届くところのものは、ハサミで切りながら金網のザルに。これだとなめこのぬめぬめをあまり傷つけないので丁度よいです。
中央の幼菌は、膜状のツバが綺麗に残っていて美しい・・・。
|
山を後にして車に乗り込み、さて、そろそろお昼ご飯でも・・・と移動を始めたのですが、道沿いの平地林でも、きのこの気配を察知。
車を降りて見てみると・・・
 |
ああっ。倒木にびっしり!!
でも残念ながら、わずかに時期が遅れてしまっています。
涙を呑んで、スルー。
|
 |
これも、あと数日手前だったらよかったのだけれど。
こうやって倒木から生えているものは、車からはぱっと見付けられないため、ライバルから見逃されていることも多いようです。
|
 |
完璧な幼菌も発見!
やった~。
それにしても、ナメコって、時期をずらしつつ、じゃんじゃか生えてくるものなのですね。
|
 |
木口からぷくぷくとアブクのように幼菌が。
可愛いにゃあ☆
|
ひとしきり探索して、また車に乗り込んで、さあ・・・と走り出したところでまた、「あっ」。
という感じで何度も収穫タイムがありました。
気づいたときにはもう3時近く。
みんなきのこに夢中で、お昼ご飯のことなどすっかり忘却の彼方。
道理でちょっとふらーっとした訳だわ。よく考えるとみんな空腹でした。
道の駅の駐車場で昼食を、という予定でしたが、その晩の宿に直接向かうことにしました。
宿にて、遅いランチとして鱒の寿司を食べ比べつつ一服。
その後、戦利品を山分け。
(miyakoさん、新聞紙まで用意して下さってありがとうございました)
 |
どっさり☆
大きなゴミをとったり、ダメなきのこを選り分けたりなど、あらあら掃除もしてしまいました。鱒の寿司の容器が、ゴミ入れに役立ちました。
ナメコは大きさ別に分けて袋詰めしました。
(ジップロックはduckbill家の御提供。ありがとうございました)
こういうきのこ掃除も、大勢でおしゃべりしながらやると楽しいです(常日頃、単独作業ばかりなので私には感涙もの)。あと、山歩きで疲れた後に自分で調理するのではなくて、お宿の夕食を頂けばいいだけなので、それも楽チンでした。
運動後の温泉も気持ちよかった~☆
|
初めてのナメコ狩りは、ものすごく勉強になったし、楽しかったです。
斜面よじのぼりは、エクササイズとしても好きなタイプの運動でした。
miyako先生、そして一緒に行った皆様、本当にありがとうございました!