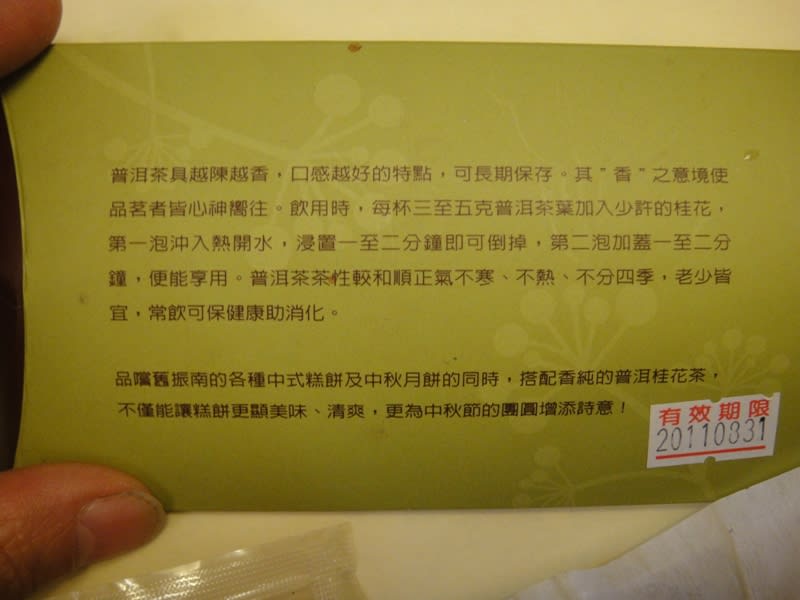台湾の若い友人(男性)は、とてもグルメです。
ビールやウィスキー、コーヒー、紅茶など、凝ってあれこれ試し、自分にとってのベストはこれだ!というものを見つけ出しているのです。
そんな彼が、最近見いだした美味しいビールがこちら。
 |
アメリカのELYSIAN醸造所のビール。 |
インディア・ペール・エールは、強いホップの苦みと高いアルコール度数(5%~7.5%)が特徴です。
大航海時代、イギリスから植民地インドにビールを送る際、アフリカ南端を迂回しても傷みにくいように、バクテリアの増殖を抑えるホップを多く加え、またアルコール度数も高くなるように作られたものだそうです。
要するに、濃くて苦味も強く、大人の味。
アバター・ジャスミンは、ジャスミンの精というような意味かな?
ジャスミンで香りづけしてあります。
コップに注ぐと、うっすら濁っているような色合いです。
瓶の下半分は、更に濁りが強め。
そして色が違うということは、味も。
なんと瓶の上半分と下半分で違う味なのです。
上半分は、すっきりしたほろ苦い味に花の香り。
下半分は、そこに甘さが加わります。花の香りとのマッチングもあって、下半分の方が美味しいとの彼の評価でした。
プロメテウスは、ギリシャ神話に出てくる神様の一人です(男性)。
神様の作業場から火を盗み、人類に渡してくれたのですが、その罰として岩にくくりつけられ、ハゲタカに毎日肝臓をつつかれるという責め苦を受けるようになった人。
彼の肝臓は毎晩再生するため、その拷問は半永久的に続いていたところ、のちにヘラクレスに解放されたようです。
プロメテウスは男性の神様ですが、ラベルはなぜか女性の火吹き芸人。なぜ・・。
ラベルに眉をひそめつつ飲んでみると、これはびっくり、驚くほどフルーティな香り。
なのに飲むと、スッキリシンプルで、ほろ苦い、男性的な味。
濃い味わいで、大変美味です。
どちらも大変に美味しいビールでした。
特にプロメテウスの方はラベルを見ただけでは絶対買わないビールなので、友人に教えて貰って良かったです。
(「それにしても何でこんなラベル?!」「アメリカだからねえ」「アメリカらしいねえ」)
エリシアン醸造所は、次々に新しいビールを出している醸造所のようです。
もし見付けたら、また買ってみたいです。
ビール好きの方、一度お試し下さいませ!
■参考情報
All About インディアペールエールについての解説
エリシアン醸造所
Avatar Jasmine IPA 解説
(生年月日を入力する必要があります。おそらく未成年の閲覧を避けるためかと。01/01/1950など、25歳以上になる年月日を適当に入れればいいと思います)
Prometheus に関するプレスリリース Beerpulse.com
2012年5月に新商品として発表されたようです。
エリシアン醸造所のサイトには今はないので、期間限定(ひと釜作って売り切り)みたいな感じだったのかもしれません。