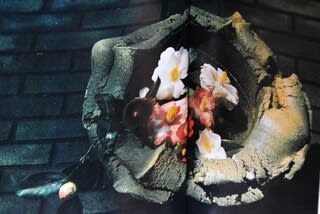日経のコラムで、FINANCIAL TIMESのラナ・フォルーハーの論文”「影の仕事」で生産性低下も”が掲載された。
労働者の生産性が(特に米国で)低下していることは現在、経済の大きな謎だが、その一つは「シャドーワーク(影の仕事)」が増えていることだ。と言うのである。
シャドーワークという言葉は、1981年にオーストリアの哲学者で社会評論家のイバン・イリイチ氏が作った。イリイチ氏の考えでは、この中には、子育てや家事など、報酬を伴わない仕事すべてが含まれる。しかし最近では、技術を駆使して企業が仕事を顧客に押し付ける事例が増えている。と言うことだが、ラナの論点は、この最後の企業のシャドーワーク押しつけによって生産性が落ちているということである。
かつては他人に任せていた数多くの作業を、今では、時間を費やす無報酬で目に見えない仕事として、ほとんどの人がデジタル機器を使って自分自身でこなしている。銀行とのやり取りや旅行予約、飲食店での注文、食料品の袋詰めなど、あらゆる作業が含まれ、駐車料金の支払いや子供の宿題の把握、テクノロジーに関するトラブル対応などに必要なアプリをダウンロードして操作する。30年までに米国の仕事の4分の1が自動化の影響を大きく受けるとの予測があり、その規模は間違いなく膨大で、しかも拡大しつつある。
こうしたシャドーワークは人間の仕事を減らし、価格の引き下げにつながるといった見方もあるだろう。確かにそうかもしれないが、経済全体としてみた場合、効率的なのだろうか。
自分のスマホに新しいアプリをいくつかダウンロードして使っているが、ある百貨店への注文で生じた問題を解決しようと数時間を費やしたり、慣れないトラベルプラットフォームを使わざるを得なくなって使い方を覚えるために時間と労力を要したり、とにかくトラブル続きの連続で、
職を必要としていて、仕事を始めたばかりの労働者のほうがはるかにうまくこなせる作業を、高給取りの知識労働者である筆者が週に何時間も費やさざるを得ないことに問題はないのだろうか。
ジョセフ・スティグリッツ氏ら一部の経済学者が、シャドーワークは市場システムにとって外部不経済(社会への悪影響)となり、企業が労働コストを削減するために使いたくなる手段だと指摘している。
ランバート氏は、シャドーワーク増加の負の影響の一つとして、サービス業で初級レベルの仕事がなくなることを挙げている。米ブルッキングス研究所が19年に実施した調査では、最も賃金が低い仕事が自動化のリスクにさらされていることがわかった。これは、特に若年層や人種的マイノリティーの生活が脅かされることを意味する。
テクノロジーの進歩に追いつくために国家が教育を改善しない限り、こうした労働者の多くは仕事に就けなくなり、生産性や経済成長の低下につながる。
一方、自動化が一層進む社会では、人と接触することが全般的にぜいたくなこととなっている。本当のお金持ちは他の人にシャドーワークを頼んでいる。
テクノロジーは「摩擦」を減らすかもしれないし、自動化やアプリは確かに、利便をもたらしている。社会全体にかかるシャドーワークのコストを計測してみる価値はありそうだ。と言う。
さて、このシャドーワークだが、これまでに何度もこのブログで言及しているアルビン・トフラーが1980年に「第三の波」で明らかにした生産消費者(Proshumer)の概念と殆ど同じである。
国民所得統計には集計されないが、販売や交換の為ではなく、自分で使う為か自分の満足を得る為に、その生活や営みを通じて財やサービスを生み出す一般消費者を「生産消費者」と称し、主婦などはその典型で、
もう半世紀以上も前にサミュエルソンが、国民所得統計の不備について言及していた。
この傾向が、ICT革命によってAIやロボティックの進展などデジタル技術の活用によって、加速度的に発展し、生産消費者、そして、シャドーワークが増加して、経済活動の重要な位置を占めてきた。
この論文のサブタイトルは、「自動化・アプリ、真の効果は」であって、
革命的な進化発展である筈の自動化・アプリが、時には摩擦要因となって経済活動を阻害し始めていて、生産性を低下させている。と言う問題提起である。
最近は、殆どの取引が、スマホやパソコンでのシャドーワークになって、途中で、一度暗礁に乗り上げると、二進も三進も行かなくなって、完全にお手上げ、
電話が掛かっても、何度もキーを叩かせられて、繋がったと思った挙句には長時間待たされて時間切れ、
企業モラルなど地に落ちた不況企業が大半なので、カスタマーサービスの片鱗さえ見えない体たらく、
自動化・アプリによるシャドーワークのトラブル続出でその解消に忙殺されて仕事にならない、
合理化のつもりで、初級レベルで賃金の低い仕事をシャドーワークにして、高級かつ知的労働者の仕事を邪魔する、何の技術進歩による生産性の向上か。と、頭に来ている著者ラナの顔が浮かぶようで面白い。
労働者の生産性が(特に米国で)低下していることは現在、経済の大きな謎だが、その一つは「シャドーワーク(影の仕事)」が増えていることだ。と言うのである。
シャドーワークという言葉は、1981年にオーストリアの哲学者で社会評論家のイバン・イリイチ氏が作った。イリイチ氏の考えでは、この中には、子育てや家事など、報酬を伴わない仕事すべてが含まれる。しかし最近では、技術を駆使して企業が仕事を顧客に押し付ける事例が増えている。と言うことだが、ラナの論点は、この最後の企業のシャドーワーク押しつけによって生産性が落ちているということである。
かつては他人に任せていた数多くの作業を、今では、時間を費やす無報酬で目に見えない仕事として、ほとんどの人がデジタル機器を使って自分自身でこなしている。銀行とのやり取りや旅行予約、飲食店での注文、食料品の袋詰めなど、あらゆる作業が含まれ、駐車料金の支払いや子供の宿題の把握、テクノロジーに関するトラブル対応などに必要なアプリをダウンロードして操作する。30年までに米国の仕事の4分の1が自動化の影響を大きく受けるとの予測があり、その規模は間違いなく膨大で、しかも拡大しつつある。
こうしたシャドーワークは人間の仕事を減らし、価格の引き下げにつながるといった見方もあるだろう。確かにそうかもしれないが、経済全体としてみた場合、効率的なのだろうか。
自分のスマホに新しいアプリをいくつかダウンロードして使っているが、ある百貨店への注文で生じた問題を解決しようと数時間を費やしたり、慣れないトラベルプラットフォームを使わざるを得なくなって使い方を覚えるために時間と労力を要したり、とにかくトラブル続きの連続で、
職を必要としていて、仕事を始めたばかりの労働者のほうがはるかにうまくこなせる作業を、高給取りの知識労働者である筆者が週に何時間も費やさざるを得ないことに問題はないのだろうか。
ジョセフ・スティグリッツ氏ら一部の経済学者が、シャドーワークは市場システムにとって外部不経済(社会への悪影響)となり、企業が労働コストを削減するために使いたくなる手段だと指摘している。
ランバート氏は、シャドーワーク増加の負の影響の一つとして、サービス業で初級レベルの仕事がなくなることを挙げている。米ブルッキングス研究所が19年に実施した調査では、最も賃金が低い仕事が自動化のリスクにさらされていることがわかった。これは、特に若年層や人種的マイノリティーの生活が脅かされることを意味する。
テクノロジーの進歩に追いつくために国家が教育を改善しない限り、こうした労働者の多くは仕事に就けなくなり、生産性や経済成長の低下につながる。
一方、自動化が一層進む社会では、人と接触することが全般的にぜいたくなこととなっている。本当のお金持ちは他の人にシャドーワークを頼んでいる。
テクノロジーは「摩擦」を減らすかもしれないし、自動化やアプリは確かに、利便をもたらしている。社会全体にかかるシャドーワークのコストを計測してみる価値はありそうだ。と言う。
さて、このシャドーワークだが、これまでに何度もこのブログで言及しているアルビン・トフラーが1980年に「第三の波」で明らかにした生産消費者(Proshumer)の概念と殆ど同じである。
国民所得統計には集計されないが、販売や交換の為ではなく、自分で使う為か自分の満足を得る為に、その生活や営みを通じて財やサービスを生み出す一般消費者を「生産消費者」と称し、主婦などはその典型で、
もう半世紀以上も前にサミュエルソンが、国民所得統計の不備について言及していた。
この傾向が、ICT革命によってAIやロボティックの進展などデジタル技術の活用によって、加速度的に発展し、生産消費者、そして、シャドーワークが増加して、経済活動の重要な位置を占めてきた。
この論文のサブタイトルは、「自動化・アプリ、真の効果は」であって、
革命的な進化発展である筈の自動化・アプリが、時には摩擦要因となって経済活動を阻害し始めていて、生産性を低下させている。と言う問題提起である。
最近は、殆どの取引が、スマホやパソコンでのシャドーワークになって、途中で、一度暗礁に乗り上げると、二進も三進も行かなくなって、完全にお手上げ、
電話が掛かっても、何度もキーを叩かせられて、繋がったと思った挙句には長時間待たされて時間切れ、
企業モラルなど地に落ちた不況企業が大半なので、カスタマーサービスの片鱗さえ見えない体たらく、
自動化・アプリによるシャドーワークのトラブル続出でその解消に忙殺されて仕事にならない、
合理化のつもりで、初級レベルで賃金の低い仕事をシャドーワークにして、高級かつ知的労働者の仕事を邪魔する、何の技術進歩による生産性の向上か。と、頭に来ている著者ラナの顔が浮かぶようで面白い。