日本ではアベノミクスとやらで、攻めの農業として輸出を念頭に農業政策が大きく転換した。農業の規模拡大で、効率化が進みコストダウンが起きて、雇用が生まれて輸出もできて、農業が栄えるというものである。ホントだろうか?
農業は規模拡大したところで、単に面積当たりの生産量が増えることはない。農業の基本は、太陽エネルギーを水と大地の力で植物に取り込むことである。このことは、自然界も含めてあらゆる生命を支える基本である。言い換えれば、生命を支えているのは植物の炭酸同化作用(光合成)と言える。
人類はこれを職業化(農業)することで、効率を上げてきた。農業とすることで、品種の改良や土地の肥培管理や灌漑などを行ってきた。
近代になって、化学肥料を投入し農薬を使い、機械を使うことで効率を上げてきた。
然し、植物の炭酸同化作用に大きな変化あるわけでない。化学物質を使って一
時の収量を上げても、長年経つと土地や生産物に様々な障害が起きることが判ってきた。化学物質を投入する無機農業は、土壌の保水力や地力一般を持続させることなく、一方的に収奪し異物を残すからである。
日本は、先進国の中では緯度が低くいが熱帯のようでもなく適量の日光量で、水も豊 富である。植物の炭酸同化作用から類推した、各国の数字が左の表である。(クリックすると大きくなります)
富である。植物の炭酸同化作用から類推した、各国の数字が左の表である。(クリックすると大きくなります)
一般的には、オーストラリアやアメリカの方が、農業生産性が高いと思われている。それは人間の労働力当りや、投入資本当たりの収入金額であって、土地や植物から見た真の姿ではない。
単位土地辺りから見た、植物の獲得するエネルギーの量は、日本や韓国の方が圧倒的に高いことが判る。
農業を大型化することは、高額な機械や施設を購入して、大量の化学物質を散布することである。自然の摂理を無視した、大型農業は地球を破壊し、大資本が儲かるだけの仕組みと言える。
その典型が、アベノミクスでありTPPである。これは人類破滅の選択 と言える。
と言える。
今年は、国連が決めた以前にも述べた世界家族農業年である。家族型農業が、農産物の安全性を保ち、環境を保全し、地域の雇用を保ち、地域紛争をなくし、飢餓人口を減らすと述べている。
世界的な食糧難が必ず起きる。そのためにも、農業を家族型の規模にしておく必要がある。そしてあらゆる地域で、食糧を自賄いさせ、食糧に自己責任を持たせる必要がある。それが未来志向の農業である。
日本は全く逆の方向に向かっている。















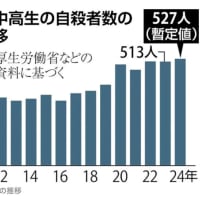




現在の遺伝子組み換え(モンサント)+大規模農業は、おそらく、安倍内閣はTPPも含めこれを実現する目算でしょうが、結局は旧ソ連のルイセンコ+ミチユーリン農法の再現になるのではと危惧しています。
話は飛びますが、太陽光パネル、気象の変化により、風害が門隊になっています。
植物は自分で支えを生産し(蔓草もありますが)、風にも負けずに、生き残った個体群が種となっています。光を個体システムで最大限に利用できるように、葉のシステムも進化してきました。進化とは、一方向にまとまるのではなく、環境に適応して広がることでしょう。
現在のグローバリゼーションの根幹は、資本の決済システムがその要です。この思考方式を訂正する、少なくとも実際の現象にしたがい見直す必要が今の世界にはあると考えています。
「工場畜産」の爆発的拡大が生む百害」
http://toyokeizai.net/articles/-/46919
残念なことに、著者は日本人ではないです。
ぼくは、文学上での生態学的思考は、
日本では宮澤賢治からと思っていますが、
今では、幅広く日本人から失われてしまったのではないかと考えています。
マスメディアと教育の賜物でしょうか。
あるいは、数字を追求する結果でしょうか?