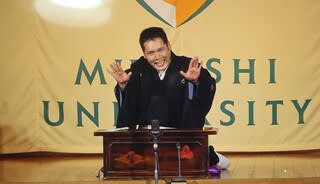
コロナウイルス騒ぎで、老人が危ないと言われているので、好きで通っていた観劇に東京へ行くのは、今年一杯諦めようと思っている。
三世帯同居で、小学生の孫息子と幼稚園の孫娘がいるので、バスや電車に乗るのさえも気になるからである。
久しぶりに、Youtubeを叩いて、神田伯山の「中村仲蔵」を見た。 動画【講談】神田伯山「中村仲蔵」in 浅草演芸ホール(2020年2月21日口演)だったが、流石に人気絶頂の講談師だけあって、実に素晴らしい。
国立演芸場で、真打ち披露公演が実施される予定で期待していたのだが、コロナで、キャンセルされたし、チケット取得が至難の業だという。
歌舞伎ファンなので、仮名手本忠臣蔵の五段目の斧定九郞にからむ中村仲蔵の逸話は知っており、落語だが、 三笑亭夢太朗の「中村 仲蔵」を聴いている。
講談も落語も演者によるバリエーションがあって興味深いのだが、物語の中心テーマとなるのは、
仮名手本忠臣蔵が上演されることになり、名題に昇進した仲蔵が期待していたにも拘わらず、与えられたのは五段目の斧定九郎一役、客が無視する「弁当幕」の端役なので意気消沈。気を取り直した仲蔵は、なにより定九郎の着付けが良くないと思て、何か良い工夫がないか必死に考え、柳島の妙見様に日参するも効果がない。お詣りを済ませた後、急に大粒の雨が降り出し、近くの蕎麦屋に駆け込む。そこへ歳の頃なら32、3歳の浪人風の粋な格好の武士が飛び込んできた。色は白い痩せ型の男で、着物は黒羽二重で尻をはしょっていて、朱鞘の大小落とし差しに茶博多の帯で、その帯には福草履を挟んでいる。破れた蛇の目傘を半開きにして入って来て、傘をすぼませてさっと水を切ってポーンと放りだし、伸びた月代を抑えて垂れた滴を拭うと、濡れた着物の袖を絞って、蕎麦を注文。
この光景を見て感激した仲蔵が、趣向を考えて新しい斧定九郞像を作り上げて、大成功を収めて座頭にまで出世するという人情話である。
この五段目に、何故、食い詰めて山賊に落ちぶれた斧定九郞が登場するのか、仮名手本忠臣蔵のフィクションの面白さだが、痩せても枯れても斧定九郞は、赤穂5万3千石の家老の息子、
夜具縞のどてらとまるくけの帯、たっつけ袴に五枚重ねのわらじに藤蔓巻きの山刀をさし、頭は百日カツラに赤顔、イグサで組んだ山岡頭巾(くすぺでぃあ)と言う山賊姿では、似つかわしくないし注目もされない汚れ役と言うこともあろうが、これを、粋でニヒルな二枚目浪人に変えて見せ場としたのだから、いうならば、歌舞伎の舞台のイノベーションである。
さて、初演の当日、花道を傘を半開きにした仲蔵の定九郎が現われると、あまりにも違っている定九郎に客席は水を打ったようにシーンと静まり返る。
オーオー、見たこともない見事な工夫じゃないか、日本一! との掛け声が掛かると思って期待していた仲蔵は、客席の無反応にこれはやり損なったかと勘違いするが最後まで演じて楽屋を去る。
猪と間違えて寛平が討った鉄砲が、定九郞に当たると、卵を潰して顔に擦り付けて、たらたら瀕死の表情・・・伯山の真に迫った語り口が仲蔵の決死の思いを表しており、異変を察した子供が泣き出してその声だけが静まりかえった舞台に響き渡り、仲蔵はがっくり倒れ込み、楽屋に帰ると嘲笑の声、絶望した仲蔵が、とぼとぼ死に場を探して歩いていると、
途中、人形町末広のあたりで、仲蔵の斧定九郞にいたく感動した通人が、スゲぇ芝居だったと観劇の感動を若い者に語りかける、これを聞いていた仲蔵は男泣き、
翌日からも大入り満員、しかし、この観客の熱狂ぶりを仲蔵だけが知らなかったのだが、
5日目の舞台で、先の通人が、大声で「堺屋、見事な工夫だ、日本一!」、観衆が唱和して歓声の嵐、
若侍の登場から、役の工夫、必死の舞台、絶望と意気消沈、認められた感動・・・目まぐるしく展開する仲蔵の心と動きを、実に情感豊かにビビッドに表現しながら感動を呼ぶ語り口に、張り扇のリズミカルなテンポ。緩急自在で、メリハリの効いた軽快な語りが何とも言えないが、通人と若者との仮名手本忠臣蔵のしっとりとした対話を一つ取っても、しみじみとした話術の冴えに深い味がある。
さて、落語の方では、絶望した仲蔵が、江戸に居られないと妻と別れて旅に出るのだが、親方中村伝九郎の呼び出しを受けて絶賛されると言う話になっており、志ん生では、引っ越し荷物で道具屋とコミカルな掛け合いがあって面白い。先代の圓楽では、まだ、成功を分っていなかった仲蔵が、伝九郞にわびを入れて泣きつくシーンが続いてしっとりとした師弟の語りを見せている。駆け出しの頃から苦楽をともにし、今生の別れだと泣いていた女房との語りも味がある。お祝いにたばこ入れを貰って帰り、妻に煙に巻かれたようだよと言われて、貰ったのがたばこ入れだ。
仲蔵が、何故、名題にもかかわらず、端役の定九郞を振り当てられたのか、貞心や志ん生は、仲蔵が名題に出世し、団十郎が相変わらず仲蔵の面倒を見るので、これが面白くなかったのが座付き作者の金井三笑が、仲蔵に嫌な役ばかりを振り当てたと語っている。
ところが、四代目團十郎に悴がいて、藝を競っていた仲蔵が妨げにならないように慮ったとか、先代の圓楽では、ヤケになっていたのを、女房が、團十郎が仲蔵へ飛躍挑戦へのチャンスを与えたのだと説得させる人情話になっていて、仲蔵を発憤させていて面白い。
三世帯同居で、小学生の孫息子と幼稚園の孫娘がいるので、バスや電車に乗るのさえも気になるからである。
久しぶりに、Youtubeを叩いて、神田伯山の「中村仲蔵」を見た。 動画【講談】神田伯山「中村仲蔵」in 浅草演芸ホール(2020年2月21日口演)だったが、流石に人気絶頂の講談師だけあって、実に素晴らしい。
国立演芸場で、真打ち披露公演が実施される予定で期待していたのだが、コロナで、キャンセルされたし、チケット取得が至難の業だという。
歌舞伎ファンなので、仮名手本忠臣蔵の五段目の斧定九郞にからむ中村仲蔵の逸話は知っており、落語だが、 三笑亭夢太朗の「中村 仲蔵」を聴いている。
講談も落語も演者によるバリエーションがあって興味深いのだが、物語の中心テーマとなるのは、
仮名手本忠臣蔵が上演されることになり、名題に昇進した仲蔵が期待していたにも拘わらず、与えられたのは五段目の斧定九郎一役、客が無視する「弁当幕」の端役なので意気消沈。気を取り直した仲蔵は、なにより定九郎の着付けが良くないと思て、何か良い工夫がないか必死に考え、柳島の妙見様に日参するも効果がない。お詣りを済ませた後、急に大粒の雨が降り出し、近くの蕎麦屋に駆け込む。そこへ歳の頃なら32、3歳の浪人風の粋な格好の武士が飛び込んできた。色は白い痩せ型の男で、着物は黒羽二重で尻をはしょっていて、朱鞘の大小落とし差しに茶博多の帯で、その帯には福草履を挟んでいる。破れた蛇の目傘を半開きにして入って来て、傘をすぼませてさっと水を切ってポーンと放りだし、伸びた月代を抑えて垂れた滴を拭うと、濡れた着物の袖を絞って、蕎麦を注文。
この光景を見て感激した仲蔵が、趣向を考えて新しい斧定九郞像を作り上げて、大成功を収めて座頭にまで出世するという人情話である。
この五段目に、何故、食い詰めて山賊に落ちぶれた斧定九郞が登場するのか、仮名手本忠臣蔵のフィクションの面白さだが、痩せても枯れても斧定九郞は、赤穂5万3千石の家老の息子、
夜具縞のどてらとまるくけの帯、たっつけ袴に五枚重ねのわらじに藤蔓巻きの山刀をさし、頭は百日カツラに赤顔、イグサで組んだ山岡頭巾(くすぺでぃあ)と言う山賊姿では、似つかわしくないし注目もされない汚れ役と言うこともあろうが、これを、粋でニヒルな二枚目浪人に変えて見せ場としたのだから、いうならば、歌舞伎の舞台のイノベーションである。
さて、初演の当日、花道を傘を半開きにした仲蔵の定九郎が現われると、あまりにも違っている定九郎に客席は水を打ったようにシーンと静まり返る。
オーオー、見たこともない見事な工夫じゃないか、日本一! との掛け声が掛かると思って期待していた仲蔵は、客席の無反応にこれはやり損なったかと勘違いするが最後まで演じて楽屋を去る。
猪と間違えて寛平が討った鉄砲が、定九郞に当たると、卵を潰して顔に擦り付けて、たらたら瀕死の表情・・・伯山の真に迫った語り口が仲蔵の決死の思いを表しており、異変を察した子供が泣き出してその声だけが静まりかえった舞台に響き渡り、仲蔵はがっくり倒れ込み、楽屋に帰ると嘲笑の声、絶望した仲蔵が、とぼとぼ死に場を探して歩いていると、
途中、人形町末広のあたりで、仲蔵の斧定九郞にいたく感動した通人が、スゲぇ芝居だったと観劇の感動を若い者に語りかける、これを聞いていた仲蔵は男泣き、
翌日からも大入り満員、しかし、この観客の熱狂ぶりを仲蔵だけが知らなかったのだが、
5日目の舞台で、先の通人が、大声で「堺屋、見事な工夫だ、日本一!」、観衆が唱和して歓声の嵐、
若侍の登場から、役の工夫、必死の舞台、絶望と意気消沈、認められた感動・・・目まぐるしく展開する仲蔵の心と動きを、実に情感豊かにビビッドに表現しながら感動を呼ぶ語り口に、張り扇のリズミカルなテンポ。緩急自在で、メリハリの効いた軽快な語りが何とも言えないが、通人と若者との仮名手本忠臣蔵のしっとりとした対話を一つ取っても、しみじみとした話術の冴えに深い味がある。
さて、落語の方では、絶望した仲蔵が、江戸に居られないと妻と別れて旅に出るのだが、親方中村伝九郎の呼び出しを受けて絶賛されると言う話になっており、志ん生では、引っ越し荷物で道具屋とコミカルな掛け合いがあって面白い。先代の圓楽では、まだ、成功を分っていなかった仲蔵が、伝九郞にわびを入れて泣きつくシーンが続いてしっとりとした師弟の語りを見せている。駆け出しの頃から苦楽をともにし、今生の別れだと泣いていた女房との語りも味がある。お祝いにたばこ入れを貰って帰り、妻に煙に巻かれたようだよと言われて、貰ったのがたばこ入れだ。
仲蔵が、何故、名題にもかかわらず、端役の定九郞を振り当てられたのか、貞心や志ん生は、仲蔵が名題に出世し、団十郎が相変わらず仲蔵の面倒を見るので、これが面白くなかったのが座付き作者の金井三笑が、仲蔵に嫌な役ばかりを振り当てたと語っている。
ところが、四代目團十郎に悴がいて、藝を競っていた仲蔵が妨げにならないように慮ったとか、先代の圓楽では、ヤケになっていたのを、女房が、團十郎が仲蔵へ飛躍挑戦へのチャンスを与えたのだと説得させる人情話になっていて、仲蔵を発憤させていて面白い。
























