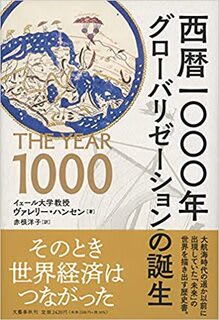
イエール大学のヴァレリー・ハンセン 教授の「西暦1000年 グローバリゼーションの誕生」
The Year 1000: When Explorers Connected the World―and Globalization Began
グローバリゼーションは、一般的には、コロンブスの活躍など大航海時代のヨーロッパ人の世界進出によって始まったとされているが、そうではなく、もっと前の西暦1000年に、大胆な探検と大胆な通商ミッションによって、初めて世界のすべての偉大な社会が結び付いた。
これがグローバリゼーションの始まりだとする画期的な歴史的研究だと言うのがこの本。
バイキングや中東、アジア、アフリカなどヨーロッパ以外の民族によるグローバル化で既に世界は繋がっており、その開発開化された世界の現状に乗ったが故に、大航海時代以降、ヨーロッパ人がかくも広大な地域を迅速に文化文明化し得たのである。
古代中国の四大発明、すなわち、羅針盤、火薬、紙、印刷術を最も活用してキャッチアップした西欧が、次代の成長発展をリードしたと言うことである。
先日レビューしたが、私が興味を感じたのは、西暦1000年頃に、バイキングが、既に、中米のチチェン・イッツァに到達していて、遺跡の「戦士の神殿」の壁画にその証拠が残っている。と言う著者の見解であった。
アメリカを発見したのは、コロンブスでもアメリゴ・ヴェスプッチでもなくバイキングであったというのは既知だが、このバイキングが、コロンブスに500年も先んじてアメリカに到達して一時定住し、太平洋横断ルートを切り開き、1000年には、アメリカ先住民族が、南北アメリカを貫通するパン・アメリカンハイウェイなど、既に精緻な交易ネットワークを構築していたので、世界を一周する輪を完成させた。と言うのである。
著者は、これらを実証するために、西暦1000年を中心にして大航海時代以前の世界の歴史を克明に分析して、活写していて読ませる。
アメリカに向かったバイキングの分派ルーシ人が、東欧に進行してロシアを建国して、スラブ人奴隷や毛皮をイスラム圏まで輸出して財を成し、ギリシャ正教に改宗する経緯などを語っていて、ウクライナ戦争の遠因が分かるような気がするのも、歴史学の良いところであろうか。
イスラム教の勢力拡大で、アフリカもグローバリゼーションに繰り込まれて、マリ王を世界一の大富豪に押し上げたというから面白い。
特に、興味深いのは、広大なユーラシア大陸を舞台にした文化文明そして宗教圏や国家の衝突攻防であり、
海上では、中国・東南アジアからインド、中東のイスラム圏、アフリカ東岸にかけての広大な交易圏の熾烈な交易やその盛衰が興味深い。
しかし、良く考えてみれば、遅れていたのは西欧だけで、
中国は、その何百年も前から大帝国を築いた文明国であり、遅ればせながら歴史を開いた日本でさえ、西暦1000年なら平安時代で、大航海時代は室町時代であり、既に高度な文化国家であり、中国と日本とは密接な交易があった。
西暦630年には、国際都市長安に第一次遣唐使を派遣しており、持ち帰った正倉院の御物を見れば、既に、中国がグローバル化していたことが分かる。
マルコ・ポーロでさえ、1280年代に国際都市として活況を呈していた中国の泉州を訪れて驚嘆していたが、
特筆すべきは、鄭和が、永楽帝時代1405年に、中国史上最大の大船団を率いて遠洋航海に出奔し、インドからアラビアを経てアフリカの東岸に達する大遠征航海であり、それに遅れたコロンブスの船団とは桁違いに壮大なスケールであった。
また、中東やアフリカ東岸からインド洋沿岸、東アジアの日本やインドネシアに至る地域は、既に、アラビアやインドや中国やアジアの商人たちが幅広く交易に明け暮れて国際商品が行き交うグローバル市場であった。バスコ・ダ・ガマが拓いたのは、喜望峰までの航路だけなのである。
さて、グローバリゼーションを、どう定義するかによって解釈は違ってくるが、要は、西欧は、大航海時代までは、イスラム圏にブロックされていたのか、喜望峰以遠のアジア方面との直接的な接触がなく、そして、南北アメリカはその存在さえ認知されておらず、これらの地域は、現実的には、新大陸であり新国家であったのであろう。
1453年にコンスタンチノープルが陥落して東ローマ帝国が滅亡するまで、西欧文化圏の東限はここまでで、その後、さらに後退するなど、独立した諸国が併存していた分裂状態の西欧の歴史的勢力圏は、高度な文化文明を誇っていたイスラム圏や中国圏などと比較して、脆弱であったということで、
著者は、西暦1000年の世界の歴史をグローバリゼーションの幕開けとして展望することで、西洋優位の歴史を、書き換えようとしたのであろうか。
The Year 1000: When Explorers Connected the World―and Globalization Began
グローバリゼーションは、一般的には、コロンブスの活躍など大航海時代のヨーロッパ人の世界進出によって始まったとされているが、そうではなく、もっと前の西暦1000年に、大胆な探検と大胆な通商ミッションによって、初めて世界のすべての偉大な社会が結び付いた。
これがグローバリゼーションの始まりだとする画期的な歴史的研究だと言うのがこの本。
バイキングや中東、アジア、アフリカなどヨーロッパ以外の民族によるグローバル化で既に世界は繋がっており、その開発開化された世界の現状に乗ったが故に、大航海時代以降、ヨーロッパ人がかくも広大な地域を迅速に文化文明化し得たのである。
古代中国の四大発明、すなわち、羅針盤、火薬、紙、印刷術を最も活用してキャッチアップした西欧が、次代の成長発展をリードしたと言うことである。
先日レビューしたが、私が興味を感じたのは、西暦1000年頃に、バイキングが、既に、中米のチチェン・イッツァに到達していて、遺跡の「戦士の神殿」の壁画にその証拠が残っている。と言う著者の見解であった。
アメリカを発見したのは、コロンブスでもアメリゴ・ヴェスプッチでもなくバイキングであったというのは既知だが、このバイキングが、コロンブスに500年も先んじてアメリカに到達して一時定住し、太平洋横断ルートを切り開き、1000年には、アメリカ先住民族が、南北アメリカを貫通するパン・アメリカンハイウェイなど、既に精緻な交易ネットワークを構築していたので、世界を一周する輪を完成させた。と言うのである。
著者は、これらを実証するために、西暦1000年を中心にして大航海時代以前の世界の歴史を克明に分析して、活写していて読ませる。
アメリカに向かったバイキングの分派ルーシ人が、東欧に進行してロシアを建国して、スラブ人奴隷や毛皮をイスラム圏まで輸出して財を成し、ギリシャ正教に改宗する経緯などを語っていて、ウクライナ戦争の遠因が分かるような気がするのも、歴史学の良いところであろうか。
イスラム教の勢力拡大で、アフリカもグローバリゼーションに繰り込まれて、マリ王を世界一の大富豪に押し上げたというから面白い。
特に、興味深いのは、広大なユーラシア大陸を舞台にした文化文明そして宗教圏や国家の衝突攻防であり、
海上では、中国・東南アジアからインド、中東のイスラム圏、アフリカ東岸にかけての広大な交易圏の熾烈な交易やその盛衰が興味深い。
しかし、良く考えてみれば、遅れていたのは西欧だけで、
中国は、その何百年も前から大帝国を築いた文明国であり、遅ればせながら歴史を開いた日本でさえ、西暦1000年なら平安時代で、大航海時代は室町時代であり、既に高度な文化国家であり、中国と日本とは密接な交易があった。
西暦630年には、国際都市長安に第一次遣唐使を派遣しており、持ち帰った正倉院の御物を見れば、既に、中国がグローバル化していたことが分かる。
マルコ・ポーロでさえ、1280年代に国際都市として活況を呈していた中国の泉州を訪れて驚嘆していたが、
特筆すべきは、鄭和が、永楽帝時代1405年に、中国史上最大の大船団を率いて遠洋航海に出奔し、インドからアラビアを経てアフリカの東岸に達する大遠征航海であり、それに遅れたコロンブスの船団とは桁違いに壮大なスケールであった。
また、中東やアフリカ東岸からインド洋沿岸、東アジアの日本やインドネシアに至る地域は、既に、アラビアやインドや中国やアジアの商人たちが幅広く交易に明け暮れて国際商品が行き交うグローバル市場であった。バスコ・ダ・ガマが拓いたのは、喜望峰までの航路だけなのである。
さて、グローバリゼーションを、どう定義するかによって解釈は違ってくるが、要は、西欧は、大航海時代までは、イスラム圏にブロックされていたのか、喜望峰以遠のアジア方面との直接的な接触がなく、そして、南北アメリカはその存在さえ認知されておらず、これらの地域は、現実的には、新大陸であり新国家であったのであろう。
1453年にコンスタンチノープルが陥落して東ローマ帝国が滅亡するまで、西欧文化圏の東限はここまでで、その後、さらに後退するなど、独立した諸国が併存していた分裂状態の西欧の歴史的勢力圏は、高度な文化文明を誇っていたイスラム圏や中国圏などと比較して、脆弱であったということで、
著者は、西暦1000年の世界の歴史をグローバリゼーションの幕開けとして展望することで、西洋優位の歴史を、書き換えようとしたのであろうか。
























