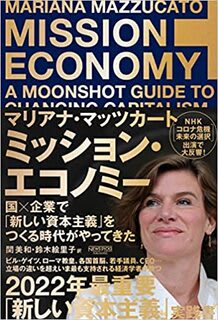
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン経済学教授のマリアナ・マッツカートの「ミッション・エコノミー:国×企業で「新しい資本主義」をつくる時代がやってきた Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism」が面白い。
”行き過ぎた新自由主義による「スタートアップ盲信」「民営化盲信」の時代は終わった。これからは国と企業が手を取り合い、万人のウェルビーイングからSDGsまで巨大なミッションを掲げ、経済を成長させながら「公共の目的(パーパス)」をかなえていく時代だ。それこそが「新しい資本主義」の姿である――。”というこの本、
別に新しい思想でも新規な経済学でもないのだが、現在、市場経済優先の民主導の自由主義経済が、機能麻痺して暗礁に乗り上げているので、政府主導の確固たる高度なビジョンに基づいたアポロ計画に匹敵した官民協調の経済に移行するよう軌道修正すべきであるという「資本主義の変革論」の提言である。
岸田首相の「新しい資本主義」批判はひかえておくが、このMission Economyこそ、真っ当な「新しい資本主義」への経済学理論であり、今日望むべき経済成長戦略であり、示唆に富んだ経済政策であると言えようか。
今回は、「21世紀のすべてはアポロ計画の波及効果」という論点だけに絞って考えてみたいと思う。
この本の”第4章 いま、アポロ計画こそが「最高の教訓」である”において、アポロ計画6つの教訓のうち「波及効果:セレンディピティとコラボレーション」で言及されているポイントなのだが、最大のイノベーションであるポータブルコンピュータを筆頭に「宇宙探索がなければ実現しなかったこと20のこと」が図入りで説明されていて、その裾野の凄さに驚かされる。
興味深いのは,冒頭で、「飢えた子供よりロケットの方が大事なのか」との疑問を呈して、「人々を救う発明は「無駄」から生まれる」と、
ドイツの伯爵が貧しい人に施していたが、レンズを磨きながら装置を作っている職人にも援助していたので批判されたが、この実験こそ、後に病気や貧困、飢餓との闘いに効果を上げた顕微鏡発明への道を拓いた、研究や発見にお金を一部当てることで、疫病が蔓延している地域にすべてを投じるよりははるかに多くの人を救ったことを例証して、
栄養、衛生、エネルギー、医療など、貧困に対処するための多くの重要な進歩が、一見目の前の課題とは関係なさそうな科学研究からもたらされると説いている。
NASAのストリンガー科学部長が、世界中に貧困と病苦に喘ぐ多くの人類が存在するのに、大金を使って月を目指すのが正義かと問われて、
技術的問題を解決する中で、大きな進歩は直接的な取り組みから生まれるのではなく、高い目的を設定するところから生まれる。それが大きなやりがいに繋がり、想像力をかき立てて、人々の最善の努力を引き出し、それがきっかけとなって次々と連鎖反応が起きる。と述べている。
これこそが、アポロ効果であり、同時に、国防総省のDARPAが、ARPANETに投資してインターネットを生んだのだが、ICT革命への道標の多くが、アメリカのスプートニック・ショックへの対応という冷戦への投資から生まれたと言うのが興味深い。
さて、それでは、新冷戦時代のウクライナ戦争は、どの様な遺産を人類に残すのであろうか。
いずれにしろ、今こそ、アポロ計画級の壮大な新しいミッション・エコノミーを打ち上げて資本主義を変革しなければならないと檄を飛ばしているのである。
”行き過ぎた新自由主義による「スタートアップ盲信」「民営化盲信」の時代は終わった。これからは国と企業が手を取り合い、万人のウェルビーイングからSDGsまで巨大なミッションを掲げ、経済を成長させながら「公共の目的(パーパス)」をかなえていく時代だ。それこそが「新しい資本主義」の姿である――。”というこの本、
別に新しい思想でも新規な経済学でもないのだが、現在、市場経済優先の民主導の自由主義経済が、機能麻痺して暗礁に乗り上げているので、政府主導の確固たる高度なビジョンに基づいたアポロ計画に匹敵した官民協調の経済に移行するよう軌道修正すべきであるという「資本主義の変革論」の提言である。
岸田首相の「新しい資本主義」批判はひかえておくが、このMission Economyこそ、真っ当な「新しい資本主義」への経済学理論であり、今日望むべき経済成長戦略であり、示唆に富んだ経済政策であると言えようか。
今回は、「21世紀のすべてはアポロ計画の波及効果」という論点だけに絞って考えてみたいと思う。
この本の”第4章 いま、アポロ計画こそが「最高の教訓」である”において、アポロ計画6つの教訓のうち「波及効果:セレンディピティとコラボレーション」で言及されているポイントなのだが、最大のイノベーションであるポータブルコンピュータを筆頭に「宇宙探索がなければ実現しなかったこと20のこと」が図入りで説明されていて、その裾野の凄さに驚かされる。
興味深いのは,冒頭で、「飢えた子供よりロケットの方が大事なのか」との疑問を呈して、「人々を救う発明は「無駄」から生まれる」と、
ドイツの伯爵が貧しい人に施していたが、レンズを磨きながら装置を作っている職人にも援助していたので批判されたが、この実験こそ、後に病気や貧困、飢餓との闘いに効果を上げた顕微鏡発明への道を拓いた、研究や発見にお金を一部当てることで、疫病が蔓延している地域にすべてを投じるよりははるかに多くの人を救ったことを例証して、
栄養、衛生、エネルギー、医療など、貧困に対処するための多くの重要な進歩が、一見目の前の課題とは関係なさそうな科学研究からもたらされると説いている。
NASAのストリンガー科学部長が、世界中に貧困と病苦に喘ぐ多くの人類が存在するのに、大金を使って月を目指すのが正義かと問われて、
技術的問題を解決する中で、大きな進歩は直接的な取り組みから生まれるのではなく、高い目的を設定するところから生まれる。それが大きなやりがいに繋がり、想像力をかき立てて、人々の最善の努力を引き出し、それがきっかけとなって次々と連鎖反応が起きる。と述べている。
これこそが、アポロ効果であり、同時に、国防総省のDARPAが、ARPANETに投資してインターネットを生んだのだが、ICT革命への道標の多くが、アメリカのスプートニック・ショックへの対応という冷戦への投資から生まれたと言うのが興味深い。
さて、それでは、新冷戦時代のウクライナ戦争は、どの様な遺産を人類に残すのであろうか。
いずれにしろ、今こそ、アポロ計画級の壮大な新しいミッション・エコノミーを打ち上げて資本主義を変革しなければならないと檄を飛ばしているのである。
























