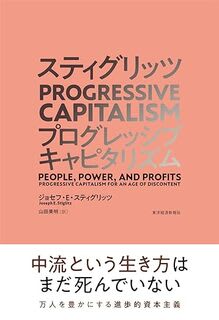
スティグリッツ 教授の本で、一番資本主義について易しく本質論を説いたのは、この本「PROGRESSIVE CAPITALISM (プログレッシブ キャピタリズム): 利益はみんなのために]」だと思っているのだが、危機に瀕した資本主義の起死回生のために、過剰な富がもたらす政治力に対抗出来るほど力強い民主主義がなければ出来ないと、政治改革をも巻き込んだ、ドラスティックな経済改革を提言していて、非常に面白い。
最近のこのコラムのブックレビューでは、書評ではなく、私が注目したトピックスについて書くことにしているので、今回は、ネガティブなイノベーションについて考えてみたいと思う。
イノベーションと言えば、企業や国家の成長発展のために最も寄与する原動力で、救世主のような扱いだが、このイノベーションが、時には成長発展の足を引っ張ることがあると言うのである。
市場支配力を乱用して反競争的行為を推進するイノベーションである。
スティグリッツ教授が、真っ先に糾弾するのは、マイクロソフトが、新たな形態の参入障壁や、既存の企業を追い払うずる賢い方法に長けている、20世紀末に、競争を制限しようとしたかっての大企業を手本に、そのような面で先進的なイノベーションを築き上げたとして、1990年代のインターネットブラウザーを巡る闘いで、新興企業に利益を侵害されるのを恐れて、ネットスケープを追い払ったことである。ほぼ独占状態であったインターネットエクスプローラーには、ネットスケープほどの魅力は無く実力だけでは勝てないので、OS市場での支配力を利用して、OSと抱き合わせ、無料で提供して、殆どのパソコンにエクスプローラーを組み込んだ。さらに、ネットスケープは相互運用性に問題があると言うFUD(恐怖・不安・疑念)戦術を展開して、ネットスケープをインストールすればパソコンの機能が損なわれる恐れがあるとユーザーに警告した。そのほかの様々な反競争的行為を通じて、ネットスケープを市場から追い出した。
現在でも、市場支配力を乱用するテクノロジー系の大企業はあとを絶たない。と言う。
また、特許は一時的な参入障壁になるので、特許制度を悪用して競争を制限する手もある。現在のイノベーションでは、多くの特許が必要となり、ある会社が新製品をつくれば、無数にある特許のどれかを知らないうちに侵害している恐れがあり、特に、大企業同士での特許共有システムに阻まれ、新規参入企業などには「特許侵害」訴訟の資金的余裕がないので、諦めるケースが多い。
実際、クアルコム対アップル、アップル対サムスンなど、数億ドル規模の訴訟が無数にあるが、訴訟で得をするのは弁護士だけで、損をするのは、競争に参加できない小企業や消費者であり、これが、21世紀の米国流資本主義だ、と言うのである。
その他にも、クレジット業界では、顧客から手数料を取るのを禁じて、事実上価格競争を回避して、様々なサービス提供コストとして任意に加盟店手数料を徴収するなど、市場支配力を利用して新たな契約規定を生み出している。また、米国の製薬企業は、ジェネリック医薬品企業の締め出しを図るなど、どの産業も、市場支配力を維持する独自の方法を見つけようと創意工夫を凝らしている。
しかし、市場支配力が増大した大半の原因は、暗黙のルールの変更、特に、反トラスト法の基準の低下で、以前よりも容易に、市場支配力を産み出し、利用し、悪用できるようになり、また、現行の反トラスト法が、変わりゆく経済に対応出来ていない。
合併・買収の規模が、史上最高を更新しており、不適切な競争政策により、Google、Facebook、Amazonなど、ある程度の市場支配力を持つ企業は、その力を高め、広げ、利用し、持続させてゆくことが可能な状態にある。と言う。
これらの叙述は、迷走する資本主義の、「搾取と市場支配力」という章でのスティグリッツ教授の見解だが、一寸毛色が変ったイノベーション論ながら興味深い。
大企業の支配市場力が、価格を釣り上げ、従業員の所得賃金を押し下げるなど利益追求に汲々としていると言うことで、ひいては、資本主義の機能不全を引き起こして成長発展を阻害している言うことであろうが、イノベーションと言っても、シュンペーターのイノベーション論から言っても、概念は広くて、プロダクトイノベーションだけではない。
私が疑問に思うのは、これが民主主義に、そして、真っ当な資本主義に似つかわしいのかどうか、米国のロビー制度である。
財力のある大企業は、1人のロー・メーカー連邦議員に対して何倍もの弁護士などロビー活動要員を送り込んで懐柔策を推進して利益誘導を図っており、特に、巨大テック企業などは、「テック企業を解体せよ」と言う運動に抗して、規制の弱体化を目指して、ロビー活動を加速させている。
石油会社やタバコ会社などのロビー活動の悪害はつとに有名であるが、他の業界も活発にロビーイングを展開している。
さて、激しさを増すイスラエルーハマス戦争、世界最強のアメリカのイスラエル・ロビーは、どう動いているのであろうか。アメリカのイスラエルに対する異常とも言うべき入れ込み方を見れば、そのパワーが分かろうと言うもの。
最近のこのコラムのブックレビューでは、書評ではなく、私が注目したトピックスについて書くことにしているので、今回は、ネガティブなイノベーションについて考えてみたいと思う。
イノベーションと言えば、企業や国家の成長発展のために最も寄与する原動力で、救世主のような扱いだが、このイノベーションが、時には成長発展の足を引っ張ることがあると言うのである。
市場支配力を乱用して反競争的行為を推進するイノベーションである。
スティグリッツ教授が、真っ先に糾弾するのは、マイクロソフトが、新たな形態の参入障壁や、既存の企業を追い払うずる賢い方法に長けている、20世紀末に、競争を制限しようとしたかっての大企業を手本に、そのような面で先進的なイノベーションを築き上げたとして、1990年代のインターネットブラウザーを巡る闘いで、新興企業に利益を侵害されるのを恐れて、ネットスケープを追い払ったことである。ほぼ独占状態であったインターネットエクスプローラーには、ネットスケープほどの魅力は無く実力だけでは勝てないので、OS市場での支配力を利用して、OSと抱き合わせ、無料で提供して、殆どのパソコンにエクスプローラーを組み込んだ。さらに、ネットスケープは相互運用性に問題があると言うFUD(恐怖・不安・疑念)戦術を展開して、ネットスケープをインストールすればパソコンの機能が損なわれる恐れがあるとユーザーに警告した。そのほかの様々な反競争的行為を通じて、ネットスケープを市場から追い出した。
現在でも、市場支配力を乱用するテクノロジー系の大企業はあとを絶たない。と言う。
また、特許は一時的な参入障壁になるので、特許制度を悪用して競争を制限する手もある。現在のイノベーションでは、多くの特許が必要となり、ある会社が新製品をつくれば、無数にある特許のどれかを知らないうちに侵害している恐れがあり、特に、大企業同士での特許共有システムに阻まれ、新規参入企業などには「特許侵害」訴訟の資金的余裕がないので、諦めるケースが多い。
実際、クアルコム対アップル、アップル対サムスンなど、数億ドル規模の訴訟が無数にあるが、訴訟で得をするのは弁護士だけで、損をするのは、競争に参加できない小企業や消費者であり、これが、21世紀の米国流資本主義だ、と言うのである。
その他にも、クレジット業界では、顧客から手数料を取るのを禁じて、事実上価格競争を回避して、様々なサービス提供コストとして任意に加盟店手数料を徴収するなど、市場支配力を利用して新たな契約規定を生み出している。また、米国の製薬企業は、ジェネリック医薬品企業の締め出しを図るなど、どの産業も、市場支配力を維持する独自の方法を見つけようと創意工夫を凝らしている。
しかし、市場支配力が増大した大半の原因は、暗黙のルールの変更、特に、反トラスト法の基準の低下で、以前よりも容易に、市場支配力を産み出し、利用し、悪用できるようになり、また、現行の反トラスト法が、変わりゆく経済に対応出来ていない。
合併・買収の規模が、史上最高を更新しており、不適切な競争政策により、Google、Facebook、Amazonなど、ある程度の市場支配力を持つ企業は、その力を高め、広げ、利用し、持続させてゆくことが可能な状態にある。と言う。
これらの叙述は、迷走する資本主義の、「搾取と市場支配力」という章でのスティグリッツ教授の見解だが、一寸毛色が変ったイノベーション論ながら興味深い。
大企業の支配市場力が、価格を釣り上げ、従業員の所得賃金を押し下げるなど利益追求に汲々としていると言うことで、ひいては、資本主義の機能不全を引き起こして成長発展を阻害している言うことであろうが、イノベーションと言っても、シュンペーターのイノベーション論から言っても、概念は広くて、プロダクトイノベーションだけではない。
私が疑問に思うのは、これが民主主義に、そして、真っ当な資本主義に似つかわしいのかどうか、米国のロビー制度である。
財力のある大企業は、1人のロー・メーカー連邦議員に対して何倍もの弁護士などロビー活動要員を送り込んで懐柔策を推進して利益誘導を図っており、特に、巨大テック企業などは、「テック企業を解体せよ」と言う運動に抗して、規制の弱体化を目指して、ロビー活動を加速させている。
石油会社やタバコ会社などのロビー活動の悪害はつとに有名であるが、他の業界も活発にロビーイングを展開している。
さて、激しさを増すイスラエルーハマス戦争、世界最強のアメリカのイスラエル・ロビーは、どう動いているのであろうか。アメリカのイスラエルに対する異常とも言うべき入れ込み方を見れば、そのパワーが分かろうと言うもの。
























