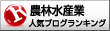1つは、高齢化である。本州方面では、平均就農者年齢が65才を越える集落が、3000とも4000とも言われている。程なく消滅し、日本の農業そのものの存続が危うい状況にある。日本農業の中で、担い手の年齢が一番若いとされる、酪農業でも高齢化が目立つ。
2番目は、穀物の高騰である。日本の畜産は大きく海外の穀物に飼料を依存している。家畜の食料(飼料)自給率は極めて低い。最も自給飼料の高い、根室地方でも50%程度 がやっとである。写真のように、夏に外で牧草を食べる姿が急速に減少して、牛を閉じこめたまま穀物多給形態が増加している。
がやっとである。写真のように、夏に外で牧草を食べる姿が急速に減少して、牛を閉じこめたまま穀物多給形態が増加している。
アメリカのコーンは、国の強力な援助を受けて、中西部で大きくエタノール生産に変わりつつある。すでに蒸留所が、100ヶ所以上稼働していて、58ヶ所が計画から建設に向かっている。アメリカの穀物の高騰は干ばつや買い付けなどの一時的なものでない。
因みに、北海道の酪農家が購入する穀物は、1年半前の30%高になっている。経営努力では乗り切れる限界になっている。
3番目は、乳価の急落である。酪農家の牛乳の販売価格がこの2年で7%も下落している。飲用乳の減少は、高齢化によるものかも知れないが、チーズなどの加工商品への移行は乳価を下げる結果になっている。
こうした世界的な動きの中で、日本の農業政策は出来もしない大型化をうたい文句に、健全な農業を蔑ろにしている。この国の住人は、日本に農業がいらなくても良いと思っているのだろうか。