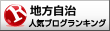今年は世界的な穀物増収の年であった。穀物の国際価格も比較的安定した年であった。上図はFAOのサイトの年次別月毎の国債取引価格の推移である。左は小麦、右はトウモロコシである。今年が際立って価格が低いのが解る。二年前の6割程度まで下がっているのである。
ところがこうした世界情勢を、大量に家畜に給与する立場の畜産農家は実感していない。その原因は、アベノミクスによって作られた円安にある。実体経済とは無縁の金融緩和策による、虚像が作り出した円安である。
何も農家だけではない。海外に60%もの食料を依存している日本の国民は、本来であれば安くなる畜産製品だけではなく関連の食料品、麺類やパンやマヨネーズは安くなるはずであるが、むしろ高くなっているのである。知人の先輩が作られた表から、食料に限ってみると経済成長著しい中国をはるかに上回るインフレ率、物価高となっていることが解る。消費税がこれに追い打ちをかける。デフレからの脱却は、食糧などのインフレ・物価高を生んだ。
自給率が極端に低い国でしか起きないこうした異常現象に、アベノミクスが作り出した円安が、さらに拍車をかけているのである。
アベノミクスは、トヨタなど輸出業者に膨大な利益をもたらしたかもしれないが、一般庶民にはインフレ率を上げるような働きしかしていない。とりわけ海外依存率の高い、自給率の低い食料に顕著に現れたのが今回の現象である。
だから、無関税システムのTPP参入はもっての他で、食糧自給率を高めることこそが重要なのである。穀物はこれからさらに戦略物質として、これまで以上に大きな存在となる。